|
- 日本葡萄酒の黎明期(1)-  高野正誠と土屋助次郎 |
原田義昭先生の栄えあるホームページに私の駄文《ボルドー便り》を掲載させていただいてから、今回で早や100回目を数えることになりました。大変感慨深いものがあります。政治家・弁護士のホームページには何も役に立たない駄文を、寛容な先生のご厚意についつい甘えてしまい8年間も自由気儘に書かせていただきました。原田先生には心から感謝申し上げますと共に、高校時代から現在に至るまで長きに亘って友情がつづいてきましたことを大変ありがたく思っております。そしてこの拙い文章をご愛読くださいました読者の皆様には改めて心から感謝と共に御礼申し上げます。ありがとうございました。 さて、今回は日本葡萄酒の黎明期に甲府勝沼からフランスへ派遣され、葡萄栽培とワインの醸造を学んできた二人の青年、高野正誠(25歳)と土屋助次郎(龍憲、19歳)の足跡を、明治という時代背景を思い浮かべながら辿ってみたいと思います。 さて、今回は日本葡萄酒の黎明期に甲府勝沼からフランスへ派遣され、葡萄栽培とワインの醸造を学んできた二人の青年、高野正誠(25歳)と土屋助次郎(龍憲、19歳)の足跡を、明治という時代背景を思い浮かべながら辿ってみたいと思います。元号が「明治」と改まって、わが国は文明開化の夜明けを迎えました。そして今回の舞台のひとつとなる山峡の甲斐国が明治4年(1872年)の廃藩置県で甲府県に変わり、間もなく山梨県に改名しました。この慌ただしく激動する世相の中で、明治政府は「富国強兵  」と共に「殖産興業」の政策を打ち出すのです。「これからは、新規事業だ。欧米並みの事業を興さなければ」と。時の為政者は中央政府のご機嫌を損ねてはと、「殖産興業」の旗印を掲げて文明開化の殿堂づくりに汲々としておりました。山梨県では藤村紫朗県令(県知事)自身が「殖産興業」に大変熱心で、それも西洋志向型の代表的人物でした。氏は自己の開明性、文化性を最大限に生かして、過去の陋習と旧弊を打破し、全てのものを西洋化に結び付けようと奔走しました。そのひとつとして甲州産の葡萄に逸早く着目し、明治9年(1877年)に甲府の舞鶴城跡に県立勧業試験場を建設し、同10年には県立葡萄酒醸造所を完成させ、全国に先駆けて西洋の酒づくりに着手したのです。そして同年10月には藤村県令の肝いりで葡萄の里、現在の勝沼町に法人組織の「大日本山梨葡萄酒会社(通称、祝村葡萄酒会社)」が産声をあげました。日本で初めての法人による葡萄酒会社を失敗なく操業していくためには、醸造技術と醸造法を完全に指導できる有能な人材が必要でありました。そこで村から優秀な青年をワインの本場フランスへ派遣し、醸造技術と施設の習得を併せて醸造用葡萄の品種の選別などを徹底的に学び取らせ、日本人の手による国産の良質な葡萄酒を生産しようとしたのです。明治の人たちの心意気は凄い! 」と共に「殖産興業」の政策を打ち出すのです。「これからは、新規事業だ。欧米並みの事業を興さなければ」と。時の為政者は中央政府のご機嫌を損ねてはと、「殖産興業」の旗印を掲げて文明開化の殿堂づくりに汲々としておりました。山梨県では藤村紫朗県令(県知事)自身が「殖産興業」に大変熱心で、それも西洋志向型の代表的人物でした。氏は自己の開明性、文化性を最大限に生かして、過去の陋習と旧弊を打破し、全てのものを西洋化に結び付けようと奔走しました。そのひとつとして甲州産の葡萄に逸早く着目し、明治9年(1877年)に甲府の舞鶴城跡に県立勧業試験場を建設し、同10年には県立葡萄酒醸造所を完成させ、全国に先駆けて西洋の酒づくりに着手したのです。そして同年10月には藤村県令の肝いりで葡萄の里、現在の勝沼町に法人組織の「大日本山梨葡萄酒会社(通称、祝村葡萄酒会社)」が産声をあげました。日本で初めての法人による葡萄酒会社を失敗なく操業していくためには、醸造技術と醸造法を完全に指導できる有能な人材が必要でありました。そこで村から優秀な青年をワインの本場フランスへ派遣し、醸造技術と施設の習得を併せて醸造用葡萄の品種の選別などを徹底的に学び取らせ、日本人の手による国産の良質な葡萄酒を生産しようとしたのです。明治の人たちの心意気は凄い!  先ずはフランス派遣の選考会を開き、最終的に派遣する青年二人を決めました。その二人が今回の話の主人公となる高野正誠(1852-1923)と土屋助次郎(龍憲、1858-1940)です。修業期間を一か年と定め、旅費、滞在費、研修費等は県内の葡萄生産地の予算(郡費)で賄うことになりました。出発日は明治10年(1878年)10月10日。横浜港から出航するフランス船タナイス号と決まりました。 先ずはフランス派遣の選考会を開き、最終的に派遣する青年二人を決めました。その二人が今回の話の主人公となる高野正誠(1852-1923)と土屋助次郎(龍憲、1858-1940)です。修業期間を一か年と定め、旅費、滞在費、研修費等は県内の葡萄生産地の予算(郡費)で賄うことになりました。出発日は明治10年(1878年)10月10日。横浜港から出航するフランス船タナイス号と決まりました。ご存知の通り、明治4年(1872年)11月には、岩倉具視を団長とする木戸孝充、大久保利通、伊藤博文をはじめ50人程の重要人物の一行が、古今東西の歴史にも例を見ないような壮大な旅をやってのけました。司馬遼太郎は、著書『明治という国家』の中で「世界史の何処に、新国家ができて早々  、革命の英雄豪傑たちが地球のあちこちを見てまわって、どのような国をつくるべきかうろついてみてまわった国があったでしょうか」と感嘆しています。この旅はなんと1年9か月余、632日という途方もなく長いものとなり、まだ混沌としていた明治初期の日本が、いかにして近代化を進め「明治という国家」をつくっていくかという歴史的課題に極めて大きな影響を与えたのです。それはまさに、日本近代化の原点にあたる旅でした。一行は行く先々で大歓迎を受け、その堂々たる立居振る舞い、礼儀作法は各国で絶賛されたのです。欧米各国はこの未知の民族について、異文化とはいえ、大変上質なものを感じたのでありましょう。 、革命の英雄豪傑たちが地球のあちこちを見てまわって、どのような国をつくるべきかうろついてみてまわった国があったでしょうか」と感嘆しています。この旅はなんと1年9か月余、632日という途方もなく長いものとなり、まだ混沌としていた明治初期の日本が、いかにして近代化を進め「明治という国家」をつくっていくかという歴史的課題に極めて大きな影響を与えたのです。それはまさに、日本近代化の原点にあたる旅でした。一行は行く先々で大歓迎を受け、その堂々たる立居振る舞い、礼儀作法は各国で絶賛されたのです。欧米各国はこの未知の民族について、異文化とはいえ、大変上質なものを感じたのでありましょう。だが、国内の政治状況が風雲急を告げたため、明治6年(1874年)5月には一足先に大久保利通だけが帰国します。帰国後、大久保は一年半に及ぶ欧米見分と世界の現状認識から「殖  産興業」を声高に叫びつづけました。そして大久保が政権を取るや逸早く勧業寮を設置しました。それは大久保が最も力を注いだ「殖産興業」の担当部門でした。つまり、新政権の目玉ともいうべき内務省を機関車として、工業を興し、農業を近代化し、総合的な国力を引き上げることを目指したのです。欧米文明探索の旅によって、大久保はその具体的な方法、とりわけ「殖産興業」の重要性を学んだことになります。そして、それは決して一足跳びにいくものではなく、着実に漸進的に発達を図らねばならない、と悟ったのです。司馬遼太郎は、「明治は、リアリズムの時代でした。それも、透きとおった、格調の高い精神で支えられたリアリズムでした」と述べております。「明治国家」とは、1868年から1912年まで44年間つづいた国家でした。 産興業」を声高に叫びつづけました。そして大久保が政権を取るや逸早く勧業寮を設置しました。それは大久保が最も力を注いだ「殖産興業」の担当部門でした。つまり、新政権の目玉ともいうべき内務省を機関車として、工業を興し、農業を近代化し、総合的な国力を引き上げることを目指したのです。欧米文明探索の旅によって、大久保はその具体的な方法、とりわけ「殖産興業」の重要性を学んだことになります。そして、それは決して一足跳びにいくものではなく、着実に漸進的に発達を図らねばならない、と悟ったのです。司馬遼太郎は、「明治は、リアリズムの時代でした。それも、透きとおった、格調の高い精神で支えられたリアリズムでした」と述べております。「明治国家」とは、1868年から1912年まで44年間つづいた国家でした。内務卿大久保利通によって奨められた「殖産興業」政策の一大スローガンの一翼の中に、葡萄と葡萄酒産業の興隆が、大きな眼目となって入っていたことは大変興味を惹くところです。葡萄と葡萄酒は、今では想像もつかないくらい、まるで日本の文明開化の食文化の象徴のように重要視されていたのです。 そして、遣米欧使節団が帰国してその僅か4年後の明治10年(1878年)には、早くも葡萄酒の世界で民間人によるフランスへの道が開かれたのであります。驚くべき速さで時代は動いていきます。明治の人たちの一連の行動の凄まじい勇気と心意気には感動を禁じえません。快挙といえば快挙、暴挙といえば暴挙なのかもしれませんが、いかにも痛快です。若さのなせる業なのでしょうか。  本題の高野と土屋の話に戻ります。派遣に先立ち藤村県令は二青年の渡航手続き、滞在中の世話などについて、恐れ多くも大久保利通にお願いしたのであります。大久保はこの申し出を快く引き受け、偶々フランスから帰国したばかりの前田正名(後の山梨県知事)に二人の世話を頼みます。薩摩人大久保は「貴方(おはん)、たのむ」とだけ前田に言ったのでしょう。前田はパリ万国博覧会の日本館事務局次長として再び渡仏することが決まっていたからです。 本題の高野と土屋の話に戻ります。派遣に先立ち藤村県令は二青年の渡航手続き、滞在中の世話などについて、恐れ多くも大久保利通にお願いしたのであります。大久保はこの申し出を快く引き受け、偶々フランスから帰国したばかりの前田正名(後の山梨県知事)に二人の世話を頼みます。薩摩人大久保は「貴方(おはん)、たのむ」とだけ前田に言ったのでしょう。前田はパリ万国博覧会の日本館事務局次長として再び渡仏することが決まっていたからです。高野と土屋は二日二晩歩きつづけて、横浜港近くの宿に着いたのは明治10年(1878年)10月7日のことでした。生まれて初めて見る海と船。見るもの聞くもの何もかもが初体験でした。外人居留地で洋服に着替えた二人は乗船前日、新橋から汽車で着いた前田正名を横浜駅で出迎えました。それも初対面でした。政府高官と民間人の二人の青年が初めて出会って、フランスの旅に一緒に 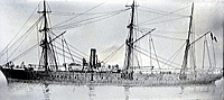 出掛ける。いかにも明治らしく何とも愉快です。その夜は前田の宿を訪れて夜遅くまでフランスのよもやま話を聞き入ったことでしょう。翌朝、前田に伴われてフランス船タナイス号に乗船しました。汽笛が消えて巨船は静かに岩壁を離れていきました。期待と不安が荒く波打つ鹿島立ちだったことでしょう。私がボルドーへ留学した時の気持ちと重なりますが、県の代表に選ばれ時代の先駆者として醸造を学びにフランスへ旅立った彼ら二人の責任は遥かに重くのしかかっていたと思います。 出掛ける。いかにも明治らしく何とも愉快です。その夜は前田の宿を訪れて夜遅くまでフランスのよもやま話を聞き入ったことでしょう。翌朝、前田に伴われてフランス船タナイス号に乗船しました。汽笛が消えて巨船は静かに岩壁を離れていきました。期待と不安が荒く波打つ鹿島立ちだったことでしょう。私がボルドーへ留学した時の気持ちと重なりますが、県の代表に選ばれ時代の先駆者として醸造を学びにフランスへ旅立った彼ら二人の責任は遥かに重くのしかかっていたと思います。一等船室の前田正名と違って、二人の三等船室は蒸し風呂のような暑さでした。前田とフランス派遣の高野と土屋を乗せたタナイス号は香港で三人を下し、彼らは別の船に乗り換えてシンガポールを経てインド洋を横断、セイロン島(現スリ  ランカ)のコロンボに寄港してアラビア海を横切り、1869年に開通したスエズ運河を抜けてポートサイド、ナポリに寄港し、フランス国マルセイユの波止場に着いたのは明治10年(1878年)11月24日のことでした。横浜を出港して実に45日間の長い船旅でした。その間船酔いと猛暑に苦しめられましたが、静かな洋上は夢の世界であったと述懐しています。寄港地で見るもの聞くもの全てが物珍しく、驚きと感動の連続だったことでしょう。 ランカ)のコロンボに寄港してアラビア海を横切り、1869年に開通したスエズ運河を抜けてポートサイド、ナポリに寄港し、フランス国マルセイユの波止場に着いたのは明治10年(1878年)11月24日のことでした。横浜を出港して実に45日間の長い船旅でした。その間船酔いと猛暑に苦しめられましたが、静かな洋上は夢の世界であったと述懐しています。寄港地で見るもの聞くもの全てが物珍しく、驚きと感動の連続だったことでしょう。マルセイユで下船して、前田正名のあとに従って旅客列車に乗り込んだ二青年は花の都パリに着きました。公使館の一室を借りてフランス語を習うため、近くの小学校へ通い始めます。一か月後にはいくらかフランス語が聞き取れるようになったといいますが、修業一か年の約束なので語学に時間をかける余裕はなかったようです。現在のように外国人向けのフランス語学校もない中で、二人が苦心惨憺されたであろうことは想像に難くありません。特に、私も苦労した醸造に関する難しい専門用語について、どのように習得していったのかも興味のあるところです。 そして二人は前田の案内で1878年のパリ万国博覧会を見物した後、愈々暮れも押し迫った12月28日にパリから150キロ程離れたシャンパーニュ地方オーブ県トロワ市に住む国際的な園芸研究家シャルル・  バルテの自宅を訪問しました。同氏は遥々日本から研修にやって来た二人を快く迎えてくれました。同氏を紹介したのも前田正名でありました。二人が車窓から初めて眺めたフランスの冬の葡萄畑は、すっかり丸坊主になった葡萄の株だけが寂しげに行儀よく並んでいたことでしょう。まるで幾何学模様のように。でも来るべき春にそなえて力を蓄えているような頼もしい感じを受け、彼らはきっと希望に目を輝かせていたように思えます。この景色は私がかつて車窓から見たボルドーの葡萄畑と二重写しになってきます。しかし、何故フランスの2大生産地のボルドーやブルゴーニュを選ばずに、敢えてトロワ市で研修することになったのかには依然疑問が残りますが、これも前田正名から知遇のあったシャルル・バルテに紹介する手筈が万端整っていたからなのでしょう。結果的には良い師と巡り会ったことになります。氏は「農業の改革は、一国だけの問題ではない。地球上の人類全てが豊かになるためのものです」と、繰り返し語ったといいます。そして、「研修に期限があるらしいから理論より実技をしっかり身につけた方がいい」と、もう一人の権威者ピエール・デュポンを紹介してくれました。私の経験からもフランス人は自国の文化を学んでいる者にはとても寛容で親切でした。時には親切過ぎるくらいに感じたものです。デュポンは同じトロワの町で手広く苗木 バルテの自宅を訪問しました。同氏は遥々日本から研修にやって来た二人を快く迎えてくれました。同氏を紹介したのも前田正名でありました。二人が車窓から初めて眺めたフランスの冬の葡萄畑は、すっかり丸坊主になった葡萄の株だけが寂しげに行儀よく並んでいたことでしょう。まるで幾何学模様のように。でも来るべき春にそなえて力を蓄えているような頼もしい感じを受け、彼らはきっと希望に目を輝かせていたように思えます。この景色は私がかつて車窓から見たボルドーの葡萄畑と二重写しになってきます。しかし、何故フランスの2大生産地のボルドーやブルゴーニュを選ばずに、敢えてトロワ市で研修することになったのかには依然疑問が残りますが、これも前田正名から知遇のあったシャルル・バルテに紹介する手筈が万端整っていたからなのでしょう。結果的には良い師と巡り会ったことになります。氏は「農業の改革は、一国だけの問題ではない。地球上の人類全てが豊かになるためのものです」と、繰り返し語ったといいます。そして、「研修に期限があるらしいから理論より実技をしっかり身につけた方がいい」と、もう一人の権威者ピエール・デュポンを紹介してくれました。私の経験からもフランス人は自国の文化を学んでいる者にはとても寛容で親切でした。時には親切過ぎるくらいに感じたものです。デュポンは同じトロワの町で手広く苗木 商を営む果樹の改良研究の実務家で、ワインの醸造もしていました。葡萄の品種改良とヨーロッパ式の新しい葡萄栽培法を実地で学びながらワイン醸造の研究も一か所でできるのはさぞ魅力だったことでしょう。早速、近くに下宿して、バルテとデュポン両氏の指導のもとでフル回転の研修がはじまりました。葡萄の剪定、挿し木法、品種改良の接ぎ木法、摘果、収穫の実技を習いながら、葡萄品種の研究等々、今のような仏和辞典もワイン用語辞典もない中での実技と理論の極めて厳しい日課は、想像するに余りあるものを感じます。この研修の成果を、殆ど知識のない故郷の人たちへ正確に伝えるために丹念にスケッチした資料が残っています。昼は作業、夜は記録と、難解な栽培法や醸造法を抱えて日夜大変な時を過ごしたことでありましょう。少しくらい失敗しても腰砕けにならず、また挑戦したのでしょう。その元気さのエッセンスとは何か・・・。それは明治の人の中にあった命をかけた使命感そして進取の気性だったように思います。 商を営む果樹の改良研究の実務家で、ワインの醸造もしていました。葡萄の品種改良とヨーロッパ式の新しい葡萄栽培法を実地で学びながらワイン醸造の研究も一か所でできるのはさぞ魅力だったことでしょう。早速、近くに下宿して、バルテとデュポン両氏の指導のもとでフル回転の研修がはじまりました。葡萄の剪定、挿し木法、品種改良の接ぎ木法、摘果、収穫の実技を習いながら、葡萄品種の研究等々、今のような仏和辞典もワイン用語辞典もない中での実技と理論の極めて厳しい日課は、想像するに余りあるものを感じます。この研修の成果を、殆ど知識のない故郷の人たちへ正確に伝えるために丹念にスケッチした資料が残っています。昼は作業、夜は記録と、難解な栽培法や醸造法を抱えて日夜大変な時を過ごしたことでありましょう。少しくらい失敗しても腰砕けにならず、また挑戦したのでしょう。その元気さのエッセンスとは何か・・・。それは明治の人の中にあった命をかけた使命感そして進取の気性だったように思います。兎に角、明治という時代が時代だっただけに、その気勢が人間にも乗り移って、飛び切りの元気者を輩出させたというべきでしょうか。当時の人には、気概というか、気迫というか、要するに気力が目いっぱい充実していたように思われてなりません。次回は高野、土屋の帰国後の活動を中心に語ってまいりたいと思います。 最後に、原田義昭先生の国政復帰が必ずや成就しますことを心からお祈り申し上げます。 |
| |