|
閑話―「仏蘭西学事始」(3)

晩年の村上英俊 |
村上英俊のその後の人生を追ってまいります。時代は日進月歩であり、英俊が苦労して修めたフランス語の知識も日を追って色褪せていくように思われてきました。
 「エゲブテ(埈及)とは何だ、あれはオランダ読みで、エヂプトと読むのが本当だそうだ」、「先生の仏蘭西語は仏蘭西に通じないという珍物だ」と、門下生の間に陰口が呟かれていたことは前回でも述べましたが、それが時を経るにつれ盛んに聞かれるようになってきました。その頃には、仏蘭西學の大家の座は明らかに英俊から箕作麟祥(1846-1897、法学者、教育者、和仏法律学校(現法政大学)初代校長、祖父は箕作阮甫、)へ移っていたのです。その箕作といえば、英俊が「達理堂」を開塾した慶應3年(1867年)に、徳川民部昭武がパリ万国博覧会に将軍の名代として渡仏した時に随行し、フランスとイギリスの両国で学び、翌年に帰朝しています。いわば本場仕込みのフランス語を達者にあやつる御仁として、その評判は頗る高かったのです。そして、明治3年(1870年)頃になると、「達理堂」の門人のうちから箕作のもとへと走る者が次々に出てくるようになってしまいました。 「エゲブテ(埈及)とは何だ、あれはオランダ読みで、エヂプトと読むのが本当だそうだ」、「先生の仏蘭西語は仏蘭西に通じないという珍物だ」と、門下生の間に陰口が呟かれていたことは前回でも述べましたが、それが時を経るにつれ盛んに聞かれるようになってきました。その頃には、仏蘭西學の大家の座は明らかに英俊から箕作麟祥(1846-1897、法学者、教育者、和仏法律学校(現法政大学)初代校長、祖父は箕作阮甫、)へ移っていたのです。その箕作といえば、英俊が「達理堂」を開塾した慶應3年(1867年)に、徳川民部昭武がパリ万国博覧会に将軍の名代として渡仏した時に随行し、フランスとイギリスの両国で学び、翌年に帰朝しています。いわば本場仕込みのフランス語を達者にあやつる御仁として、その評判は頗る高かったのです。そして、明治3年(1870年)頃になると、「達理堂」の門人のうちから箕作のもとへと走る者が次々に出てくるようになってしまいました。
なお、「達理堂」(この名称は『三語便覧』に既に達理堂蔵と記されているように、  かなり早くから用いられていたようです)が開塾された年は、英俊が9カ年に亘って関係をもった開成所を引退した時でもあって、時間の余裕が出てきたのか、従来の門下生だけではなく、もっと広く門人を募ろうとの考えから塾を公にすることにしました。すると、「達理堂」の門を叩く若者が全国から集まってきたのです。最盛期には400余名に達していたといわれています。英俊の塾に最初に駆けつけた門下生の中には、兆民中江篤介(1847-1897、思想家、政治家、ジャン・ジャック・ルソーを紹介し、日本における自由民権運動の理論的指導者)がいましたが、のちに破門されてしまいます。遊蕩が過ぎたことに原因があったようです。「達理堂」の門下生の中からは、このように維新後の日本を動かした人物を数多く輩出しています。英俊は門人には非常に親切であり、春には墨田川の堤に出て花見をし、帰途には料亭で馳走もしていたし、病人が出れば深夜といえども自ら診察に赴いたというように、門人の面倒をよくみていたようです。 かなり早くから用いられていたようです)が開塾された年は、英俊が9カ年に亘って関係をもった開成所を引退した時でもあって、時間の余裕が出てきたのか、従来の門下生だけではなく、もっと広く門人を募ろうとの考えから塾を公にすることにしました。すると、「達理堂」の門を叩く若者が全国から集まってきたのです。最盛期には400余名に達していたといわれています。英俊の塾に最初に駆けつけた門下生の中には、兆民中江篤介(1847-1897、思想家、政治家、ジャン・ジャック・ルソーを紹介し、日本における自由民権運動の理論的指導者)がいましたが、のちに破門されてしまいます。遊蕩が過ぎたことに原因があったようです。「達理堂」の門下生の中からは、このように維新後の日本を動かした人物を数多く輩出しています。英俊は門人には非常に親切であり、春には墨田川の堤に出て花見をし、帰途には料亭で馳走もしていたし、病人が出れば深夜といえども自ら診察に赴いたというように、門人の面倒をよくみていたようです。
しかしながら、前述したように仏蘭西學の主たる指導的立場は英俊から箕作麟祥へと移っており、英俊はついに明治10年(1877年)になると、「達理堂」を閉塾してしまいます。門人をとらないようになると、たちまち困るようになったのは、その経済生活です。明治5年には妻を亡くしており、一子榮太郎は放蕩三昧の生活で家に寄りつかず、とうてい頼れる状況になかったのです(榮太郎は明治16年に33歳の若さで逝去)。もはや英俊には昔日の姿はなく、フランス語を教えるという気力すら萎えてしまっておりました。生計を立てるには英俊のフランス語はあまりにも旧式なものになっていたのでありましょう。だが、フランス語の知識そのものはまだ十分に活用できるとの希望だけは捨てていませんでした。そこで英俊はフランス語と共に長年かけて修めた化学、とりわけヨード(沃度)の研究を完成しようと考えたのです。これが成功すれば、生計の心配も消えてしまうかもしれない。英俊は医薬品の分野で、このヨードの研究を役立てようとしたのです。明治12年(1879年)にはその研究を仕上げ、内務省から製薬免許證が与えられるまでになり、英俊は老躯に鞭打って製薬場の設置に奔走しましたが、残念ながらヨードの製造販売の事業は計画倒れに終わってしまったようです。そして、ついに英俊は生涯でもっとも不幸な状態に陥ってしまいました。英俊の生活は窮乏を極め、かつての仏蘭西學の大家の面影はどこにも見当たらないほどの落魄ぶりでありました。 しかし、英俊の運命の星は強かったのです。英俊の窮境をいつまでも放っておくほど、かつて世話になった門人たちは薄情に過ぎることはなかったのです。門下生の一人は、当時英俊が一室を借りて侘び住まいをしていた寺を訪れて、そこの8畳間で独り黙々と食事をとっている老いた英俊の姿に接して驚き、旧師のあまりの悲惨な生活ぶりを仲間たちに知らせました。みなで相談の結果、家賃のための拠金をして、これを英俊に届けることになりました。やがて英俊もかつての門下生宅へ足を運ぶようになり、時には料亭で門人たちと食事を共にすることもあったようです。こうして、英俊の身辺は少しばかり賑わいをみせるようになっていきました。 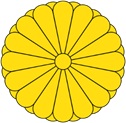 門人たちは英俊のこのような落魄を悲しみ、これを救うには門人たちの拠金、饗応というような個人的な援助ではなく、もっと抜本的な策を講ずる必要を覚えました。国家的に英俊の功績を顕彰しなくてはならないと。英俊はそれに充分値する功績のある御仁であったからです。門下生たちは英俊のために文部省当局に働きかけるべく奔走しました。そして、ついに明治15年(1882年)に、村上英俊は東京學士會院会員に満場一致で選出されることになりました。英俊はこの名誉を担って、翌年から『東京學士會院誌』に「血液論」の翻訳を連載しはじめるのです。英俊にとって、どん底から一躍絶頂にのぼりつめたうれしさはいかばかりのものがあったことでしょう。 門人たちは英俊のこのような落魄を悲しみ、これを救うには門人たちの拠金、饗応というような個人的な援助ではなく、もっと抜本的な策を講ずる必要を覚えました。国家的に英俊の功績を顕彰しなくてはならないと。英俊はそれに充分値する功績のある御仁であったからです。門下生たちは英俊のために文部省当局に働きかけるべく奔走しました。そして、ついに明治15年(1882年)に、村上英俊は東京學士會院会員に満場一致で選出されることになりました。英俊はこの名誉を担って、翌年から『東京學士會院誌』に「血液論」の翻訳を連載しはじめるのです。英俊にとって、どん底から一躍絶頂にのぼりつめたうれしさはいかばかりのものがあったことでしょう。
 名誉といえば、明治18年(1885年)になって、フランス大統領からレジョン・ドヌール・シュヴァリエ勲章が英俊に授けられるという栄誉に浴しました。日本における仏蘭西學創始、これが叙勲の理由でありました。更に、翌19年には、文部省から東京學士會院会員に授与される年金も与えられ、これで生活の心配はまったくなくなりました。東京學士會院会員として国内での栄誉を誇り、レジョン・ドヌール勲章叙勲者として国外での名声を得て、英俊は学界にその存在を重くしたのであります。そして佛學會の名誉会員にも推されています。英俊の晩年にとって、輝ける残照でありました。 名誉といえば、明治18年(1885年)になって、フランス大統領からレジョン・ドヌール・シュヴァリエ勲章が英俊に授けられるという栄誉に浴しました。日本における仏蘭西學創始、これが叙勲の理由でありました。更に、翌19年には、文部省から東京學士會院会員に授与される年金も与えられ、これで生活の心配はまったくなくなりました。東京學士會院会員として国内での栄誉を誇り、レジョン・ドヌール勲章叙勲者として国外での名声を得て、英俊は学界にその存在を重くしたのであります。そして佛學會の名誉会員にも推されています。英俊の晩年にとって、輝ける残照でありました。
この頃、英俊は北豊島郡金杉村(現在の東京都台東区金杉町)で静かに余生を送っておりましたが、明治23年(1890年)1月10日、肺炎により78年に亘る生涯を閉じました。宮内省からも特使が派遣され、仏蘭西學の功績を讃えて祭粢料が下賜されました。葬儀は青山墓地で執り行われ、英俊の門に学んで、既に明治の政界、学界などでしかるべき地位をしめている旧門下生が多数会葬したといわれております。 これまで3回に亘って、世にあまり知られていない、わが国仏蘭西學の始祖と讃えられた村上英俊の波乱万丈の人生について物語ってきました。少しでも村上英俊という人物に思いを馳せていただけましたら幸甚に存じます。 それでは次に、昔々購入していたことを忘れかけていましたが、村上英俊の『三語便覧』をきっかけに思い出したメルメ・ド・カション著『佛英和辭典(FRANÇAIS-ANGLAIS-JAPONAIS)』について語ってみようと思います。メルメ・ド・カション(Mermet de CACHON,1828-1871(?))は、1828年にスイス国境近くの「ヴァン・ジョーヌ(vin jaune,黄色いワイン)」や「ヴァン・ド・パイユ(vin de paille、麦藁のワイン)」のワイン産地として有名なジュラ地方にある、ラ・ベッスのショードザンブルという集落で生まれました。ラ・ベッスはパイプの産地として知られているサン・クロードから20キロほど離れたジュラ山中の寒村です。カションはそのサン・クロードの神学校に学び、聖職者としての生涯を歩み始めました。1852年になると、カションはパリに赴き、パリ外国宣教会神学校に入学しています。ここは、海外へ多数の宣教師を派遣し、カトリックの布教に尽力している神学校です。そこで司祭となり、1854年に日本に向けて勇躍パリを出発することになりました。  1855年に、カションは2人の宣教師を伴って沖縄那覇に到着し、やがて松尾という町に住み、日本語の学習に専念することになります。ところが、宣教師として使命を果たすためには様々な障害につきあたったようで、宗教上の反感から結局僅か1名の日本人を洗礼させたにすぎず、翌1856年には健康を害し、静養のために一時香港に渡らなくてはなりませんでした。 そして、1858年(安政5年)には、日仏通商条約締結の全権公使としてグロ男爵の来日に際し、カションも通訳として同行し、初めて神奈川・下田の地を踏んだのであります。奇しくも、英俊がこの日仏通商条約の締結にあたって、仏国へ手交した条約文作成に係ったのではないかともいわれているように、英俊は日仏外交の裏舞台で、そしてカションはその表舞台で活躍していたとは、何とも面白い歴史の巡り合わせのように思います。   余談ですが、2008年に日仏交流150周年(150ème anniversaire des relations franco-japonaises)の記念事業が執り行われ、私の主催するワイン会が在日フランス大使館によって正式にその事業のひとつに認めていただけたのは誠に嬉しい思い出です。何よりも日仏交流150周年の栄えある記念事業に少しだけでも携わることができたのは、フランスとフランス・ワインをこよなく愛するひとりとして感慨深いものがありました。 余談ですが、2008年に日仏交流150周年(150ème anniversaire des relations franco-japonaises)の記念事業が執り行われ、私の主催するワイン会が在日フランス大使館によって正式にその事業のひとつに認めていただけたのは誠に嬉しい思い出です。何よりも日仏交流150周年の栄えある記念事業に少しだけでも携わることができたのは、フランスとフランス・ワインをこよなく愛するひとりとして感慨深いものがありました。
さて、カションは条約締結後、一旦香港に戻りましたが、翌1859年には開港直後の箱館(函館)へ赴任することになりました。そして寺の境内に家を借り司祭館とし、教会堂を建て、塾を開きフランス語を教え、更に病院をも設立しようとしたのです。カションが箱館に滞在したということは極めて注目される事柄で、とりわけ、この地で栗本鋤雲(1822-1897、外国奉行、勘定奉行、箱館奉行を歴任。思想家。パリ万博に随行)をはじめ塩田三郎(1843-1897、外交官。清国特命全権大使)、立廣作(文久遣欧使節通訳)などの幕末から明治にかけて外交舞台で活躍した人たちにフランス語を教えたことは、その後の日仏関係の展開を促す上で大きな意味をもつことになっていきます。更には本題の『佛英和辞典』(1866年)をはじめ『アイヌ。起源、言語、風俗、宗教』(1863年)の編纂、そして今年世界文化遺産に登録され、国宝にも指定答申された富岡製糸場の先駆けともなる、栗本鋤雲が殖産興業の一環として熱意をもって取り組んだ養蚕育成の事実が、カションをして日本における養蚕への関心を深めさせたことは、『養蠶秘録』(1866年)の翻訳となって現れています。カションの『佛英和辞典』の編纂やアイヌ語語彙の蒐集、養蚕事業に対する関心などは全て箱館滞在時の成果でありました。 次回はカションの『佛英和辞典』等の著述をはじめ幕末から明治維新期にかけて、日本での活動の足跡とその人となりについて語ってみたいと思います。 |