|
マドリードの旅(7)

「ボティン(Botin)」 |
| マドリード最後の日は、今回の旅ですっかりお世話になったキロスさんとお母様を昼餐にお招きし、お別れ会をすることにしました。さて何処にご招待するか、いろいろガイドブックで探して、仔豚の丸焼き(コチニージョ・アサド,Cochinillo asado)で有名な、世界で最も古いレストランといわれ、ギネスブックにも認定されている1725年創業の「ボティン(Botín)」に決め予約しました。
先ずは、名物の仔豚料理に入る前に、 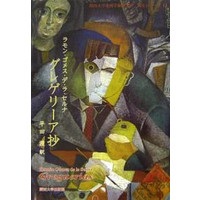 この店は19世紀から20世紀に至るスペイン文学をはじめ英米文学の作家による小説、戯曲等の舞台に数多く登場していますのでご紹介しましょう。スペイン文学の至宝といわれるラモン・ゴメス・デ・ラ・セルナ(1888-1963)は短詩型の散文作品集『グレゲリーア抄』の中で、「ボティンは偉大なレストランだ。新鮮な材料を、使い込んだ年代物の鍋で調理する」、「クチリェロス通りにある旧いボティンに、乳飲み豚あり。感動すべき乳飲み豚を前にして、まるでわが子たちを見るようで泣き出したりしたものだ。果ては、“洗礼を受けたものは大金で、洗礼を受けていないものは目一杯お安く”と私たちに言い出しそうに思えてきた」と。後に英国に帰化したアルトゥーロ・バレーア(1897-1957)は、マドリードの当時の風俗を描いた作品の中で、「・・・一人で、または私たちのうちの誰かと、マドリードの非常に伝統あるレストラン・ボティンに行って、仔豚の丸焼きを注文する。彼女は一人で(もし誰も同行していなければ)、大きな器に盛られたレタスと、1リットルのワインと共に、その仔豚を平らげる」等々。そして多くの英米文学の作家たちが、スペイン滞在中に貴族の館の佇まいを残す「ボティン」に魅了され、彼らの作品に登場させています。『第三の男』、『ハバナの男』等で有名な英国のグレアム・グリーン(1904-1991)は晩年の作『キホーテ神父』の中で、「暗紫色の靴下を買う前に、ボティンでうまい食事と行こうじゃないか」と。もっと新しいところでは、『ジャッカルの日』で有名な、同じく英国の作家、フレデリック・フォーサイス(1938-)が作品の中に登場させています。でも、何と言ってもこの店の創業家のゴンザレス一族と強い絆で結ばれていたのが、アーネスト・ヘミングウェイ(1899-1961)です。 この店は19世紀から20世紀に至るスペイン文学をはじめ英米文学の作家による小説、戯曲等の舞台に数多く登場していますのでご紹介しましょう。スペイン文学の至宝といわれるラモン・ゴメス・デ・ラ・セルナ(1888-1963)は短詩型の散文作品集『グレゲリーア抄』の中で、「ボティンは偉大なレストランだ。新鮮な材料を、使い込んだ年代物の鍋で調理する」、「クチリェロス通りにある旧いボティンに、乳飲み豚あり。感動すべき乳飲み豚を前にして、まるでわが子たちを見るようで泣き出したりしたものだ。果ては、“洗礼を受けたものは大金で、洗礼を受けていないものは目一杯お安く”と私たちに言い出しそうに思えてきた」と。後に英国に帰化したアルトゥーロ・バレーア(1897-1957)は、マドリードの当時の風俗を描いた作品の中で、「・・・一人で、または私たちのうちの誰かと、マドリードの非常に伝統あるレストラン・ボティンに行って、仔豚の丸焼きを注文する。彼女は一人で(もし誰も同行していなければ)、大きな器に盛られたレタスと、1リットルのワインと共に、その仔豚を平らげる」等々。そして多くの英米文学の作家たちが、スペイン滞在中に貴族の館の佇まいを残す「ボティン」に魅了され、彼らの作品に登場させています。『第三の男』、『ハバナの男』等で有名な英国のグレアム・グリーン(1904-1991)は晩年の作『キホーテ神父』の中で、「暗紫色の靴下を買う前に、ボティンでうまい食事と行こうじゃないか」と。もっと新しいところでは、『ジャッカルの日』で有名な、同じく英国の作家、フレデリック・フォーサイス(1938-)が作品の中に登場させています。でも、何と言ってもこの店の創業家のゴンザレス一族と強い絆で結ばれていたのが、アーネスト・ヘミングウェイ(1899-1961)です。
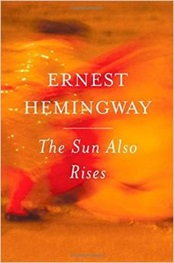 当時、ヘミングウェイはパエリアのつくり方に非常に興味があったとのことですが、タイプライターの扱いと同様に料理も苦手だったようです。ヘミングウェイはスペインをこよなく愛し、マドリードについては、「スペインで最もスペインらしい都市である」、「プラド美術館、その北へ2時間のところにエスコリアル修道院、南にトレド、アビラへと続く美しい道、そしてラ・グランハからほど近いセゴビアへ通じるもうひとつの美しい道、これら全てを有するマドリードにいたら、いつかこの世を去る日、これら全ての美しいものに別れを告げなければならないことに絶望感を抱くことだろう」とまで述べています。熱烈な闘牛の愛好者であり擁護者でもあったヘミングウェイは、闘牛を題材にした『午後の死』の中で、ボティンについて触れています。「・・・だがその間、夕食にボティンで仔豚でも食べた方がましだ。座り込んで友人たちが苦しむ事故のことを考えているよりは・・・」。そしてあの名作『日はまた昇る』の最後の舞台としてボティンが登場します。「ボティンの2階で昼食をとる。ここは世界中で最高のレストランのひとつだ。コチニージョ・アサド(仔豚の丸焼き)を食べて、リオハ・アルタのワインを飲んだ。ブレットはそれほど食べなかった。彼女は常に小食なのだ。私はといえば、非常によく食べ、リオハ・アルタのワインを3本飲んだ」とあります。『日はまた昇る』を書き上げたテーブルが、まだその場所に残されています。画家のゴヤはこの店で皿洗いのアルバイトをしていたとか。 当時、ヘミングウェイはパエリアのつくり方に非常に興味があったとのことですが、タイプライターの扱いと同様に料理も苦手だったようです。ヘミングウェイはスペインをこよなく愛し、マドリードについては、「スペインで最もスペインらしい都市である」、「プラド美術館、その北へ2時間のところにエスコリアル修道院、南にトレド、アビラへと続く美しい道、そしてラ・グランハからほど近いセゴビアへ通じるもうひとつの美しい道、これら全てを有するマドリードにいたら、いつかこの世を去る日、これら全ての美しいものに別れを告げなければならないことに絶望感を抱くことだろう」とまで述べています。熱烈な闘牛の愛好者であり擁護者でもあったヘミングウェイは、闘牛を題材にした『午後の死』の中で、ボティンについて触れています。「・・・だがその間、夕食にボティンで仔豚でも食べた方がましだ。座り込んで友人たちが苦しむ事故のことを考えているよりは・・・」。そしてあの名作『日はまた昇る』の最後の舞台としてボティンが登場します。「ボティンの2階で昼食をとる。ここは世界中で最高のレストランのひとつだ。コチニージョ・アサド(仔豚の丸焼き)を食べて、リオハ・アルタのワインを飲んだ。ブレットはそれほど食べなかった。彼女は常に小食なのだ。私はといえば、非常によく食べ、リオハ・アルタのワインを3本飲んだ」とあります。『日はまた昇る』を書き上げたテーブルが、まだその場所に残されています。画家のゴヤはこの店で皿洗いのアルバイトをしていたとか。
 また前置きが長くなってしまいましたので、コチニージョ・アサド(仔豚の丸焼き)の料理の話に入ります。コチニージョ・アサドは、もともとはマドリードから北西へ95キロほどの標高1000メートルの岩山の上にある城塞都市セゴビアの名物料理として知られていました。むろん仔豚の丸焼きの本場というだけのところではありません。ここは紀元前8世紀にケルト人によって築かれ、その後ローマ帝国の要地となり、西ゴート族に受け継がれ、一時イスラム教徒の支配下に入ったが、レコンキスタ(国土回復運動)の結果再びキリスト教徒のものとなった誇り高い古都で、カスティーリアの女王イサベルがここで戴冠式をしたという由緒あるところでもあります。ここはブルゴス等と並んで、カスティーリア地方の旅の途上で通り過ぎることができない町ですが、今回は日程の都合で残念ながら訪ねることができませんでした。 また前置きが長くなってしまいましたので、コチニージョ・アサド(仔豚の丸焼き)の料理の話に入ります。コチニージョ・アサドは、もともとはマドリードから北西へ95キロほどの標高1000メートルの岩山の上にある城塞都市セゴビアの名物料理として知られていました。むろん仔豚の丸焼きの本場というだけのところではありません。ここは紀元前8世紀にケルト人によって築かれ、その後ローマ帝国の要地となり、西ゴート族に受け継がれ、一時イスラム教徒の支配下に入ったが、レコンキスタ(国土回復運動)の結果再びキリスト教徒のものとなった誇り高い古都で、カスティーリアの女王イサベルがここで戴冠式をしたという由緒あるところでもあります。ここはブルゴス等と並んで、カスティーリア地方の旅の途上で通り過ぎることができない町ですが、今回は日程の都合で残念ながら訪ねることができませんでした。
「ボティン」で、卵入りニンニク・スープ(Sopa de ajo con huevo)を食べ終わる頃に、コチニージョ・アサド(仔豚の丸焼き)が堂々たる姿で登場しました。  本当に丸焼きで、顔もちゃんとついています。仔豚の表情が残っているのを食べるのには、「郷に入れば郷に従え」の少々勇気が必要です。私たちには、これもスペイン風と思われるかもしれませんが、多かれ少なかれ肉食人種には、動物をその生きていた姿のままで一度認めてから食べる風習があるのでしょう。日本でも魚については鯛の姿煮とか刺身の活造りがあるように。外皮はこんがりとカラメル色に焼けているが、下地の肉は薄い飴色で、ところどころ清楚なピンクの部分も見えます。皮にナイフを入れてばらすと、肉の繊維がふわり、ぱらりとほぐれ、柔らかな髪の束のようにほどけてゆきます。何とも美味そうです。口に入れると、先ずトロリとする。優しいゼラチン質と脂肪が頬の内側に広がり、顎と舌が自然に動きはじめる。皮も肉も弾力を失わない程度に柔らかく、歯から舌へと、舌から喉へとスムーズに運ばれる。塩味もくどくない。岩塩かもしれません。そして美味い!これは八角などで香と味をつける広州の烤乳猪とは違い、殆ど塩味だけのあっさりした料理であるから、肉の質が余程良くないとこうは美味くならないし、焼き加減も問題でしょう。材料にしても竈にしても理想的な状態が必要となります。春の野原にこんもりと茂る木立のような、あるいはその木立の下に湧く泉に射す陽光のような、優しい女性的な自然の味がしました。森や草原の光景を思い浮かべながら食べ進むうちに、少しずつ満足感がみなぎってきました。今思いかえしてみても、やはり美味かったというほかはありません。 本当に丸焼きで、顔もちゃんとついています。仔豚の表情が残っているのを食べるのには、「郷に入れば郷に従え」の少々勇気が必要です。私たちには、これもスペイン風と思われるかもしれませんが、多かれ少なかれ肉食人種には、動物をその生きていた姿のままで一度認めてから食べる風習があるのでしょう。日本でも魚については鯛の姿煮とか刺身の活造りがあるように。外皮はこんがりとカラメル色に焼けているが、下地の肉は薄い飴色で、ところどころ清楚なピンクの部分も見えます。皮にナイフを入れてばらすと、肉の繊維がふわり、ぱらりとほぐれ、柔らかな髪の束のようにほどけてゆきます。何とも美味そうです。口に入れると、先ずトロリとする。優しいゼラチン質と脂肪が頬の内側に広がり、顎と舌が自然に動きはじめる。皮も肉も弾力を失わない程度に柔らかく、歯から舌へと、舌から喉へとスムーズに運ばれる。塩味もくどくない。岩塩かもしれません。そして美味い!これは八角などで香と味をつける広州の烤乳猪とは違い、殆ど塩味だけのあっさりした料理であるから、肉の質が余程良くないとこうは美味くならないし、焼き加減も問題でしょう。材料にしても竈にしても理想的な状態が必要となります。春の野原にこんもりと茂る木立のような、あるいはその木立の下に湧く泉に射す陽光のような、優しい女性的な自然の味がしました。森や草原の光景を思い浮かべながら食べ進むうちに、少しずつ満足感がみなぎってきました。今思いかえしてみても、やはり美味かったというほかはありません。
  この仔豚の丸焼きに合わせるワインは、少し贅沢をしてリベラ・デル・ドゥエロの中でも屈指のつくり手、ボデガス・エミリオ・モロの「マレオルス・デ・サンチョマルティン(MALLEOLUS DE SANCHOMARTIN)2005年」を選んでみました。このところリオハよりもすっかりリベラ・デル・ドゥエロに魅せられています。この赤ワインは樹齢45年以上の古木のティント・デル・バイス種(テンプラニーリョ種)100%でつくられ、フレンチ・オークの新樽で22か月間熟成させたエミリオ・モロの最高峰のワインです。アルコール度数は15.4%と高いです。カシスのアロマティックな香りにシナモン、アニス、クローブなどが続き、やがてカカオやバニラの香りが現れます。ミネラルを感じます。きれいな酸とのバランスもよく、タンニンもなめらかです。フィニッシュも長くつづきます。仔豚の丸焼きに合わせるには少し重かったかもしれませんが、見事なワインでした。でも、酒豪のヘミングウェイのように3本なんてとても空けられませんでした。 この仔豚の丸焼きに合わせるワインは、少し贅沢をしてリベラ・デル・ドゥエロの中でも屈指のつくり手、ボデガス・エミリオ・モロの「マレオルス・デ・サンチョマルティン(MALLEOLUS DE SANCHOMARTIN)2005年」を選んでみました。このところリオハよりもすっかりリベラ・デル・ドゥエロに魅せられています。この赤ワインは樹齢45年以上の古木のティント・デル・バイス種(テンプラニーリョ種)100%でつくられ、フレンチ・オークの新樽で22か月間熟成させたエミリオ・モロの最高峰のワインです。アルコール度数は15.4%と高いです。カシスのアロマティックな香りにシナモン、アニス、クローブなどが続き、やがてカカオやバニラの香りが現れます。ミネラルを感じます。きれいな酸とのバランスもよく、タンニンもなめらかです。フィニッシュも長くつづきます。仔豚の丸焼きに合わせるには少し重かったかもしれませんが、見事なワインでした。でも、酒豪のヘミングウェイのように3本なんてとても空けられませんでした。
デザートは、濃厚なチョコレートのかかったバニラ・アイスクリームをサングリア(Sangría)と共に楽しみました。そういえば、この店で初めてスペイン名物のサングリアにお目に掛かりました。これまた美味でした。キロスさんとお母様と大いに語り合い、名残惜しくも楽しい昼下がりの一時でした。お世話になりました。  最後に、誰もがご存知のあのセルバンテスが書いた『ドン・キホーテ』にみられる有名なワインに関するひとつの挿話をご紹介しましょう。「サンチョが大きな鼻の郷士に向って、自分はワインの利き酒には自信がある。これはわが一族の代々の特性なのだ、と言い張るのは十分理のあることである。― かつてわが身内が二人呼ばれて、年代物ですばらしく上等な葡萄酒と考えられている大樽のワインについて意見を求められた。一人が味見をし、しばし考え、そしてじっくりと考えをまとめてからこのワインは結構だ、ただし、自分がその中に感じた、ちょっとした皮の味がなかったならば、と言う。もう一人は、同じように注意力を働かせてから、同じくワインの良さを称えるのだが、ただし、彼が容易に判別できた鉄の味については留保したのだ。二人が下したそれらの判断がどれほど笑われたか想像はできまい。しかし、最後に笑ったのは誰であろう。その大樽を空にしてみると、底に、細い皮ひものついた古い鍵が見つかったのである」と、サンチョはいかにも得意気に語ります。皮ひもつきの鍵こそがサンチョの縁者の発言を正しいと立証したのであり、彼らを非難した自称判定者たちを見事挫けさせたのであります。それが果たして香りできき分けたのか、それとも味で判定したのかは興味を惹くところですが、今となってはサンチョに聞くこと叶わず残念です。たとえ、酒樽を空にしなかったとしても、ある者の味覚は変わらずに精妙であり、またある者の味覚は変わらず鈍感で冴えないものであることは確かであります。しかし、一方の者の方がどの傍観者の判断よりも優れていると証明することは、実際に樽を空にしなかった場合はより困難であったであろうと思われます。ワインを利き酒する味覚の感覚がいかなる性質をも見逃さないほどに微妙で、同時に、あらゆる要素を知覚できるほど精密である場合には、その味覚を私たちは“精妙な味覚”と呼ぶことができるのではないでしょうか。つまり、全ての感覚は受動的であるが、味覚だけは例外なのであります。味覚は意識的でありつづける唯一の知覚なのです。英国の哲学者デイヴィッド・ヒューム(1711-1776)は『趣味論』の中で、「“精妙な味覚(趣味)”は良い情操をもたらすゆえに、愛情や友情に資する」とも述べております。如何でしょうか。 最後に、誰もがご存知のあのセルバンテスが書いた『ドン・キホーテ』にみられる有名なワインに関するひとつの挿話をご紹介しましょう。「サンチョが大きな鼻の郷士に向って、自分はワインの利き酒には自信がある。これはわが一族の代々の特性なのだ、と言い張るのは十分理のあることである。― かつてわが身内が二人呼ばれて、年代物ですばらしく上等な葡萄酒と考えられている大樽のワインについて意見を求められた。一人が味見をし、しばし考え、そしてじっくりと考えをまとめてからこのワインは結構だ、ただし、自分がその中に感じた、ちょっとした皮の味がなかったならば、と言う。もう一人は、同じように注意力を働かせてから、同じくワインの良さを称えるのだが、ただし、彼が容易に判別できた鉄の味については留保したのだ。二人が下したそれらの判断がどれほど笑われたか想像はできまい。しかし、最後に笑ったのは誰であろう。その大樽を空にしてみると、底に、細い皮ひものついた古い鍵が見つかったのである」と、サンチョはいかにも得意気に語ります。皮ひもつきの鍵こそがサンチョの縁者の発言を正しいと立証したのであり、彼らを非難した自称判定者たちを見事挫けさせたのであります。それが果たして香りできき分けたのか、それとも味で判定したのかは興味を惹くところですが、今となってはサンチョに聞くこと叶わず残念です。たとえ、酒樽を空にしなかったとしても、ある者の味覚は変わらずに精妙であり、またある者の味覚は変わらず鈍感で冴えないものであることは確かであります。しかし、一方の者の方がどの傍観者の判断よりも優れていると証明することは、実際に樽を空にしなかった場合はより困難であったであろうと思われます。ワインを利き酒する味覚の感覚がいかなる性質をも見逃さないほどに微妙で、同時に、あらゆる要素を知覚できるほど精密である場合には、その味覚を私たちは“精妙な味覚”と呼ぶことができるのではないでしょうか。つまり、全ての感覚は受動的であるが、味覚だけは例外なのであります。味覚は意識的でありつづける唯一の知覚なのです。英国の哲学者デイヴィッド・ヒューム(1711-1776)は『趣味論』の中で、「“精妙な味覚(趣味)”は良い情操をもたらすゆえに、愛情や友情に資する」とも述べております。如何でしょうか。
奇想天外な冒険譚『ドン・キホーテ』の物語は、スペイン文学としては食べ物の記述の多い作品としても知られています。次回は「ドン・キホーテと食」について少し述べてみたいと思います。  |
|
|