|
余聞:ドン・キホーテと食について(2)

<ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ> |
『ドン・キホーテ』は、スペイン文学としては食べ物の記述が多い作品であると書いてきました。このことは、日常の食べ物をふんだんに登場させることでセルバンテスが、この作品に底流する意図をいかに巧みに織り込んでいるかを知ることになるでしょう。作者のこうした姿勢は後編第59章を読み返してみるとよく分かると思います。不運にも闘牛の群れと遭遇して、身も心もぼろぼろになった我らが騎士ドン・キホーテが、最もむごたらしい死である餓死を覚悟する場面に遭遇する時です。
 この劇的な自己省察は、我に返ったドン・キホーテが食べ物の正しい役立て方を巡って従士サンチョと交わす会話に表れています。「サンチョよ、おまえは食って命を養うがよい。私よりも、お前にとっては大事なことだからな。私の方は、憂いに沈み、身の不運をかこちつつこのまま死なせてもらおう。私は死にながら生きるべく生まれ、お前は食べながら死ぬべく生まれついておるのだ」と。 この劇的な自己省察は、我に返ったドン・キホーテが食べ物の正しい役立て方を巡って従士サンチョと交わす会話に表れています。「サンチョよ、おまえは食って命を養うがよい。私よりも、お前にとっては大事なことだからな。私の方は、憂いに沈み、身の不運をかこちつつこのまま死なせてもらおう。私は死にながら生きるべく生まれ、お前は食べながら死ぬべく生まれついておるのだ」と。
いずれにしても、この作品の登場人物たちをあらゆる職務から解き放つことができるのは食べ物であり、セルバンテス自身がいみじくも強調する通り、「人が飲み食いをしている時には、わずらいごとの入り込む余地はなくなるものである」― この言葉もまた、後顧の憂いを捨てて食卓につくことの大切さを説く賢慮のひとつといえるでしょう。 セルバンテスは巻頭一番、この郷士の一週間の献立を構成する食事のリストをずばり書き連ねることで、本名アロンソ・キハーノ(ドン・キホーテ)の人となりを描き出すことから物語を始めます。この斬新な文学手法によって、私たちはこの人物の境遇と趣味嗜好をたちどころにイメージできるという仕掛けです。「羊肉よりは牛肉の多く入った煮込み、大抵の夜に出される挽き肉のタマネギあえ、金曜日のレンズ豆、土曜日の塩豚と卵の炒めもの、そして日曜日に添えられる子鳩といったところが通常の食事で、彼の実入りの四分の三はこれで消えた」とあります。勿論、ここからはカスティーリアの郷士の質実さが窺えると共に、しかも、一切の前置きなしに読者の私たちは問題の核心を示されることになります。即ち、安閑とした生活態度と、騎士道物語の読書三昧がドン・キホーテから正気を奪うに至ったのだという事実を。 さて、遍歴の騎士は「ひと月くらいは何も食わない。食おうとしてもあり合せのものに限る。それが遍歴の騎士の誇りとするところだ」と、ドン・キホーテは胸を張り、その後も似たような台詞を繰り返します。しかし考えてみれば、きのうまで、けっして贅沢ではないにせよ、郷士時代のドン・キホーテは上記にあげた食事を毎日食べていた御仁であるから、ひと月も食べずにいたことがあるとは思えません。ところが、いったん遍歴の騎士を名乗ってからは、物語で読んだ騎士像を自分のものにしようとして、過去を切り捨てたのでした。その結果、ドン・キホーテの言行は常に騎士道文学の独特の読み方からつくりあげた遍歴の騎士像を模範とするようになっていったのでした。 だが、作者セルバンテスはドン・キホーテのそんな気持ちにお構いなく、食事についていえば、全編を通じてドン・キホーテが自宅にいる時も旅の間も、そして連れ戻されて静養している時も見逃さず、ざっと数えただけで50回程の「食」の風景を記述しているから驚いてしまいます。「食わないと言って食う」、まさに騎士道小説のパロディです。 騎士道小説の主人公は食べないだけでなく、眠らないし、大抵は死なないのです。ところがドン・キホーテは食べて眠って死んで、この建前を覆してしまいます。食べて眠って死ぬ、とはドン・キホーテが最も縁遠いものに考えていたことですが、それが全て現実になっていくのです。とりわけ、「食べない騎士」に対するパロディとしてのドン・キホーテは物語全体の中の「食」の意識を絶えず蘇らせることになります。ドン・キホーテの50回近い食事に加えて他の登場人物の食事の場面が、この物語の中で実に大きな比重を占めています。前編・後編合わせて126章のうち60章近くに亘って食べることへの言及があります。なんと平均すると1章おきということになるから驚きです。このことは今まで意外と見過ごされてきたのではないでしょうか。ドン・キホーテの物語はドン・キホーテの冒険で埋め尽くされていると思いきや、主従の「食」とそこでの会話、あるいは招かれた席での食事や会話の占める部分が大きいのです。そこに見るべきは、ドン・キホーテの想像力によって醸し出されていく世界です。それは無限に広がっていきます。 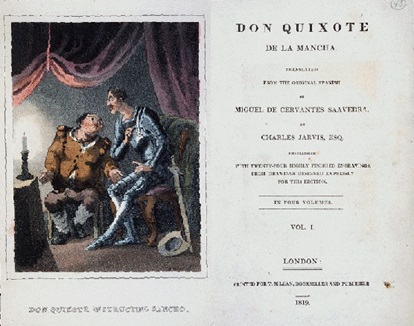 ところで、この物語の中で従士サンチョはいささかがさつですが純朴な、事なかれ主義の愛すべきひょうきん者として登場します。そのサンチョが誇りとない交ぜになった苦い自嘲の念から、ドン・キホーテの騎士としての本分について触れていきます。そして、不滅の手柄を立てようとするあまり、野原の真ん中で眠りにつき、木の実で腹を満たすまでに至った主人ドン・キホーテの暮らしぶりを披露します。身分の枷は縛られて、自由に行動できない有閑貴族たちとはかけ離れた人生を生きるドン・キホーテには思想と行動と基本的欲求の間に折り合いをつける方法に思い巡らす時間がたっぷりとありました。そうした行動への意欲が、風車やならず者たちとの決闘へと私たちを導きます。また、そうした思想を愛する気持ちが、母なる大地を守る人間性を取戻し、人としての尊厳を帯びた理想に再び立ち戻ろうという思いを育むのです。この種の規範意識は狂信と映るかもしれません。しかし、「思うが儘に人生を送る」ことは、共に食べる喜びや味覚の法悦が織りなす祝宴なのです。従って、この偉大な書を読む時、ドン・キホーテは自分であることに私たちは気づくでしょう。夢を忘れず型破りな行動に走る私たちもまた叡智を求める長い旅に船出したのです。 ところで、この物語の中で従士サンチョはいささかがさつですが純朴な、事なかれ主義の愛すべきひょうきん者として登場します。そのサンチョが誇りとない交ぜになった苦い自嘲の念から、ドン・キホーテの騎士としての本分について触れていきます。そして、不滅の手柄を立てようとするあまり、野原の真ん中で眠りにつき、木の実で腹を満たすまでに至った主人ドン・キホーテの暮らしぶりを披露します。身分の枷は縛られて、自由に行動できない有閑貴族たちとはかけ離れた人生を生きるドン・キホーテには思想と行動と基本的欲求の間に折り合いをつける方法に思い巡らす時間がたっぷりとありました。そうした行動への意欲が、風車やならず者たちとの決闘へと私たちを導きます。また、そうした思想を愛する気持ちが、母なる大地を守る人間性を取戻し、人としての尊厳を帯びた理想に再び立ち戻ろうという思いを育むのです。この種の規範意識は狂信と映るかもしれません。しかし、「思うが儘に人生を送る」ことは、共に食べる喜びや味覚の法悦が織りなす祝宴なのです。従って、この偉大な書を読む時、ドン・キホーテは自分であることに私たちは気づくでしょう。夢を忘れず型破りな行動に走る私たちもまた叡智を求める長い旅に船出したのです。
独創にあふれたこの作品が全編にわたり繰り広げる遍歴は、教訓を重視する時代色に彩られています。そうした教訓の中でも特に重要なものが、「賢者の愚行を性急にあざけるなかれ」という教えであろうと思います。400年以上も前にあって既に、時代の性急な移り変わりに抵抗し、至高の道徳律以外の何物も制約としない運動が展開されていた時代でありました。そして、そうした信条をバネとする作者セルバンテスは、食生活にせよ生活習慣にせよ、規範の壁にぶつかった時こそ自らの意志が頼りになること、目の前のご馳走は悔いなく存分に味わえばよいということを私たちに向って丁寧に説き明かしてくれるのです。 だが、この物語に占める「食」の重要性については、どう説明をつければいいでしょうか。恐らくそれは、誰もが知る通り、食べ物を通して人は自らの熱狂を現実の中で表現するのであり、それによって、食べる喜びを分かち合うこと ― 社会の一員であることの特権のひとつ ― に結び付けるからではないでしょうか。  それではこれから、『ドン・キホーテ』を読み解いていく上で「食」のキーワードとなる、興味深い食材と料理について述べていくことにしましょう。先ずは、冒頭の郷士の食生活に登場した「タマネギ(Cebolla)」(スペインのタマネギは甘く、日本のように辛くない)について考えてみましょう。食べないか、粗食に甘んじるのが遍歴の騎士のモットーでありますが、いかに粗食といえども騎士たるもの、タマネギだけは食べてはならないとされておりました。それとニンニクも。タマネギやニンニクが余りにも粗末だからでしょうか。否、それだけではありません。騎士の世界にはタマネギに対する根の深い偏見があったからです。ドン・キホーテが読んだ騎士道物語の世界にとどまらず、現実でもタマネギは騎士と名乗るものにとっては禁断の食べ物といってよかったのです。タマネギは次に述べる「茄子」とは対照的に百薬の長ともいえる食べ物でありながら。では何故、タマネギは騎士の世界から忌避されていたのでしょうか。これにはキリスト教の宗教騎士団がもつ使命が関わっていたのでした。そもそもタマネギをスペインに持ち込み盛んに栽培していたのは、彼らの宿敵イスラム勢力の地でありました。そこでモーロ人やユダヤ人が作って食べていたのです。このタマネギをレコンキスタ(国土回復運動)によってキリスト教徒の天下になったスペインで、モリスコ(キリスト教に改宗したイスラム教徒)が栽培し、やがてキリスト教徒もそれに倣うわけですが、そんな時代になってもタマネギは騎士にとっては甘い食べ物ではなかったのです。あくまで見下すべきモリスコが作る草のひとつであり、戦士の腹の足しになるカロリー源でもなかったのです。そのタマネギを鞍袋から取り出す時にサンチョがドン・キホーテに、「旦那様のような強い騎士のお口に合うものではありません」という時、 それではこれから、『ドン・キホーテ』を読み解いていく上で「食」のキーワードとなる、興味深い食材と料理について述べていくことにしましょう。先ずは、冒頭の郷士の食生活に登場した「タマネギ(Cebolla)」(スペインのタマネギは甘く、日本のように辛くない)について考えてみましょう。食べないか、粗食に甘んじるのが遍歴の騎士のモットーでありますが、いかに粗食といえども騎士たるもの、タマネギだけは食べてはならないとされておりました。それとニンニクも。タマネギやニンニクが余りにも粗末だからでしょうか。否、それだけではありません。騎士の世界にはタマネギに対する根の深い偏見があったからです。ドン・キホーテが読んだ騎士道物語の世界にとどまらず、現実でもタマネギは騎士と名乗るものにとっては禁断の食べ物といってよかったのです。タマネギは次に述べる「茄子」とは対照的に百薬の長ともいえる食べ物でありながら。では何故、タマネギは騎士の世界から忌避されていたのでしょうか。これにはキリスト教の宗教騎士団がもつ使命が関わっていたのでした。そもそもタマネギをスペインに持ち込み盛んに栽培していたのは、彼らの宿敵イスラム勢力の地でありました。そこでモーロ人やユダヤ人が作って食べていたのです。このタマネギをレコンキスタ(国土回復運動)によってキリスト教徒の天下になったスペインで、モリスコ(キリスト教に改宗したイスラム教徒)が栽培し、やがてキリスト教徒もそれに倣うわけですが、そんな時代になってもタマネギは騎士にとっては甘い食べ物ではなかったのです。あくまで見下すべきモリスコが作る草のひとつであり、戦士の腹の足しになるカロリー源でもなかったのです。そのタマネギを鞍袋から取り出す時にサンチョがドン・キホーテに、「旦那様のような強い騎士のお口に合うものではありません」という時、
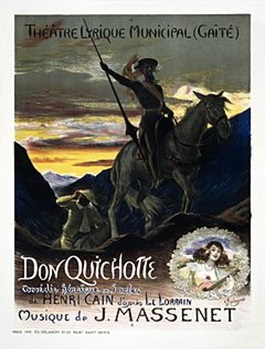 作者セルバンテスの魂胆は上記のような事情に発していると考えてもあながち的外れではないでしょう。『ドン・キホーテ』の物語は「タマネギ」ひとつにしても実に意味深長なのです。 作者セルバンテスの魂胆は上記のような事情に発していると考えてもあながち的外れではないでしょう。『ドン・キホーテ』の物語は「タマネギ」ひとつにしても実に意味深長なのです。
ドン・キホーテは遍歴の騎士を名乗って旅に出る以前は毎日のようにタマネギのサルピコン(サラダ)を食べていました。ところが騎士になってからは、当初は兎も角、次第にタマネギを忌避するようになってきます。初めは、毎日のようにタマネギを食べていたことをおくびにも出しませんが、うっかりサンチョと仲良く食べてしまいます。この時ドン・キホーテはタマネギが自分にとって宿敵のごとく憎い存在になろうとは夢にも思わなかったのです。しかし、実際にはタマネギの皮肉は執念深くドン・キホーテの世界に取り付いて悩ませます。それは死の寸前まで纏わりついてきます。タマネギの臭いを拭い去ることが後編におけるドン・キホーテの使命でもあったといえます。それは『ドン・キホーテ』の中で、タマネギは大別して2つの意味で使われていたからです。一つは、「ニンニクとタマネギ」に象徴される粗食の代名詞として。もう一つは、その「臭い」やモリスコから連想される「素性の卑しさ」です。「臭いでお前が平民の出であることが分かってしまわないよう、ニンニクもタマネギも食べるな」、これはサンチョがこの旅のお供をするに当ってドン・キホーテと約束を交わした島の太守に目出度く任じられ島へ赴く際に、ドン・キホーテが授けた助言でした。そして、ドン・キホーテがタマネギを毛嫌いした最大の理由は、ドン・キホーテの言動の鍵を握る想い姫ドゥルシネーアが、ある時魔法使いによって「タマネギ臭い」田舎娘に変えられてしまったことです。タマネギは憎い。それ以来、後編の第10章から第73章まで、即ちこの物語のおしまい近くになって村に帰り着き死を迎える直前まで、ドン・キホーテの最大の使命はドゥルシネーアからタマネギの臭いを消し、元の甘く芳しい姫に戻すことにありました。皮肉なことに、ドン・キホーテの故郷ラ・マンチャは、スペインで古くから「ニンニクとタマネギの里」と言われてきたのであります。 次回は『ドン・キホーテ』の「食」のもうひとつの鍵を握る「茄子」、そして興味深い「料理」についてお話ししようと思います。  |