|
余聞:ドン・キホーテと食について(3)

“Duelos y Quebrantos(哀悼と悲嘆)” |
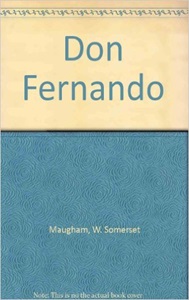 梅雨のある日、退屈凌ぎに書斎の本を整理していると、堆(うずたか)く積んである本の中に、大分昔に買った『Don Fernando(ドン・フェルナンド)』という古びた一冊の洋書が目に留まりました。著者はWilliam Somerset Maugham(ウイリアム・サマセット・モーム,イギリスの小説家、劇作家。1874-1965)です。その時、何故か久し振りに読んでみたい気持ちに駆られました。そして、ページを繰っていく内に、“Don Quixote(ドン・キホーテ)”という文字が目に飛び込んできたのです。確かに、サマセット・モームの旅行好きは有名で、なかでもスペインへの愛着は大変なものがあり、何十回も訪問を重ねています。この『Don Fernando』というスペイン歴史物語の中に、ドン・キホーテが登場するのは当然といえば当然のことであります。因みに、題名の『Don Fernando』とは、サマセット・モームがセビリャに住んでいた頃に足繁く通った酒場の陽気で太っちょな主(あるじ)の名前です。そこで主を相手に、アンダルシア産の上等のマンサニ―リャ(辛口シェリー、フィノの一種)を一杯やるのがとても楽しみだったようです。 梅雨のある日、退屈凌ぎに書斎の本を整理していると、堆(うずたか)く積んである本の中に、大分昔に買った『Don Fernando(ドン・フェルナンド)』という古びた一冊の洋書が目に留まりました。著者はWilliam Somerset Maugham(ウイリアム・サマセット・モーム,イギリスの小説家、劇作家。1874-1965)です。その時、何故か久し振りに読んでみたい気持ちに駆られました。そして、ページを繰っていく内に、“Don Quixote(ドン・キホーテ)”という文字が目に飛び込んできたのです。確かに、サマセット・モームの旅行好きは有名で、なかでもスペインへの愛着は大変なものがあり、何十回も訪問を重ねています。この『Don Fernando』というスペイン歴史物語の中に、ドン・キホーテが登場するのは当然といえば当然のことであります。因みに、題名の『Don Fernando』とは、サマセット・モームがセビリャに住んでいた頃に足繁く通った酒場の陽気で太っちょな主(あるじ)の名前です。そこで主を相手に、アンダルシア産の上等のマンサニ―リャ(辛口シェリー、フィノの一種)を一杯やるのがとても楽しみだったようです。
余談ですが、サマセット・モームといえば、大学時代に『Of Human Bondage(人間の絆)』というタイトルに惹かれ、モームの半自伝的小説を夢中で読んだものです。  そして同名の映画(キム・ノヴァクとローレンス・ハーヴェイ主演)を渋谷の映画館に見に行ったのも今となっては懐かしい思い出です。『人間の絆』の中で、主人公は「アンダルシアは自分の意気込んだ熱意を満足させるには余りにも柔らかく感覚的で、少しばかり通俗的であり、むしろ、風に晒されたカスティーリアの遠景やアラゴンやレオンの起伏に富んだ壮大な風景に思いを馳せた」と語っています。そして最後に、スペインに対して描く夢が情熱を込めて語られています。この『ドン・フェルナンド』の中でも、モームは、バスク地方からエストレマドゥーラまで、ガリシアからカタルーニャまでの各地を縦横無尽に闊歩して、そこに展開されるスペイン人の人間ドラマを、感嘆を交えながら紹介しています。 そして同名の映画(キム・ノヴァクとローレンス・ハーヴェイ主演)を渋谷の映画館に見に行ったのも今となっては懐かしい思い出です。『人間の絆』の中で、主人公は「アンダルシアは自分の意気込んだ熱意を満足させるには余りにも柔らかく感覚的で、少しばかり通俗的であり、むしろ、風に晒されたカスティーリアの遠景やアラゴンやレオンの起伏に富んだ壮大な風景に思いを馳せた」と語っています。そして最後に、スペインに対して描く夢が情熱を込めて語られています。この『ドン・フェルナンド』の中でも、モームは、バスク地方からエストレマドゥーラまで、ガリシアからカタルーニャまでの各地を縦横無尽に闊歩して、そこに展開されるスペイン人の人間ドラマを、感嘆を交えながら紹介しています。
さて、今回は“茄子”の話をする積りにしていましたが、いきなりサマセット・モームの話に転換したのには少々訳があるのです。 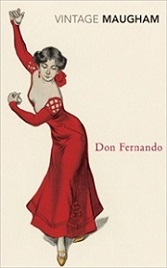 それは私が予てから興味を抱いていた、『ドン・キホーテ』の中に登場する奇妙な料理“Duelos y Quebrantos(ドウェロス・イ・ケブラントス)”について、『ドン・フェルナンド』の中で言及しているのに気付いたからです。実は、モームはこの本の第8章で、「セルバンテスがドン・キホーテの毎日の食事について詳しく述べているのは当時のスペイン文学として異例である」と指摘したあとに、前回紹介したドン・キホーテの一週間分の献立について、次のように書いております。「一週間のうち二日以外は、午餐にスペイン郷土料理のオジャ・ポドリーダ(Olla Podrida)を食べた。これは牛肉と羊肉のごった煮で、羊肉は高かったから牛肉の方が多く、それにキャベツとえんどう豆を混ぜ、タマネギとオリーブで味付けしたものである。日曜日には、これにひとつがいの鳩がついた。夕食には、乱切りにした肉、ハムに酢漬けのタマネギを食べた。信心深いカトリック教徒だったので、金曜日はレンズ豆以外のものは一切食べなかった」と。そして、何よりも私が一番興味を惹いたのは、モームが「土曜日は“Duelos y Quebrantos(ドウェロス・イ・ケブラントス)”、これを英訳すると“Pains and Sorrows(和訳すると“苦痛と悲嘆”でしょうか)”である」と書いていることです。「識者たちは、この奇妙な名をつけられた料理が一体何だったのか知ろうとして苦労を重ねた」とあります。 それは私が予てから興味を抱いていた、『ドン・キホーテ』の中に登場する奇妙な料理“Duelos y Quebrantos(ドウェロス・イ・ケブラントス)”について、『ドン・フェルナンド』の中で言及しているのに気付いたからです。実は、モームはこの本の第8章で、「セルバンテスがドン・キホーテの毎日の食事について詳しく述べているのは当時のスペイン文学として異例である」と指摘したあとに、前回紹介したドン・キホーテの一週間分の献立について、次のように書いております。「一週間のうち二日以外は、午餐にスペイン郷土料理のオジャ・ポドリーダ(Olla Podrida)を食べた。これは牛肉と羊肉のごった煮で、羊肉は高かったから牛肉の方が多く、それにキャベツとえんどう豆を混ぜ、タマネギとオリーブで味付けしたものである。日曜日には、これにひとつがいの鳩がついた。夕食には、乱切りにした肉、ハムに酢漬けのタマネギを食べた。信心深いカトリック教徒だったので、金曜日はレンズ豆以外のものは一切食べなかった」と。そして、何よりも私が一番興味を惹いたのは、モームが「土曜日は“Duelos y Quebrantos(ドウェロス・イ・ケブラントス)”、これを英訳すると“Pains and Sorrows(和訳すると“苦痛と悲嘆”でしょうか)”である」と書いていることです。「識者たちは、この奇妙な名をつけられた料理が一体何だったのか知ろうとして苦労を重ねた」とあります。
ということで、この機会に自分なりの疑問に答えを出そうと、“Duelos y Quebrantos”なる料理を少し詳しく調べてみることにしました。改めて、スペイン語辞典で言葉の意味を確かめてみますと、Duelos:深い悲しみ、哀悼、Quebrantos:悲嘆、気落ち、とありました。私はこの料理に益々興味をそそられていきました。この“哀悼と悲嘆”と名付けられた奇妙な料理は、一体どんなものなのかと。 先ずは、歴代翻訳者の『ドン・キホーテ』の日本語訳を調べてみましたが、何故か解釈は一定ではありませんでした。島村抱月、片上伸共訳(植竹書院、1915年)は「肉屑」、進藤遠訳(思索社、1949年)は「鶏と豚とのごった煮」、堀口大學訳(新潮社、1965年)は「ベーコン添えの目玉焼き」、会田由訳(昌文社他、1965年)は「塩豚の卵あえ」、永田寛定訳(岩波文庫、1971年)は「塩豚の玉子あえ」、そして最新刊の牛島信明訳(岩波文庫、1999年)は「塩豚と卵の炒めもの」となっています。否、日本語訳の問題以前に、“哀悼と悲嘆”と名付けられた料理について、今日まで多くの世界のセルバンテス研究者がこの料理の正体に挑んできた筈ですが、どうも決定的な解明には至っていないようです。ドン・キホーテがいわば常食としてきた料理であるのに。これはどうやら只者ではなさそうです。この料理が大きな謎として今日に至っている最大の理由は、セルバンテスが生きた時代の前後に出版された料理本に載っていないからだというのが定説になっています。 でも、サマセット・モームによると、「識者なるものの例にもれず、あてずっぽうな空想にふけった人たちもいた。結局、『ドン・キホーテ』の記念碑的な版において、ドン・フランシスコ・マリンがセルバンテスの不朽の名作の同時代のフランス語版、  イタリア語版を調べ、古典劇を注意深く熟読した結果、アロンソ・キハーノ(ドン・キホーテ)が土曜日に食べた“Duelos y Quebrantos(Pains and Sorrows)”は《ベーコン・エッグ》に他ならないことが、疑いの余地なく分かったのである(...,by attentive perusal of the classical plays,to discover beyond shadow of doubt that what Alonso Quijana ate on Saturdays was neither more nor less than 《eggs and bacon》)」と,自信満々に答えております。サマセット・モームが『ドン・フェルナンド』の初版を著したのは1935年のことでした。もし、これが正解だとすると一番近いのは堀口大學訳のようですが、豚肉を塩漬けにして燻製したものがベーコンですから、会田訳も永田訳もそして牛島訳も同じ解釈となります。各翻訳者は過去の古典劇等を十分調査した結果なのでありましょう。 イタリア語版を調べ、古典劇を注意深く熟読した結果、アロンソ・キハーノ(ドン・キホーテ)が土曜日に食べた“Duelos y Quebrantos(Pains and Sorrows)”は《ベーコン・エッグ》に他ならないことが、疑いの余地なく分かったのである(...,by attentive perusal of the classical plays,to discover beyond shadow of doubt that what Alonso Quijana ate on Saturdays was neither more nor less than 《eggs and bacon》)」と,自信満々に答えております。サマセット・モームが『ドン・フェルナンド』の初版を著したのは1935年のことでした。もし、これが正解だとすると一番近いのは堀口大學訳のようですが、豚肉を塩漬けにして燻製したものがベーコンですから、会田訳も永田訳もそして牛島訳も同じ解釈となります。各翻訳者は過去の古典劇等を十分調査した結果なのでありましょう。
当時の料理書には載っていないものの、サマセット・モームが述べているように文学作品や古典劇には“哀悼と悲嘆”への言及が散見されていたようです。  古典劇には「まあ、ご主人様、“哀悼と悲嘆”のために卵12個だなんて」とあることから、この料理が卵と関係のありそうなことは分かります。ひょっとすると、これはスペイン風オムレツ(トルティージャ)だったかもしれません。あるいは、「“哀悼と悲嘆”と一緒になった豚の脂肉を揚げたもので食事をしながら」とある通り、つまり脂肉(今で言うベーコン)と結びつきやすいことになります。同時に揚げたものであるらしいことも分かります。どうやらこの謎めいた奇妙な名前をもつ料理は「卵とベーコンを炒めたもの」という、サマセット・モームが『ドン・フェルナンド』で記した《ベーコン・エッグ》と同様の結論が導き出せそうです。でも、「脳みそ入り卵焼き」、あるいは「家畜類の頭、手足、内臓類に塩豚三枚肉と卵を加えたもの」との説もあるようです。 古典劇には「まあ、ご主人様、“哀悼と悲嘆”のために卵12個だなんて」とあることから、この料理が卵と関係のありそうなことは分かります。ひょっとすると、これはスペイン風オムレツ(トルティージャ)だったかもしれません。あるいは、「“哀悼と悲嘆”と一緒になった豚の脂肉を揚げたもので食事をしながら」とある通り、つまり脂肉(今で言うベーコン)と結びつきやすいことになります。同時に揚げたものであるらしいことも分かります。どうやらこの謎めいた奇妙な名前をもつ料理は「卵とベーコンを炒めたもの」という、サマセット・モームが『ドン・フェルナンド』で記した《ベーコン・エッグ》と同様の結論が導き出せそうです。でも、「脳みそ入り卵焼き」、あるいは「家畜類の頭、手足、内臓類に塩豚三枚肉と卵を加えたもの」との説もあるようです。
ここでもう一つ興味のあることは、この料理を食べる曜日との関係です。ドン・キホーテが“哀悼と悲嘆”を「土曜日」に食べていたことです。この点に着目して、キリスト教と肉食節制との関係から見てみましょう。宗教が特定の食べ物を、とりわけ特定の日に食べることを禁じることがあるのはよく知られています。例えば、ユダヤの飲食に関する規制が旧約聖書の「レビ記」に記されていることからも分かります。紀元5世紀初頭の教皇インノケンティウス1世の書簡によると、キリスト受難に思いを馳せて金曜日に肉食を控え、次に復活を記念して聖週間のみならず日曜日まで肉食を控えるのなら、苦しみと喜びの間に挟まれた土曜日にも肉食を控えるのが理に叶うとあります。でも、この規定は徹底しなかったらしく、11世紀後半になると土曜日の肉食節制を推奨程度に緩和してしまいます。果たして、こうした規定や推奨はセルバンテス時代のスペインでも通用していたのでしょうか。  ただ、文学作品には「徹夜や小斎(羅:abstinentia、摂取できる食品制限のことで、キリストの受難を思い出すために肉類を控えること)を守る日には、肉の代わりに卵を焼くか目玉焼きかゆで卵にするか・・・」と、しっかり規定を守っていますが、もう一方では「土曜日の食べ物は、脳みそこそありませんでしたが、頭と舌がありました」と。つまり、土曜日に肉食を控えるといっても、動物の胴体部分の肉を控えただけで、“哀悼と悲嘆”の料理に用いられた肉は、同じ肉でも内臓や手足、首を含めた頭部であったのではないかという推測が可能になってきます。いずれにしても週末の食事の組み合わせが絶妙です。金曜、土曜、日曜は夫々イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の安息日です。そのユダヤ教の安息日である土曜日にドン・キホーテは敢えて“哀悼と悲嘆”を食べたのです。イスラム教の安息日である金曜日にレンズ豆(イスラム教徒の代表的な日常食)を食べ、そしてキリスト教の安息日、日曜日に小鳩を食べたのであります。昔から鳩は聖霊をもたらすと考えられていたからです。こういった事実に照らしますと、ドン・キホーテは3つの宗教の祭日に夫々と因縁のある食べ物を選んでいたことが分かります。つまりは、“哀悼と悲嘆”を味わうことは<嘆きの壁>に向かって祈るようなもので、日本でいう精進料理的なもの、もしくは斎日(キリスト教で、祭に自らの心身を備える事を定められている日)のメニューだったのではないでしょうか。 ただ、文学作品には「徹夜や小斎(羅:abstinentia、摂取できる食品制限のことで、キリストの受難を思い出すために肉類を控えること)を守る日には、肉の代わりに卵を焼くか目玉焼きかゆで卵にするか・・・」と、しっかり規定を守っていますが、もう一方では「土曜日の食べ物は、脳みそこそありませんでしたが、頭と舌がありました」と。つまり、土曜日に肉食を控えるといっても、動物の胴体部分の肉を控えただけで、“哀悼と悲嘆”の料理に用いられた肉は、同じ肉でも内臓や手足、首を含めた頭部であったのではないかという推測が可能になってきます。いずれにしても週末の食事の組み合わせが絶妙です。金曜、土曜、日曜は夫々イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の安息日です。そのユダヤ教の安息日である土曜日にドン・キホーテは敢えて“哀悼と悲嘆”を食べたのです。イスラム教の安息日である金曜日にレンズ豆(イスラム教徒の代表的な日常食)を食べ、そしてキリスト教の安息日、日曜日に小鳩を食べたのであります。昔から鳩は聖霊をもたらすと考えられていたからです。こういった事実に照らしますと、ドン・キホーテは3つの宗教の祭日に夫々と因縁のある食べ物を選んでいたことが分かります。つまりは、“哀悼と悲嘆”を味わうことは<嘆きの壁>に向かって祈るようなもので、日本でいう精進料理的なもの、もしくは斎日(キリスト教で、祭に自らの心身を備える事を定められている日)のメニューだったのではないでしょうか。
でも、最後にどうしても不可思議なことは、何故この料理に“哀悼と悲嘆”という奇妙な名前が付けられたのかということです。一説には、ラ・マンチャ地方の牧人は、死んだ家畜の胴体部分を領主に定期的に届けていたようで、飼い主は当然のことながら家畜に“哀悼”を捧げつつ、“悲嘆”に暮れながらも末端肉を使った料理を土曜日につくっていたというのです。こじつけの感を拭いえないものの、料理名自体が奇異であるからには、この程度の解釈が登場するのも不思議ではないのかもしれません。更には、肉食をじっと我慢しなくてはならないことから、  “悲嘆”を苦行、禁欲の意とする説もあるそうです。しかし、依然として最終的な答えは謎に包まれたままです。「塩豚(ベーコン)と卵の炒めもの」の訳が妥当なのか否かは別として、“哀悼と悲嘆”の直訳では読者にまるで意味が通じずに使いものにならないことは明確です。そして、使われた肉が豚であるとすれば、ドン・キホーテはイスラム教徒やユダヤ人ではなく、正真正銘のキリスト教徒であることを、食べ物を通して主張していることにもなります。『ドン・キホーテ』は食べ物ひとつとってもなかなか味わい深いです。いずれにしても、“哀悼と悲嘆”という料理は『ドン・キホーテ』が書かれていた時代の料理書に出てこないということから、手の込んだ高級料理でないことは確かであり、落ちぶれ郷士の口に入る程度の庶民の食べ物であったといえるのではないでしょうか。 “悲嘆”を苦行、禁欲の意とする説もあるそうです。しかし、依然として最終的な答えは謎に包まれたままです。「塩豚(ベーコン)と卵の炒めもの」の訳が妥当なのか否かは別として、“哀悼と悲嘆”の直訳では読者にまるで意味が通じずに使いものにならないことは明確です。そして、使われた肉が豚であるとすれば、ドン・キホーテはイスラム教徒やユダヤ人ではなく、正真正銘のキリスト教徒であることを、食べ物を通して主張していることにもなります。『ドン・キホーテ』は食べ物ひとつとってもなかなか味わい深いです。いずれにしても、“哀悼と悲嘆”という料理は『ドン・キホーテ』が書かれていた時代の料理書に出てこないということから、手の込んだ高級料理でないことは確かであり、落ちぶれ郷士の口に入る程度の庶民の食べ物であったといえるのではないでしょうか。
結論的にいえることですが、大変感心させられ且つ感銘を受けたのは、セルバンテスがドン・キホーテの食事として、敢えてこの奇怪な料理名のついた“哀悼と悲嘆”を選んだことです。それは狂気の道に走り、遍歴の旅で幾多の辛酸を嘗める以前に、物語の冒頭一番にドン・キホーテが土曜日ごとに“哀悼と悲嘆”を常食としていることを表明し、己の“哀悼と悲嘆”とを着実に準備していたことを読者に暗に知らしめたのではないかと思うのです。その質素な料理を食していたドン・キホーテの作品こそは、セルバンテスが私たち読者に贈ってくださったかけがえのない滋養のように思えてなりません。 今回はサマセット・モームの『Don Fernando』の本が偶々目に留まり、その中に記された奇妙な料理“Duelos y Quebrantos(哀悼と悲嘆)”に興味を抱いてしまったばかりに、終始この話で尽きてしまいました。自己満足だけで、読者の皆様には退屈だったかもしれません。ご容赦ください。次回も更にドン・キホーテの食べ物の話を続けます。『ドン・キホーテ』の食への興味は尽きません。  |