|
- ワインの書物について(その2) - 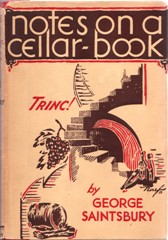 |
| 私は今までにどれ程多くのワイン書に巡り合ったことでしょうか。ワインを飲むにつれ自然とワイン書の魅力にも引き込まれていきました。そしていつの間にか本を携えて何度もフランスワインの故郷を訪ねる旅に出掛け、ついには定年前に会社を辞めてまで本場ボルドーの地でワインを学ぶに至りました。文字通りワインは私の生涯の友になりました。その旅に誘(いざな)ってくれたのはワインそのものの魅力と共に書物の面白さも一役買ってくれたのかもしれません。今回はわが国で翻訳され、入手可能な海外の著書を中心に語ってみたいと思います。 どうしても忘れられない一冊は、英国の著名なワイン作家として今も活躍しているヒュー・ジョンソンが著した『THE WORLD ATLAS OF WINE』(1971年)と巡り合った時です。まだワインの興味に目覚めて4,5年頃のことで、神戸三宮の丸善で偶然目に留まりました。ワインカラーの外箱に入っており、ページを繰ると美しい世界のワインのラベルと地図が詳細に記されていて、一遍で気に入ってしまいました。ところが当時新婚時代の安サラリーの私にとっては高価であったため躊躇してしまい、一旦は諦めて帰りました。しかし、丸善に一冊のみ入荷した本ということもあって、どうしても手に入れたくなり翌日の昼間に会社(当時関西勤務)をこっそり抜け出して買いに行ったことを覚えています。それはオランダで印刷された美しい本でした。それからは会社から帰ると辞書を片手に読み耽ったものです。当時、「無人島で生活することになった時に、あなたが持参したい一冊の本を挙げよ」というアンケートがあったように記憶しますが、私は問答無用でこの『THE WORLD ATLAS OF WINE』を持っていきたいと思ったものです。いったいワインを論じた本の方が、ワインそのものよりも面白いなんてことがあるのでしょうか。それがあるのですね、この本には。飲んだワインがいったいどんな場所でつくられているのか、この地図を見ると一目瞭然に分かるのです。本の上であれこれ想いを巡らせて楽しい小旅行ができるのです。この本は3年後に早くも地理学者の日高達太郎により翻訳され『わいん-世界の銘酒とその風土』というタイトルで出版されました。いまだに版を重ねている名著です。またヒュー・ジョンソンはご存知、『POCKET WINE BOOK』の著者でもあります。この初版に近い1979年版(小口金箔)に出合った時も感激したものです。こんな便利で簡潔なワインの本があるのかと。それと大著『THE STORY OF WINE』(1989年、邦訳『ワイン物語』上・下巻(1990年))も忘れるわけにはいかないでしょう。 次は含蓄に富んだ、アレック・ウォーの名著『IN PRAISE OF WINE』(1959年)を挙げねばならないでしょう。著者は20世紀の英国の生んだ偉大な作家、イヴリン・ウォー 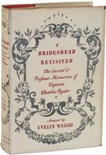 の実兄でもあります。イヴリン・ウォーの代表作『ブライズヘッド再訪(Brideshead Revisited)』には、全編を通じてワインの話が出てきますので、弟の方も兄に劣らないワイン愛好家であったのでしょう。併せてお読みいただければ成程と頷かれると思います。ワイン通として自他ともに許す兄のアレック・ウォーの蘊蓄は、歴史や地理にはじまってワインに対する心構えが丁寧に記されており、その魅力に思わず引き込まれてしまいます。「シェークスピアの時代およびその前後」の章も興味深く、英国人がこよなくワインを愛する姿がシェークスピアの劇作と共に語られています。この本は、英文学者増野正衛の名訳により『わいん-世界の酒遍歴』(1964年)として刊行されました。 の実兄でもあります。イヴリン・ウォーの代表作『ブライズヘッド再訪(Brideshead Revisited)』には、全編を通じてワインの話が出てきますので、弟の方も兄に劣らないワイン愛好家であったのでしょう。併せてお読みいただければ成程と頷かれると思います。ワイン通として自他ともに許す兄のアレック・ウォーの蘊蓄は、歴史や地理にはじまってワインに対する心構えが丁寧に記されており、その魅力に思わず引き込まれてしまいます。「シェークスピアの時代およびその前後」の章も興味深く、英国人がこよなくワインを愛する姿がシェークスピアの劇作と共に語られています。この本は、英文学者増野正衛の名訳により『わいん-世界の酒遍歴』(1964年)として刊行されました。そしてシェークスピアで思い出すのは、同じく英国の著名なワイン作家であるアンドレ・シモンがシェークスピア生誕400年祭(1964年)を祝して行った講演を小冊子にまとめた私家版『WINE IN SHAKESPEARE'S DAYS AND SHAKESPEARE'S PLAY』も見逃せない一冊でしょう。前々回でご紹介しましたジョージ・ギッシングが『ヘンリ・ライクロフトの私記』の中で、「私がイギリスに生まれたことをありがたく思う多くの理由のうち、まず初めに浮かぶ理由のひとつは、シェークスピアを 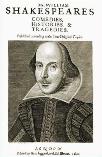 母国語で読めるということである」と述べています。このように英国人とは切っても切れないシェークスピアという人物と劇作は英国のみならず世界全域に亘って、数え切れないほど多くの研究者たちの心に訴え掛けてきたわけですが、この小冊子でアンドレ・シモンはシェークスピアの生涯と作品のなかでワインがどのような位置を占め、どのような意味をもっていたかというユニークな観点で述べております。「シェークスピアの時代には、誰も水を飲むことはいたしませんでした。水は安全な飲み物ではなかったのです。国内の極めて貧しい人たちは別として、朝食にはエール、昼食にはビール、そして晩餐にはワインが、すべての食卓で飲料として用いられておりました」とあり、「ワインはシェークスピアの英国においては“善良な家族の一員”といった性格をもっておりました」と述べています。シェークスピアは勿論ボルドーワインを熟知していましたが、作品中ではサック酒(シェリー)とその同類の酒への言及の多さが群を抜いているとも語っています。どうやらシェークスピアの劇作の中では、ボルドーワインは期待する程の地位は占めていなかったようです。 母国語で読めるということである」と述べています。このように英国人とは切っても切れないシェークスピアという人物と劇作は英国のみならず世界全域に亘って、数え切れないほど多くの研究者たちの心に訴え掛けてきたわけですが、この小冊子でアンドレ・シモンはシェークスピアの生涯と作品のなかでワインがどのような位置を占め、どのような意味をもっていたかというユニークな観点で述べております。「シェークスピアの時代には、誰も水を飲むことはいたしませんでした。水は安全な飲み物ではなかったのです。国内の極めて貧しい人たちは別として、朝食にはエール、昼食にはビール、そして晩餐にはワインが、すべての食卓で飲料として用いられておりました」とあり、「ワインはシェークスピアの英国においては“善良な家族の一員”といった性格をもっておりました」と述べています。シェークスピアは勿論ボルドーワインを熟知していましたが、作品中ではサック酒(シェリー)とその同類の酒への言及の多さが群を抜いているとも語っています。どうやらシェークスピアの劇作の中では、ボルドーワインは期待する程の地位は占めていなかったようです。余談ですが、シェークスピア劇の例えば「ハムレット」の中で、“We'll hear a play tomorrow”と言っています。日本でならばさしずめ「芝居を見る」というところでしょうが、それが全作品を通してしばしば「芝居を聴く」、hearになっているのです。これはシェークスピア劇がセリフの芝居といわれていた  こと、そして小劇場で演じられていたことにより、当時は「見る」芝居よりも、「聴く」芝居であったからかもしれません。ワインをテースティングする時の「聴く」にも通じるように思うのですが、如何でしょうか。 こと、そして小劇場で演じられていたことにより、当時は「見る」芝居よりも、「聴く」芝居であったからかもしれません。ワインをテースティングする時の「聴く」にも通じるように思うのですが、如何でしょうか。そしてアンドレ・シモンは数々のワインに関する名著を世に送り出しています。代表作といえば『THE COMMONSENSE OF WINE』(1966年、邦訳『世界のワイン』(1973年))でしょう。その中で「ワインに関する書物は役に立つと思うか」との問いに、「道路標識と旅行者の関係のようなものだ。書物によって人はワインに関する正しい知識を得ることができる。しかし、活字は活字以外のなにものでもない。始めにして終わりはグラスの中の生きたワインだ。道標がなくてもドライブはできるが、ガソリンがなければ車は走らない」と答えています。“一瓶のワインには、万巻の書物よりも多くの哲学が詰まっている”とのルイ・パストゥールの言葉を思い出します。また「ワインは良い飲みものと思うか」に対しては、「およそこの世の飲みものの中で、最も優れたものだと確信している。何故なら、まず水よりも品が良い、牛乳より安全だ。まして清涼飲料水よりさっぱりしている。ビールより気がきいているし、スピリッツほど激しくない。視覚、嗅覚、味覚の発達した人にとって、今日までに発見された他のいかなる飲みものよりはるかに快適だからだ」と答えています。そして「あなたが良いと思ったワインが一番良いワインだ」とも言っております。蓋し名言です。でも、私にはアンドレ・シモンの本ではちょっと苦い思い出があります。彼の初期の著作である『The history of the wine trade in England』(1906-1909年)の3巻の大著を本郷の西洋古書店で偶然見つけたのですが、近所の古書店を回ってから買おうと思い、後でもう一度その店に立ち寄った時には残念ながら既に売れてしまっておりました。それ以降この本とは海外の古書店でも巡り合えません。古書というのは何冊もないので、これといった本に出合ったら、その時には迷わずに瞬時に決心して買うのが鉄則だということを改めて思い知らされました。世の中は不思議なもので何処かに必ず自分と同じ思考をする人がいて、その人が一足先に、自分だけに価値があると思っていた本をさらっていってしまったのだと諦めることにしています。 それと英国人の著作で忘れてはならないのが、“知の巨人”、“酒仙”と讃えられているエディンバラ大学のジョージ・セインツベリー教授の書かれた『NOTES ON A CELLAR-BOOK』(1920年)です。初版本を友人がニューヨークの古書店で見つけて送ってくれた時はうれしかったです。この本は『セインツベリー教授のワイン道楽』(1998年)というタイトルで、何と出版されてから78年後に初めて邦訳されたのです。英国人の間ではワインに関する必読の書として代々読み継がれているという名著です。それだけワインについての知識が英国の上流階級や知識人にとって必須の教養になっているのでしょう。ただ、本書に紹介されている内容は私たちの今日の状況とは異なり、当時は長く寝かせた年代もののワインを好んで味わっていたこと、そして20世紀初頭の頃は食前酒を嗜む習慣はなく、ポートやリキュールだけでなくクラレット(英国での赤のボル  ドーワインの愛称)までも、専ら夕食後に楽しんでいたようです。“英国人のワイン”とも呼ばれるポート、そしてシェリーをこよなく愛していたことも分かります。教授が自宅のセラーで保管している19世紀珠玉のボルドーのグラン・クリュ・ワインがリストアップされているのは正に壮観です。そして最後に教授の味わった数々の思い出のメニューと共にその時のワインが載っています。教授のクモの巣の張ったセラーの中の銘醸ワインから芳しき香りが伝わってくるような奥深い本です。同種の本にはモーリス・ヒーリ著『STAY ME WITH FLAGONS』(1940年、未訳)やモルトン・シャンド著『A BOOK OF FRENCH WINE』(1928年、未訳)があります。 ドーワインの愛称)までも、専ら夕食後に楽しんでいたようです。“英国人のワイン”とも呼ばれるポート、そしてシェリーをこよなく愛していたことも分かります。教授が自宅のセラーで保管している19世紀珠玉のボルドーのグラン・クリュ・ワインがリストアップされているのは正に壮観です。そして最後に教授の味わった数々の思い出のメニューと共にその時のワインが載っています。教授のクモの巣の張ったセラーの中の銘醸ワインから芳しき香りが伝わってくるような奥深い本です。同種の本にはモーリス・ヒーリ著『STAY ME WITH FLAGONS』(1940年、未訳)やモルトン・シャンド著『A BOOK OF FRENCH WINE』(1928年、未訳)があります。それと個別の詳しい本となると、これも英国人の独壇場です。残念ながら邦訳はされていませんが、エドマンド・ペニング・ローゼル著『THE WINES OF BORDEAUX』(1969年),特に、シャトー個別の物語としては、シリル・レイ著『LAFITE』(1968年)やニコラ・フェース著『CHÂTEAU MARGAUX』(1980年)、『LATOUR』(1991年)等があります。更に、マニアックな話になって恐縮ですが、私の手元に『THE WINE AND SPIRIT MERCHANT』というロンドンで発行された古書があります。この本には刊行年が何処にも明記されていませんが、19世紀以前に書かれていることが分かるのです。何故かといいますと、本書の文中に出てくる現在のボルドー第1級格付けの<CHÂTEAU LAFITE>が<CHÂTEAU LAFITTE>とTがダブって表記されているからです。これは20世紀にはない表記で、1707年頃からロンドン・ガゼット紙には“  LAFITTE”という名前で登場しています。このような謎解きの楽しみもあります。 LAFITTE”という名前で登場しています。このような謎解きの楽しみもあります。それとコリン・ウイルソン著『A BOOK OF BOOZE』(1974年)も面白いです。邦題『わが酒の讃歌』(1985年)として田村隆一の名訳で刊行されました。コリン・ウイルソンの理性と感性が光るワイン遍歴書です。 スコッチ・ウイスキーで有名な英国はワインができなかった(つくったことはありますが、いいワインはできませんでした)ので、いきおい輸入に頼らざるを得なかったわけです。そこで世界の貿易大国として君臨していた大英帝国は世界各地から様々なワインを輸入し、愛飲するようになりました。ボルドーワインが世界に冠たる地位を占めるようになったのも、もとをただせば英国の貿易力のお陰であったわけです。そうしたお国柄であったためか、どうしても多種多様な酒の知識が必要になり、ワイン書というジャンルが必然的に生まれてきたのでしょう。何故ワインの名著がフランスやイタリアのようなワイン生産国より英国に多いのかの、ひとつの理由がそこにあるように思います。 次回はアメリカとフランスのワイン書について述べてみようと思います。 |
上の |