|
- 余話:音楽と絵について(その2) -  セノオ楽譜と竹久夢二 |
| 今回は『セノオ楽譜』と竹久夢二を中心に、『スポーツと気晴らし』との関連についても私見を述べてみたいと思います。暫しのお付き合いをお願いいたします。 大正ロマンの時代に一世を風靡したといわれる『セノオ楽譜』については、大正、昭和そして平成と三代の時を経て、もうその存在すら知らない世代(かくいう私もそうです)も多くなってきたのではないかと思いますので、先ずは『セノオ楽譜』のお話からはじめてみたいと思います。 『セノオ楽譜』は、妹尾幸陽(せのお・こうよう、本名幸次郎)が洋の東西の名 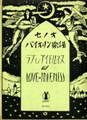 曲名歌の数々を、古きも新しきも紹介するために1910年(明治43年)より発行をはじめた音楽出版物です。この楽譜の表紙絵は、竹久夢二をはじめ杉浦非水、岡田九郎などの多くの有名画家が腕を競い合いました。現在分かっているだけでも1044点に及ぶ膨大なものです。その内容は、独唱曲が最も多く、ヴァイオリン曲、ピアノ曲、合唱曲そして軍歌、鉄道唱歌など広範囲に亘っており、斬新な表紙の装画と共に一曲ずつを一つの印刷物とするピースものと呼ばれている極めて水準の高い楽譜です。20世紀のはじめ、レコードやラジオがまだ普及していなかった頃に音楽を広めるための手段として楽譜は有力なメディアであったの 曲名歌の数々を、古きも新しきも紹介するために1910年(明治43年)より発行をはじめた音楽出版物です。この楽譜の表紙絵は、竹久夢二をはじめ杉浦非水、岡田九郎などの多くの有名画家が腕を競い合いました。現在分かっているだけでも1044点に及ぶ膨大なものです。その内容は、独唱曲が最も多く、ヴァイオリン曲、ピアノ曲、合唱曲そして軍歌、鉄道唱歌など広範囲に亘っており、斬新な表紙の装画と共に一曲ずつを一つの印刷物とするピースものと呼ばれている極めて水準の高い楽譜です。20世紀のはじめ、レコードやラジオがまだ普及していなかった頃に音楽を広めるための手段として楽譜は有力なメディアであったの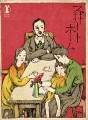 でしょう。また大正ロマンという時代は、華麗な西洋文化が大衆の娯楽として広がりはじめた時であり、西洋の音楽を身近に感じるようになった時代でもあったのだと思います。『セノオ楽譜』の選曲や訳詞や装画の中に感じる懐かしさは、大正時代に西洋音楽と出合った大衆のみずみずしい感動へのオマージュといえるかもしれません。丁度時を同じくしてフランスでは1910年代から1930年代にかけてアール・デコの華やかりし時でもありました。世界の動きの類似性、連動性には誠に面白いものがあり、その偶然性にはしばしば驚かされます。前回述べました『スポーツと気晴らし』と でしょう。また大正ロマンという時代は、華麗な西洋文化が大衆の娯楽として広がりはじめた時であり、西洋の音楽を身近に感じるようになった時代でもあったのだと思います。『セノオ楽譜』の選曲や訳詞や装画の中に感じる懐かしさは、大正時代に西洋音楽と出合った大衆のみずみずしい感動へのオマージュといえるかもしれません。丁度時を同じくしてフランスでは1910年代から1930年代にかけてアール・デコの華やかりし時でもありました。世界の動きの類似性、連動性には誠に面白いものがあり、その偶然性にはしばしば驚かされます。前回述べました『スポーツと気晴らし』と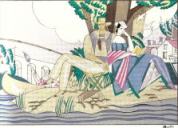 今回の『セノオ楽譜』との関連について、ある共通なことが思い浮かんでまいります。『スポーツと気晴らし』は、フランスの家庭にピアノが普及しはじめた頃に、優雅なご婦人の客間を飾る楽譜として、エリック・サティの序と20曲のピアノ小曲の楽譜と、それと交互に配されたシャルル・マルタンの20点の絵(ポショワール)が制作され、限定版の音楽アルバムとして世に出ました。それに対し、『セノオ楽譜』は当時誰でもが購入できる大衆 今回の『セノオ楽譜』との関連について、ある共通なことが思い浮かんでまいります。『スポーツと気晴らし』は、フランスの家庭にピアノが普及しはじめた頃に、優雅なご婦人の客間を飾る楽譜として、エリック・サティの序と20曲のピアノ小曲の楽譜と、それと交互に配されたシャルル・マルタンの20点の絵(ポショワール)が制作され、限定版の音楽アルバムとして世に出ました。それに対し、『セノオ楽譜』は当時誰でもが購入できる大衆 版であったという違いはありますが、双方の発想は極めて似ているということです。果たして、どちらが最初に思いついたのでしょうか、大変興味のあるところです。大正時代は西洋文化が堰を切ったように広がりはじめた頃であり、横開きにして楽譜に挿絵を付けた出版物が当時のフランスでは流行のひとつであったことからも、妹尾幸陽がそのことを知って日本でもやってみようと思いついたと考えるのは素直な推論であるかもしれません。1913年には絵本画家のアンドレ・エレとクロード・ドビュッシーによる『おもちゃ箱(La boîte à joujoux)』が既に出版されています。でもここで注目しなければならないことは、妹尾幸陽が楽譜の出版をはじめたのは1910年といわれておりますので、それより3年も早いということです。でも、この時の楽譜が果たして表紙絵付きのものであったのかは残念ながら不明です。しかし、そうした皮相な相似性や時空を遥かに越えて、それぞれは独創的な考えによっていたのかもしれません。当時、フランスそして日本にあって、双方が芳しき香気を漂わせていたのは間違いないことでありましょう。 版であったという違いはありますが、双方の発想は極めて似ているということです。果たして、どちらが最初に思いついたのでしょうか、大変興味のあるところです。大正時代は西洋文化が堰を切ったように広がりはじめた頃であり、横開きにして楽譜に挿絵を付けた出版物が当時のフランスでは流行のひとつであったことからも、妹尾幸陽がそのことを知って日本でもやってみようと思いついたと考えるのは素直な推論であるかもしれません。1913年には絵本画家のアンドレ・エレとクロード・ドビュッシーによる『おもちゃ箱(La boîte à joujoux)』が既に出版されています。でもここで注目しなければならないことは、妹尾幸陽が楽譜の出版をはじめたのは1910年といわれておりますので、それより3年も早いということです。でも、この時の楽譜が果たして表紙絵付きのものであったのかは残念ながら不明です。しかし、そうした皮相な相似性や時空を遥かに越えて、それぞれは独創的な考えによっていたのかもしれません。当時、フランスそして日本にあって、双方が芳しき香気を漂わせていたのは間違いないことでありましょう。それでは妹尾幸陽(1891-1961)とは一体どのような人物であったのでしょうか。少ない資料からその人物像を覗いてみようと思います。妹尾幸陽は明治24年に東京で生まれ、慶應義塾で学んでいましたが中退し、その後時事新報の記者を経て、1915年(大正4年)にセノオ音楽出版社を設立したと記されています。その時幸陽は弱冠24歳です。更に最初の楽譜の出版年、1910年が事実だとすればまだ20歳にも満たない若さです。尤も、1908年(明治4 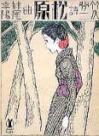 1年)に創刊された『音楽界』の中で歌劇ファースト、メリイウィドウ、マダムバタフライ等について既に多くの論評をしていることからも、幸陽の音楽に対する早熟さが窺い知れます。また夢二の詩を愛好し、『セノオ楽譜』の中には夢二作詞のものに幸陽自ら曲をつけたものが24曲もあります。1925年(大正14年)には東京放送局(現NHK)開始時の初代洋楽部長に就いていることからも、西洋音楽への造詣が深かったことが分かります。慶應を中退した後に音楽学校へ行ったのかとも思いますが、幸陽自身は詳らかにしていません。ただ、幸陽が音楽に目覚めたのは14歳の時であったと自らを語っています。洋楽部長を務め、作曲等の音楽関係に深く携わっていたところからみて、当時フランス等に洋行して楽譜と挿絵を合作した出版物を目にしたか、それとも西洋文化に多大の憧れをもっていた7歳年上の夢二からそのことを聞き及んだのか、或いは何らかの情報を得てそのような出版物があるのを知っていたのではないかと考えるのが自然のように思われますが、年若い24歳の幸陽が、一体どのような意図から 1年)に創刊された『音楽界』の中で歌劇ファースト、メリイウィドウ、マダムバタフライ等について既に多くの論評をしていることからも、幸陽の音楽に対する早熟さが窺い知れます。また夢二の詩を愛好し、『セノオ楽譜』の中には夢二作詞のものに幸陽自ら曲をつけたものが24曲もあります。1925年(大正14年)には東京放送局(現NHK)開始時の初代洋楽部長に就いていることからも、西洋音楽への造詣が深かったことが分かります。慶應を中退した後に音楽学校へ行ったのかとも思いますが、幸陽自身は詳らかにしていません。ただ、幸陽が音楽に目覚めたのは14歳の時であったと自らを語っています。洋楽部長を務め、作曲等の音楽関係に深く携わっていたところからみて、当時フランス等に洋行して楽譜と挿絵を合作した出版物を目にしたか、それとも西洋文化に多大の憧れをもっていた7歳年上の夢二からそのことを聞き及んだのか、或いは何らかの情報を得てそのような出版物があるのを知っていたのではないかと考えるのが自然のように思われますが、年若い24歳の幸陽が、一体どのような意図から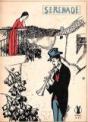 、あのような表紙絵付き大楽譜集成を出版したのか不思議でなりません。ひょっとすると幸陽が独自に考えついたのかもしれません。むしろ私としては、そう思いたいのですが・・・。そうであれば世界に先駆けたすばらしい発想であり、わが国の音楽史上において大いに誇るべき、輝かしい業績ではなかったかと思います。いずれにしましても、時代の先駆者たちは洋の東西を問わず、偶然機を同じくしてこのような面白い発想をするものかもしれません。 、あのような表紙絵付き大楽譜集成を出版したのか不思議でなりません。ひょっとすると幸陽が独自に考えついたのかもしれません。むしろ私としては、そう思いたいのですが・・・。そうであれば世界に先駆けたすばらしい発想であり、わが国の音楽史上において大いに誇るべき、輝かしい業績ではなかったかと思います。いずれにしましても、時代の先駆者たちは洋の東西を問わず、偶然機を同じくしてこのような面白い発想をするものかもしれません。夢二人気の陰に隠れて妹尾幸陽の存在は現在に至るもどうも影が薄いように思われます。大衆に音楽を普及させたこの表紙絵付き楽譜の果たした役割はもっと注目され、再評価されてしかるべきではないかと思いますが、幸陽の本当の魅力とは何かを知る  には遺された資料が少なすぎました。今後幸陽研究が進むことを切に願うものです。 には遺された資料が少なすぎました。今後幸陽研究が進むことを切に願うものです。さて、次はいよいよ竹久夢二(1884-1934)にご登場願おうと思います。ここでは紙数の制限から『セノオ楽譜』と夢二の関係についてのみに的をしぼり、夢二の画風やフランス絵画との関連については次回に述べたいと思います。 『セノオ楽譜』に夢二の絵が登場するのは、楽譜番号12の《お江戸日本橋》が最初です(1916年、大正5年)。それから1927年(昭和2年)までの間に、『セノオ楽譜』の表紙のために273点の装画を描きつづけました。これらの装画には、日本・西洋の名曲名歌に合わせて歌の心を描き抜いた、夢二の古典的浮世絵、デフォルメした心象画、目を見張る抽象画、モダンなアール・ヌーヴォーやアール・デコ 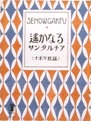 風のデザイン画など、才気溢れる意匠と多様な手法が総動員されています。また、歌曲のタイトルのレタリングにもそれぞれ優れた感覚と創意工夫が窺われます。それらは永遠にモダンであり、永遠に新しいもののよ 風のデザイン画など、才気溢れる意匠と多様な手法が総動員されています。また、歌曲のタイトルのレタリングにもそれぞれ優れた感覚と創意工夫が窺われます。それらは永遠にモダンであり、永遠に新しいもののよ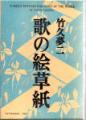 うに感じます。夢二は『セノオ楽譜』の中でグラフィック・デザイナーとしての先駆的な仕事もしてきたのです。 うに感じます。夢二は『セノオ楽譜』の中でグラフィック・デザイナーとしての先駆的な仕事もしてきたのです。ここに『歌の絵草紙』(昭和41年、龍星閣)という一冊の美本があります。そこには夢二が大正3年から昭和2年まで、『新小唄』(35篇全て夢二の表紙ですが、その中に夢二の詩が17篇あり、それを全て妹尾幸陽が作曲しています)と『セノオ楽譜』の両方の表紙に描いた装画280点が収められています。この本は夢二の絵と各作詞を並べて鑑賞できるようになっていますが、絵を主体としているため残念ながら楽譜は付いておりません。 ところで、『セノオ楽譜』の中で、夢二の詩として最もよく知られているのは七五調の短い詩、「宵待草」(1918年、大正7年)の一篇でしょう。  まてどくらせどこぬひとを 宵待草のやるせなさ こよひは月もでぬさうな この抒情豊かな夢二の詩に共感した多忠亮(おおの・ただすけ)が作曲し、そのやるせなく甘い調べはやがて大正時代の日本を風靡することになります。現代に至るも歌い継がれ、その生命の輝きは失っていないように思います。因みに、植物学的には「まつよいぐさ(待宵草)」が正しいようですが、『セノオ楽譜』(楽譜番号106)の表紙も版により「待宵草」と「宵待草」の2種類の表記があります。また、夢二自身の自筆記録(大正9年)には「待宵草」となっています。しかし、口に出してみますと「・・・こぬひとを待宵草」とつづくと極めて発音しにくいのに、「よいまちぐさ」の音律は大変口にのりやすく、曲がつくと、もうこれは「まつよいぐさ」では歌えないように思いますが、如何でしょうか。 このように夢二は、文学と美術と音楽の響き合いに興味をもっていたようですので、楽譜の表紙絵はうってつけの舞台であったのでしょう。夢二はそこで、和洋の様々な表現を自由に繰って、楽しげな実験を繰り広げたのではないでしょうか。『セノオ楽譜』の発行当時は楽譜への要求が多かったにせよ、これだけの人気を博した要因として夢二の表紙絵の魅力が大きく与っていたのは紛れもない事実でありましょう。 ある旅館の主(あるじ)の思い出として、「セノオ楽譜を見ながら、チェロを弾いていますと、突然、私の脇に立った人が、その歌はぼくがつくったのだ、と言われたのか、その楽譜の絵は、ぼくが描いたのだ、と言われたのか、ともかく、そうした意味のことを言われたので私はびっくりして、竹久さんですかと言ったのです。それまで、夢二さんが、私の家に泊っていることを私は知らなかったのです」といった逸話が残されているくらいですから、『セノオ楽譜』は一般大衆にも膾炙していたことがよく分かります。しかしながら、関東大震災以降、レコードの普及とラジオ放送のはじまりにより、やがて楽譜の表紙絵の黄金時代は終焉を迎え、歴史から静かに消え去る運命を辿ることになります。 次回はアール・デコ時代のイラストをはじめとするフランス絵画と夢二の関連を中心に少しく語ってみたいと思います。 |
上の |