|
- 余話の余話:梅若丸伝説について -  <隅田川> |
| 今回は<シャトー訪問記>を一時お休みさせてもらい、皆様をわが国古典文学・芸能の世界に誘(いざな)おうと思います。実は昨年のお正月にボルドー第3大学で哲学を研究している友から一通のメールが舞い込んできました。そこには1月(昨年)にボルドーから日本の古典文学を研究している女史が来日し、「フランスから見た梅若丸伝説について」の講演をされるので是非参加して会って欲しいというものでした。なに「梅若丸」だと、牛若丸なら知っているが・・・、取敢えずインターネットを開けてみると確かに「梅若丸」に纏わることがいろいろと書かれてあります。読み進めるうちに少しずつ興味が湧いてきました。フランス人女性が日本人でも余り知識がないと思われる(私だけかもしれませんが)、梅若丸伝説を語るとは面白い、是非講演会に参加してお会いしてみようと、早速に講演場所である「すみだ郷土文化資料館」へ申し込みました。当日は隅田川を吹きすさぶ風は冷たく、言問橋を渡って漸く資料館へ辿り着くと部屋は既に満員の盛況です。廊下には懐かしいボルドーの写真がいろいろ飾られており、その中には私の友も写っておりました。 女史はヴィヴィアンヌ・ドュヴェルジェ(Madame Viviane DUVERGÉ)さんというお名前の市井の研究者です。フランス語で2時間余に亘って講演されましたが、わが国の古典文学・芸能に対する豊かな感性と深い洞察力に只々感銘し感動してしまいました。 彼女の講演内容に入る前に「梅若丸伝説」なるものがどういうものか、先ずは、能の「隅田川」を例にとって簡単なあらすじを述べてみたいと思います。 春の夕暮れ時、武蔵の国隅田川の渡し場で、渡し守が最終の舟を出そうとしていると旅人が現れ、狂女(女物狂)がやってくると告げました。女は京の都北白河に住んでいましたが、わが子が  人買いにさらわれたために心が狂乱し、息子を探しに遥々この地まで来たのでした。渡し守が、狂女に舟に乗りたければ面白く狂って見せろというと、女は『伊勢物語』第九段の「都鳥」の古歌を引き、自分と在原業平とを巧みに引き比べて、「狂い」はじめます。「名にし負はば、いざ言問はん、都鳥、我が思ふ人は、ありやなしやと」を下敷きにして、「我もまたいざ言問はん都鳥、わが思ひ子は東路にありやなしやと・・・」と替え歌に作った一さしの舞は、渡し守ほか周囲の者をすっかり感心させてしまい、無事舟に乗り込むことができました。 人買いにさらわれたために心が狂乱し、息子を探しに遥々この地まで来たのでした。渡し守が、狂女に舟に乗りたければ面白く狂って見せろというと、女は『伊勢物語』第九段の「都鳥」の古歌を引き、自分と在原業平とを巧みに引き比べて、「狂い」はじめます。「名にし負はば、いざ言問はん、都鳥、我が思ふ人は、ありやなしやと」を下敷きにして、「我もまたいざ言問はん都鳥、わが思ひ子は東路にありやなしやと・・・」と替え歌に作った一さしの舞は、渡し守ほか周囲の者をすっかり感心させてしまい、無事舟に乗り込むことができました。川を渡しながら、渡し守は一年前  の今日、三月十五日に対岸の下総の川岸で亡くなった子ども、梅若丸の話を物語り、皆も一周忌の供養に加わってくれと頼みます。舟が対岸に着き皆が下船しても、狂女は降りようとせず泣いています。渡し守がわけを尋ねると、先ほどの話の子はわが子だというのです。 の今日、三月十五日に対岸の下総の川岸で亡くなった子ども、梅若丸の話を物語り、皆も一周忌の供養に加わってくれと頼みます。舟が対岸に着き皆が下船しても、狂女は降りようとせず泣いています。渡し守がわけを尋ねると、先ほどの話の子はわが子だというのです。渡し守は狂女に同情し、手助けして梅若丸の塚に案内し、大念仏で一緒に弔うよう勧めます。夜の大念仏で、狂女が母として、鉦鼓を鳴らし、念仏を唱え弔っていると、塚の中から梅若丸の亡霊が現れます。抱きしめようと近寄ると、幻は腕をすり抜け、母の悲しみは一層増すばかり。やがて東の空が白みはじめ、夜明けと共に亡霊の姿も消え、母はただ草ぼうぼうの塚で涙にむせぶのでした。 といった千古不易の親子の情愛を主題とする能が「隅田川」のあらすじです。これを踏まえ、フランス人女性の驚くほど繊細な感性に触れて、日本古来の伝説や古典文学がどんな風に変身をとげ、またどんな風にその本質を顕すのかを、デュヴェルジェさんの2時間余に亘る講演の中で、私の記した拙いメモからとくとお感じになってくだされば幸いです。 デュヴェルジェさんは今から15年ほど前にパリの東洋語学校(INALCO,フランスで一番有名な語学研究所を最優秀の成績でご卒業されました)で「伊勢物語」に出合い、「梅若丸伝説」を詳しく知ったことで人生観そのものまで変わったといいます。日本文学はフランスから最も遠い距離にあり、文化的・言語的な隔たりを感じつつも、語学的な困難さは逆に豊かなものを見せてくれ、刺激的な闘いでもあったようです。それは分からないなりに自由に想像力を働かせることができたからといいます。  「梅若丸伝説」― 何がそれ程までに感動させたのか、それは「梅若丸伝説」を生んでくれた文化をフランスという外から眺めることができたこと。そして隅田川と出会い、文化的に高い価値を見出したからだといいます。「梅若丸伝説」との初めての出会いは、東洋語学校から更に5年ほど遡り、ボルドー第3大学教授から文法の授業の例文として、「梅若丸伝説」の一節を引用されたことにはじまります。隅田川というものが自分の人生にかかわりはじめたというより、隅田川という川が自分の人生に流れ込んで来たように感じたとのこと。そして「伊勢物語」第九段の“ゆりかもめ(都鳥)”に出合った。この”ゆりかもめ”という5音節の美しい響きに魅かれたといいます。そして古語のもつ深さに感じ入ったようです。 「梅若丸伝説」― 何がそれ程までに感動させたのか、それは「梅若丸伝説」を生んでくれた文化をフランスという外から眺めることができたこと。そして隅田川と出会い、文化的に高い価値を見出したからだといいます。「梅若丸伝説」との初めての出会いは、東洋語学校から更に5年ほど遡り、ボルドー第3大学教授から文法の授業の例文として、「梅若丸伝説」の一節を引用されたことにはじまります。隅田川というものが自分の人生にかかわりはじめたというより、隅田川という川が自分の人生に流れ込んで来たように感じたとのこと。そして「伊勢物語」第九段の“ゆりかもめ(都鳥)”に出合った。この”ゆりかもめ”という5音節の美しい響きに魅かれたといいます。そして古語のもつ深さに感じ入ったようです。フランス語では隅田川は<La Sumida>と4音節になり、日本語の“すみだがわ”の響きの方が遥かに美しいといいます。隅田川という場所の持つ重要性、能における隅田川の役割の重要性を説きます。果たして21世紀の日本では隅田川の存在はあるのかと疑問を投げかけます。彼女が初めて見た隅田川は、川開き、花火、沢山の舟の出入り、下町、関東平野等々、楽しみ、悲しみそして親しみが交錯していたという。家族の一員として隅田川が扱われているように感じたらしいのです。 大学院の卒論のテーマは「隅田川、その現実とイメージ」であった。初めての来日時に見た隅田川は♪春のうらあらあの隅田川・・・♪の歌そのものであった。隅田川は私に語りかけてくれました ― 冒険に身を投じてご覧と。四季折々の姿を見せる隅田川。隅田川と子供にも興味を抱いた。 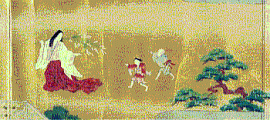 木母寺(もくぼじ)の梅若忌で「能と梅若権現絵巻」を初めて見た時の衝撃はいまだに忘れられない。彼女は絵巻物の一つの絵(梅若丸の死を2匹の猿が覗いている場面)をスライドに映し、身振り手振りでそのすばらしさを説明してくださいました。虫眼鏡まで取り出して猿の優しい表情を読み取ったといいます。”Légende d’Umewaka(梅若丸伝説)”!伝説の方からまたもや私に語りかけてくれた ― 「時」を、そして「空間」を越えてやって来なさいと。今でもヨーロッパ文学に脈々と影響を与え、インスピレーションを与え続けている ― イギリスの音楽家ブリテンは、能「隅田川」をもとにオペラ「カーリュウ・リヴァー(Curlew River)」を作曲した。 木母寺(もくぼじ)の梅若忌で「能と梅若権現絵巻」を初めて見た時の衝撃はいまだに忘れられない。彼女は絵巻物の一つの絵(梅若丸の死を2匹の猿が覗いている場面)をスライドに映し、身振り手振りでそのすばらしさを説明してくださいました。虫眼鏡まで取り出して猿の優しい表情を読み取ったといいます。”Légende d’Umewaka(梅若丸伝説)”!伝説の方からまたもや私に語りかけてくれた ― 「時」を、そして「空間」を越えてやって来なさいと。今でもヨーロッパ文学に脈々と影響を与え、インスピレーションを与え続けている ― イギリスの音楽家ブリテンは、能「隅田川」をもとにオペラ「カーリュウ・リヴァー(Curlew River)」を作曲した。何故それ程までに感動させるのか?それは芸術的な形式面 ― 物語を形作る和歌や他の古典文学の引用である。例えば、謡曲の隅田川の引用。フランス文学には2つの古典物語を織り交ぜる手法はない。フランス演劇(17世紀)は原典を使用するが、分からないようになっている。シテの狂女は具体的に伊勢物語を重ね合わせている。文学的な記憶、即ち古典を知っている。「梅若丸伝説」には、知的な興味を起こさせるものが沢山ある。 能の「隅田川」は決して悲劇ではない。この安らぎは仏教の微妙なズレから生じるものかもしれない。モヤのようなポエジーである。西洋の悲劇は古代ギリシャまで遡るが、それは固いもので、美しいものではない。そして優しさを受け入れるものではなく厳しい。「梅若丸伝説」をフランス悲劇に置き換えるには相当の無理がある。西洋悲劇とは相容れないものがある。ラシーヌの文学とも違う。フランス人に感想を求めると梅若丸は死んでいるが、決して悲劇ではないという。そこには詩的なものが存在し美しいから。子供は死んでいなく一本の柳として生きつづけ、希望があるからと。これは仏教的な考え方には出口があるからなのかもしれない。物語は普遍的でもある。 最後に彼女の希望で♪春のうらあらあの隅田川・・・♪の<花>をみんなで合唱して終わりました。感動的な2時間余でした。 といったのがデュヴェルジェさんの講演から特に感じた私のメモ書きですが、恥ずかしながら「梅若丸伝説」をはじめ「伊勢物語」、能の「隅田川」等に殆ど知識のなかった私には、正直彼女の話をどう結びつけていけばいいのか、残念ながらはっきり分かりませんでした。でも彼女の「梅若丸伝説」をはじめわが国古典文学・芸能への深い思いはよく理解できました。そしてこのようなわが国古典文学・芸能の市井の研究者がボルドーに居られたことに感動すら覚えました。  あのボルドーの懐かしいガロンヌ河の流れを毎日眺めながら生活している彼女に。そして彼女を知るきっかけをつくってくれたボルドー第3大学の若き哲学研究者の友に感謝したいと思います。人の巡り合いは不思議で楽しいものです。彼女と暫く話しましたが、最後に私のことを“élégant”と言ってくださったのが自慢です。 あのボルドーの懐かしいガロンヌ河の流れを毎日眺めながら生活している彼女に。そして彼女を知るきっかけをつくってくれたボルドー第3大学の若き哲学研究者の友に感謝したいと思います。人の巡り合いは不思議で楽しいものです。彼女と暫く話しましたが、最後に私のことを“élégant”と言ってくださったのが自慢です。その後デュヴェルジェさんの講演にすっかり感化されて、一年余りに亘って「伊勢物語」をはじめ能・狂言・謡曲関係の本を読み漁りました。また偶々同じ立教大学で学んでいる狂言師と出会い、国立能楽堂で能、狂言を鑑賞する機会にも恵まれました。ということで、西洋のワイン文化に現(うつつ)を抜かすだけでなく、遅ればせながらわが国本来の古典文学・芸能のすばらしさに目覚めたことは、何とも豊かで幸せな気持ちにさせてくれました。芥川龍之介は『金春会の隅田川』という随筆の中で「僕は兎に角「隅田川」に美しいものを見た満足を感じた。― それだけ云ひさいすれば十分である」と書いています。  ところで、「隅田川」で特色的な「物狂い」というのは、今の言葉でいうと芸能者というほどのことであり、感情の高ぶりの果てに恍惚として芸能をする、これは日常正気の姿に比すれば、確かに「狂っている」のでしょう。ここを巧みに劇化したのが能の狂い物で、「隅田川」は代表作であることも理解できたように思います。今も「隅田川」を見て落涙する人は多いでしょう。それは取りも直さず、この能が如何に人類普遍の問題を鮮やかに切り取っているか、彼女の話からも十分わかるような気がしてまいりました。だからわが国古典芸能のひとつである能が、いつまでも古びないのは、つまり、そういう生々しい魂を内在させているからなのでしょう。大きな収穫をしたかのように感じてうれしかったです。 ところで、「隅田川」で特色的な「物狂い」というのは、今の言葉でいうと芸能者というほどのことであり、感情の高ぶりの果てに恍惚として芸能をする、これは日常正気の姿に比すれば、確かに「狂っている」のでしょう。ここを巧みに劇化したのが能の狂い物で、「隅田川」は代表作であることも理解できたように思います。今も「隅田川」を見て落涙する人は多いでしょう。それは取りも直さず、この能が如何に人類普遍の問題を鮮やかに切り取っているか、彼女の話からも十分わかるような気がしてまいりました。だからわが国古典芸能のひとつである能が、いつまでも古びないのは、つまり、そういう生々しい魂を内在させているからなのでしょう。大きな収穫をしたかのように感じてうれしかったです。ただひとつ疑問に思うのは、わが国のどの著作を読んでも「隅田川」は悲劇であると断言していることです。でもデュヴェルジェさんのお話では、フランス人は悲劇とは思っていないという疑問です。この答えのひとつはパリ在住の作曲家、吉田進氏の言葉にヒントが隠されているように思われます。彼の新作能オペラ「隅田川」がフランス北西部カンペールで初演され、「感動に満ちたオペラ」(テレグラム紙)などフランス各紙で絶賛されました。そこで彼は「隅田川は単なる悲劇ではなく、人間が出会いを通して復活できるというのが真のテーマだと気がついた」と述べていることです。 また、桜に縁のある能のひとつが「隅田川」であるといわれています。これは別に桜が主題であるわけでなく、舞台にもそれらしき様子は現れないが、時期をことさらに旧暦三月十五日に設定し、隅田川の堤を舞台にしているからなのでしょう。それを見る観客はおのずから心の目に桜を見ながら、物語の余りにも哀れな運命が、桜の花のおぼろげなる雰囲気と対象をなしてこの曲を聴くからでしょうか。 「春は名のみの風の寒さや」の余寒の季節に、一足早く桜の頃を思い出させる「梅若丸伝説」のお話をお届けいたします。 私と同じように、これを機にわが国の古典文学・芸能のすばらしさに目覚めていただけますれば幸甚に存じます。 |
上の |