|
- アルケスナン王立製塩工場(3)-  <ショーの理想都市> |
 アルケスナン王立製塩工場のあるフランシュ・コンテは、この地方が生んだ偉大な画家ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)の故郷でもあります。幸運にも私たちがこの製塩工場を訪れた時は、「ギュスターヴ・クールベ特別展」が監督官の館で開催されていました。世界遺産の荘厳な建築の中で絵画展を見るのは、美術館とはまた一味違った趣があり、大変貴重な経験になりました。クールベといえば写実主義の代表として知られ、「生きた芸術を生み出すこと、それが私の目標」と、理念と空想の芸術 アルケスナン王立製塩工場のあるフランシュ・コンテは、この地方が生んだ偉大な画家ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)の故郷でもあります。幸運にも私たちがこの製塩工場を訪れた時は、「ギュスターヴ・クールベ特別展」が監督官の館で開催されていました。世界遺産の荘厳な建築の中で絵画展を見るのは、美術館とはまた一味違った趣があり、大変貴重な経験になりました。クールベといえば写実主義の代表として知られ、「生きた芸術を生み出すこと、それが私の目標」と、理念と空想の芸術 を否定し、芸術から神話・宗教・歴史・文学を追放し、単なる古典絵画の模倣でなく、今の時代の風景、人々、現実を自分の感じたままに描くということにありました。代表作『オルナンの埋葬』、『画家のアトリエ』の2つの大作の他に、森の中の動物を主題にした風景画や、謎に包まれた官能的な『世界の起源』等、数多くの傑作を世に遺しています。 を否定し、芸術から神話・宗教・歴史・文学を追放し、単なる古典絵画の模倣でなく、今の時代の風景、人々、現実を自分の感じたままに描くということにありました。代表作『オルナンの埋葬』、『画家のアトリエ』の2つの大作の他に、森の中の動物を主題にした風景画や、謎に包まれた官能的な『世界の起源』等、数多くの傑作を世に遺しています。さて、本題のクロード・ニコラ・ルドゥーの話に戻ります。ルドゥーの生きた18世紀のフランスは、「啓蒙の時代」とか「理性の時代」とよくいわれています。「啓蒙主義」とは、反封建的な合理主義の思想です。このことは当時の教会の権威に基づく保守的な制度に対し、理性の啓蒙による進歩を目指したもので、やがて教会と王への攻撃がはじまりました。このようにして「啓蒙主義」はフランス革命の思想的バックボーンになっていったのです。でも、ルドゥーの中には単純に「理性の時代」だけでは割り切れない何かがあったように思います。それはある種の“超越性”かもしれません。超越的なものの上に崇高性のような視点を意図的に取り出していって、それをイメージ化するとどうなるかということを考えていたように思われます。超越となると、バロック時代の神のイメージが既にありました。無限の神です。美の対立概念としての崇高性です。それはおどろおどろしくて奇妙でというような、美に対立するものです。それがルドゥーの仕事に登場し、ひとつの建築作品としてアルケスナン王立製塩工場にも見えてくるような気がしてきます。 ところで、18世紀の啓蒙主義の時代、ルドゥーの同時代人にあ  のマルキ・ド・サドという突き抜けた合理主 のマルキ・ド・サドという突き抜けた合理主 義者が登場してきます。サドの小説、例えば『ソドムの120日』の構図の論理性、説明の仕方の合理性は徹底しており、非常に明快なロジックをもっています。そしてストーリーが組み立てられていく描写の空間がフリーメーソン(中世の石工(メーソン)のギルドに端を発する知識階級の秘密結社)の入信儀式のプロセスと殆ど同じ内容で、人も状況も構成されているといわれています。ルドゥーの著作で説明された製塩工場に辿りつくプロセスもかなり儀式的であると思います。当時はフリーメーソンに入っていなかったら建築家とみなされなかったようですので自然の成り行きだったのでしょう。今日の視点からみると、フリーメーソンのイニシエーションの儀式などは、およそ啓蒙主義とは無縁のように思いますが、あの18世 義者が登場してきます。サドの小説、例えば『ソドムの120日』の構図の論理性、説明の仕方の合理性は徹底しており、非常に明快なロジックをもっています。そしてストーリーが組み立てられていく描写の空間がフリーメーソン(中世の石工(メーソン)のギルドに端を発する知識階級の秘密結社)の入信儀式のプロセスと殆ど同じ内容で、人も状況も構成されているといわれています。ルドゥーの著作で説明された製塩工場に辿りつくプロセスもかなり儀式的であると思います。当時はフリーメーソンに入っていなかったら建築家とみなされなかったようですので自然の成り行きだったのでしょう。今日の視点からみると、フリーメーソンのイニシエーションの儀式などは、およそ啓蒙主義とは無縁のように思いますが、あの18世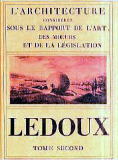 紀の時代では無縁でなく、むしろ同じものと考えていたようです。ルドゥーの“超越性”にも通じるものかもしれません。これからお話ししますルドゥーの大著『芸術・習俗・法制との関係から考察された建築(L'architecture considérée sous le rapport de l'art,des moeurs et de la législation)』もマルキ・ド・サドの『ソドムの120日』も、共に牢獄の中で基礎が組み立てられたということも興味ある事実です。 紀の時代では無縁でなく、むしろ同じものと考えていたようです。ルドゥーの“超越性”にも通じるものかもしれません。これからお話ししますルドゥーの大著『芸術・習俗・法制との関係から考察された建築(L'architecture considérée sous le rapport de l'art,des moeurs et de la législation)』もマルキ・ド・サドの『ソドムの120日』も、共に牢獄の中で基礎が組み立てられたということも興味ある事実です。前置きが少し長くなりました。これから今回の主題であるルドゥーの『芸術・習俗・法制との関係から考察された建築』(以下『・・・建築』と称します)を眺めてまいりましょう。随分とにぎにぎしいタイトルをつけていますが、当時はこういう長いタイトルが流行っていたようです。ルドゥーは、この書物の刊行費用を自分自身の残された財産から捻出しなければなりませんでした。というのは、理想の町のための幻想的な計画案と本文の付いたこの新作を進んで世に出そうという出版社が全く現れなかったからです。ルドゥーはこう語っています。「時の流れの圧力と不実さによって汲み尽くされてしまった財産の残滓と私の余暇とを、こうした心配事に使い切ってしまったあと、私は自分の知るかぎり最大級の収穫品の最初の部分を公表することに決めた。私は、私のあとをついてくることになる人々に、この大部の著作を遺すという計画を立てたのであった」と。ルドゥーは自らが趣意書をつくり上げ、それを学識者たちの会や知人たちに送ったのです。友人への手紙の中でルドゥーは、この著作の文体に誇りを感じていると記し、豪華なつくりのこの著作が必ずや成功を導くことになるという誇りと  期待の念を表しています。ルドゥーが趣意書のなかで理想の町のための計画案を予告したことは、彼の身に次々に降りかかった不幸に打ち砕かれた晩年の気持ちをよく物語っております。このように、ルドゥーの面白いところは、建築書というスタイルを取りながら私事を曝け出していることです。フランス革命の恨みなど個人的な不満をいろいろと述べています。この本はルドゥーのまさに告白の書であり、後世への遺産でもありました。そこにはルドゥーが思想的に大きな影響を受けたジャン・ジャック・ルソーが世に出した自伝的文学のスタイルが混ざっているようにも思えます。そういう意味でもこのテクストのハイブリッド性というか、革新性について世の高い評価を受けていることに合点がいきます。 期待の念を表しています。ルドゥーが趣意書のなかで理想の町のための計画案を予告したことは、彼の身に次々に降りかかった不幸に打ち砕かれた晩年の気持ちをよく物語っております。このように、ルドゥーの面白いところは、建築書というスタイルを取りながら私事を曝け出していることです。フランス革命の恨みなど個人的な不満をいろいろと述べています。この本はルドゥーのまさに告白の書であり、後世への遺産でもありました。そこにはルドゥーが思想的に大きな影響を受けたジャン・ジャック・ルソーが世に出した自伝的文学のスタイルが混ざっているようにも思えます。そういう意味でもこのテクストのハイブリッド性というか、革新性について世の高い評価を受けていることに合点がいきます。実際に建築したアルケスナン王立製塩工場は、本来の理想都市ではなく、ユートピアでもなく、『・・・建築』の本の中で、漸くルドゥー自らが描いた理想の都市を実現させたのでしょう。それは自分の作品の一覧表というか、自分の全作品が一堂に会する一冊でした。本の中で延々と実際の製塩工場の周辺に数限りなく建物を追加していきました。これが“ルドゥーのミュージアム”といわれる所以でしょう。今でいうと、ほとんどバーチャルの世界に入り込んでいたのかもしれません。空想の世界に、実際にあった建物をはめ込んでしまっているので、これは恐らく夢の構造と非常によく似ているのではないかと思ってしまいます。何故なら、夢は現実と非現実の大きく真ん中のところからできあがっているからです。そして、社会的に疎外された晩年に、それを逆にバネにして組み立てているところにルドゥーの凄さを感じます。  これからルドゥーの『・・・建築』の中で描かれている「ショーの理想都市」について具に見ていきたいと思います。ルドゥーは、自分の最も優れた作品の版画集の出版という目的をもっていたので、1789年(フランス革命の年)までに一冊の本を刊行するに足るだけの充分な数の版画作成を多くの彫り師に話をもちかけていました。しかし、ルドゥーの計画がかなり発展するのは1789年以降です。つまり、先に述べたように、ルドゥーが少しずつ自らの運命、建築家としての役割、建築家としての使命を考察するようになったのは、パリの55の市門の建築家としての不名誉によってショックを受け、彼が寵愛を受けていたアンシャン・レジームが崩壊し、最後に監獄に投獄されるという経験によってであります。こうした中で誕生したのが『・・・建築』なのです。ルドゥーが後世に託す遺産とみなしたこの刊行物は、あらゆる建築の文献の中でも極めて個性的であり、魅惑的な労作になりました。ここに新しい社会から追放される原因となった王の建築家という衣を脱ぎ捨てるルドゥーの姿があります。ここで彼は衣がえをします。自由のメッセージを伝えようとするが、それを理解しえなかったアンシャン・レジームによって懲罰を受けた、民衆を愛する芸術家という衣を着込むのです。ルドゥーは1806年に70歳で亡くなりますが、それまでの15年間の間、この『・・・建築』の著作に全エネルギーを費やすことになります。この本の中心は、実際に彼が建てたアルケスナン製塩工場を核にして、全く新しい空想の都市の設計を延々とやったものでした。こうして半円形の実在の建物にもう一つ半円を付け加えて円形にした「ショーの理想都市」ができあがったのです。 これからルドゥーの『・・・建築』の中で描かれている「ショーの理想都市」について具に見ていきたいと思います。ルドゥーは、自分の最も優れた作品の版画集の出版という目的をもっていたので、1789年(フランス革命の年)までに一冊の本を刊行するに足るだけの充分な数の版画作成を多くの彫り師に話をもちかけていました。しかし、ルドゥーの計画がかなり発展するのは1789年以降です。つまり、先に述べたように、ルドゥーが少しずつ自らの運命、建築家としての役割、建築家としての使命を考察するようになったのは、パリの55の市門の建築家としての不名誉によってショックを受け、彼が寵愛を受けていたアンシャン・レジームが崩壊し、最後に監獄に投獄されるという経験によってであります。こうした中で誕生したのが『・・・建築』なのです。ルドゥーが後世に託す遺産とみなしたこの刊行物は、あらゆる建築の文献の中でも極めて個性的であり、魅惑的な労作になりました。ここに新しい社会から追放される原因となった王の建築家という衣を脱ぎ捨てるルドゥーの姿があります。ここで彼は衣がえをします。自由のメッセージを伝えようとするが、それを理解しえなかったアンシャン・レジームによって懲罰を受けた、民衆を愛する芸術家という衣を着込むのです。ルドゥーは1806年に70歳で亡くなりますが、それまでの15年間の間、この『・・・建築』の著作に全エネルギーを費やすことになります。この本の中心は、実際に彼が建てたアルケスナン製塩工場を核にして、全く新しい空想の都市の設計を延々とやったものでした。こうして半円形の実在の建物にもう一つ半円を付け加えて円形にした「ショーの理想都市」ができあがったのです。次に、『・・・建築』の中に出てきます「ショーの理想都市」の建築群をご紹介いたしましょう(文中の写真とスライドの写真をご参照ください)。ギリシャ十字の形態をした、荘厳な行列によって近づいてゆく「教会堂  」、がやがやとした活気に満ちた「市場」、独立したパビリオンの「大砲鋳造工場」、簡潔な立方体であり、立方体の4つの正面は枠づけしている正方形に内接したいくつもの巨大な同心円によって形づくられている「樽職人の仕事場」、ベルサイユ宮殿の礼拝堂を思わせる「監督官の礼拝室」、新しい倫理に捧げられた「パナレテオン(美徳の館)」、新しい権利を示す「パシフェール(調停所)」、有徳の旅人を受け入れ、善人と悪人を区別することによって人類の改善に寄与しようとする「救護所」、ルソー主義の祀堂であり、会合もし 」、がやがやとした活気に満ちた「市場」、独立したパビリオンの「大砲鋳造工場」、簡潔な立方体であり、立方体の4つの正面は枠づけしている正方形に内接したいくつもの巨大な同心円によって形づくられている「樽職人の仕事場」、ベルサイユ宮殿の礼拝堂を思わせる「監督官の礼拝室」、新しい倫理に捧げられた「パナレテオン(美徳の館)」、新しい権利を示す「パシフェール(調停所)」、有徳の旅人を受け入れ、善人と悪人を区別することによって人類の改善に寄与しようとする「救護所」、ルソー主義の祀堂であり、会合もし くは同好会のための家の「団結の館」、正方形の内部に置かれたギリシャ十字形をしている「教育館」、情念の館あるいは不道徳の神殿と呼んでもよい「オイマケ(風俗の退廃を学ぶ場所)」、球戯や舞踏そしてチェスのための「遊興の館」、教会堂と繋がっている「4つの墓地」と「共同墓地」、四角い下部構造の中へ挿入された円堂の「牧師館」、丈の低い四角い壁に囲まれた円筒形の「公共浴場」、この町の最も豪華な住居のひとつと考えられる「会計係の家」、バロックのように見える「狩猟館」、新しい構成上の理想と抵触する古典主義とロマン主義を示す現代的な「監督官邸」、バロックの構成をほのかに思い起こさせる「職工の家々」、丸太で構成された独創的な森の番人たる「樵夫の家」、因襲的な形態から解き離れたいと願った円筒状の「公認仲買人の家」、1773年に認可された150の計画案のひとつの「邸宅」、非常に魅力的な「二人の美術商(芸術家及び服飾業者)の家」、立方体状の洗練された「4人の家族の家」等々、これらがルドゥーの大著『・・・建築』の中で夢想した「ショーの理想都市」の風景です。このテクスト全体は、ひとりの旅行者の報告として構想されているのも面白いところです。こうすることによってルドゥーは、読者に記述的な物語から抽象的な考察へと進むことができるようにしたのでしょう。ルドゥーはこの本の標語として、ホラティウスの“EXEGI MONUMENTUM(われは記念碑を建立せり)”という誇りに満ちた言葉を選んだのです。 くは同好会のための家の「団結の館」、正方形の内部に置かれたギリシャ十字形をしている「教育館」、情念の館あるいは不道徳の神殿と呼んでもよい「オイマケ(風俗の退廃を学ぶ場所)」、球戯や舞踏そしてチェスのための「遊興の館」、教会堂と繋がっている「4つの墓地」と「共同墓地」、四角い下部構造の中へ挿入された円堂の「牧師館」、丈の低い四角い壁に囲まれた円筒形の「公共浴場」、この町の最も豪華な住居のひとつと考えられる「会計係の家」、バロックのように見える「狩猟館」、新しい構成上の理想と抵触する古典主義とロマン主義を示す現代的な「監督官邸」、バロックの構成をほのかに思い起こさせる「職工の家々」、丸太で構成された独創的な森の番人たる「樵夫の家」、因襲的な形態から解き離れたいと願った円筒状の「公認仲買人の家」、1773年に認可された150の計画案のひとつの「邸宅」、非常に魅力的な「二人の美術商(芸術家及び服飾業者)の家」、立方体状の洗練された「4人の家族の家」等々、これらがルドゥーの大著『・・・建築』の中で夢想した「ショーの理想都市」の風景です。このテクスト全体は、ひとりの旅行者の報告として構想されているのも面白いところです。こうすることによってルドゥーは、読者に記述的な物語から抽象的な考察へと進むことができるようにしたのでしょう。ルドゥーはこの本の標語として、ホラティウスの“EXEGI MONUMENTUM(われは記念碑を建立せり)”という誇りに満ちた言葉を選んだのです。このようにして生存中の1804年に第1巻が出版されますが、ルド  ゥーは全4巻を考えていたようで、大量に刷らせていた版画を自分の弟子に全部預け、本にするように頼んで亡くなるのです。従って、「ルドゥーの製塩工場」には、実在の建築と、著作の両方があり、両者が重なってもいるのです。ただ、『・・・建築』の本になった時には、昔のものを別のバージョンで説明しています。ルドゥーは、あらゆるものを改めることを好んだようです。宗教上、社会上、そして経済上の論題が、この本の中で扱われています。ルドゥーは、いかなる問題にも関心を抱くことこそが、建築家の特権であると見做していました。幾人もの合理思想の持ち主たちからルドゥーは、批判的な特質を受け継ぎ、ルソーからは自然の新しい認識の仕方や、教育と肉体の鍛錬についての新しい思想の数々を引き出しました。空を背景にした美しい一本の老木は、ルドゥーにとっては一個の芸術作品に劣らず意味あるものだったのでしょう。ルドゥーの『・・・建 ゥーは全4巻を考えていたようで、大量に刷らせていた版画を自分の弟子に全部預け、本にするように頼んで亡くなるのです。従って、「ルドゥーの製塩工場」には、実在の建築と、著作の両方があり、両者が重なってもいるのです。ただ、『・・・建築』の本になった時には、昔のものを別のバージョンで説明しています。ルドゥーは、あらゆるものを改めることを好んだようです。宗教上、社会上、そして経済上の論題が、この本の中で扱われています。ルドゥーは、いかなる問題にも関心を抱くことこそが、建築家の特権であると見做していました。幾人もの合理思想の持ち主たちからルドゥーは、批判的な特質を受け継ぎ、ルソーからは自然の新しい認識の仕方や、教育と肉体の鍛錬についての新しい思想の数々を引き出しました。空を背景にした美しい一本の老木は、ルドゥーにとっては一個の芸術作品に劣らず意味あるものだったのでしょう。ルドゥーの『・・・建 築』は、様々な矛盾や疑念、そして将来への望みに満ちた一つの過渡期の所産であったと思います。やがてこの思想はロバート・オーウェンやフーリエ等、少しあとのユートピアを考えた人々の空想都市あるいはユートピア都市の具体的なプロジェクトに引き継がれていくことになります。ルドゥーを後の世の人は、「天才と燃えるような想像力を備えた人物」と評しました。 築』は、様々な矛盾や疑念、そして将来への望みに満ちた一つの過渡期の所産であったと思います。やがてこの思想はロバート・オーウェンやフーリエ等、少しあとのユートピアを考えた人々の空想都市あるいはユートピア都市の具体的なプロジェクトに引き継がれていくことになります。ルドゥーを後の世の人は、「天才と燃えるような想像力を備えた人物」と評しました。3回に亘って18世紀のフランスの建築家クロード・ニコラ・ルドゥーの「アルケスナン王立製塩工場」と「ショーの理想都市」を中心に紹介してまいりました。これまで辛抱強くご笑覧くださりありがとうございました。数奇な運命を辿った建築家ルドゥーについて少しでも興味をもっていただければうれしい限りです。 |
上の |