|
- シャトー訪問記25-  『ロマネ・コンティ・1935年』 |
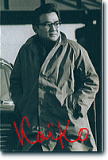 今回は<ロマネ・コンティ>に纏わる開高健(1930-1989)の短編の名作『ロマネ・コンティ・1935年』(1973年文學界)を紹介してまいります。 今回は<ロマネ・コンティ>に纏わる開高健(1930-1989)の短編の名作『ロマネ・コンティ・1935年』(1973年文學界)を紹介してまいります。ブルゴーニュやボルドーの人たち、そしてフランスの作家コレットやイギリスの作家ロアルド・ダールの抱く、燃え上がるようなワインに対する情熱と想いは、同じようにわが国の開高健の描く作中人物をも襲っています。この短編で描かれている<ロマネ・コンティ1935年>は、フィロキセラ禍から逃れたものの、残念ながら既に華を欠いており、様々な想像を生む原動力にはなり得なくなって  、背景に退いてしまっています。それに代わって、栄光と様々な想像を抱かせる酒効の頂点には、1966年の<ラ・ターシュ>が燦然と輝きわたっているのです。ブルゴーニュのグラン・ヴァン(銘醸ワイン)はこの作品が示しているように日本人にとってもエキゾティック且つエロティックであり、紛れもなく私たちを魅了し続けております。開高健はこの一本のロマネ・コンティから誠に驚嘆すべき物語を創造しました。そこではワインは、はかなくうつろう一人の女に昇華され、女は男に深くかかわって、人生のあらゆる陰翳のゆらめき、比類ない想念を引き出しています。まさに一人の愛飲家の男が、愛するワインへのオマージュを捧げているのです。 、背景に退いてしまっています。それに代わって、栄光と様々な想像を抱かせる酒効の頂点には、1966年の<ラ・ターシュ>が燦然と輝きわたっているのです。ブルゴーニュのグラン・ヴァン(銘醸ワイン)はこの作品が示しているように日本人にとってもエキゾティック且つエロティックであり、紛れもなく私たちを魅了し続けております。開高健はこの一本のロマネ・コンティから誠に驚嘆すべき物語を創造しました。そこではワインは、はかなくうつろう一人の女に昇華され、女は男に深くかかわって、人生のあらゆる陰翳のゆらめき、比類ない想念を引き出しています。まさに一人の愛飲家の男が、愛するワインへのオマージュを捧げているのです。それでは早速、氏の小説の饒舌ぶりに、暫し耳を傾けてみましょう。そしてワインに対する愛情込めた表現の見事さを感じとってみてください。 ― 冬の日曜日の午後遅く、鋼鉄とガラスで構築された都会の高層ビルの料理店で、41歳の小説家は40歳の重役氏と向かい合ってテーブルに座っている。どうやら重役氏は、うらやむべきフランス・ワインの旅を終え、彼の地で仕入れた珠玉とも宝石ともいうべき2本のグラン・ヴァンを携えて帰ってきたというのがこの物語の設定です。「若いのは6歳、古いのは37歳だ(1972年に飲んでいるので)。となりどうしの畑でとれたけれど、名がちがうから、異母兄弟というところかな。本物中の本物、ヴレ・ド・ヴレというやつさ」と重役氏は自慢する。 小説家の前に最初に現れたのは、<ラ・ターシュ>の1966年の一瓶である。彼は重役氏の話に耳を澄ませながら、  深紅に輝く若い酒の暗部に見とれたり、一口、二口すすって、その酒を噛んだりする。「いい酒だ。よく熟成している。肌理(きめ)がこまかく、すべすべしていて、くちびるや舌に羽毛のように乗ってくれる。ころがしても、漉しても、砕いても、崩れるところがない。最後に咽喉へごくりとやるときも、滴が崖をころがりおちる瞬間に見せるものをすかさず眺めようとするが、のびのびしていて、まったく乱れない。若くて、どこもかしこも張りきって、溌剌としているのに、艶やかな豊満がある。円熟しているのに清淡で爽やかである。つつましやかに微笑しつつ、ときどきそれと気づかずに奔放さを閃かすようでもある。咽喉へ送って消えてしまったあとでふとそれと気がつくような展開もある」と、一瓶の赤ワインを前に、愛飲家の小説家はこう独りごちる。 深紅に輝く若い酒の暗部に見とれたり、一口、二口すすって、その酒を噛んだりする。「いい酒だ。よく熟成している。肌理(きめ)がこまかく、すべすべしていて、くちびるや舌に羽毛のように乗ってくれる。ころがしても、漉しても、砕いても、崩れるところがない。最後に咽喉へごくりとやるときも、滴が崖をころがりおちる瞬間に見せるものをすかさず眺めようとするが、のびのびしていて、まったく乱れない。若くて、どこもかしこも張りきって、溌剌としているのに、艶やかな豊満がある。円熟しているのに清淡で爽やかである。つつましやかに微笑しつつ、ときどきそれと気づかずに奔放さを閃かすようでもある。咽喉へ送って消えてしまったあとでふとそれと気がつくような展開もある」と、一瓶の赤ワインを前に、愛飲家の小説家はこう独りごちる。そして、愈々<ロマネ・コンティ1935年>の登場となります。給仕が静かにテーブルに近づくと、白い籠をそっと、一本の髪をつまみとるような注意深さでとりあげる。籠の中には、濃緑で、口を赤い蠟で封をした、撫で肩の、古い瓶が一本、ひっそりと横たわっていた。黄ばんだレッテルに、ちょっと古めかしい斜体の、細かい筆記体で、Romanée Contiとあり、すみに小さくゴチック体で、Anée1935とあった。小説家はぼんやりと眼をあげ、「ロマネ・コンティだ」とつぶやいた。「本物。らしいな」と。重役氏はにがく笑い「1935年だぜ」といった。 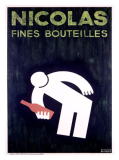 給仕の顔にひどい緊張があらわれた。手はしっかりと、けれど籠とのあいだに紙一枚のゆとりをあけて、つかんだ。瓶の口は猫の慎重さでグラスにしのびよった。瓶がゆさぶられないか、酒が混乱しないか、澱(おり)が舞い上がらないか、注がれているあいだずっと小説家は息をつめて眺めた。給仕は静かに、ゆっくりと、何度かにわけて二つのグラスに注ぎ、注ぎ終わった瞬間、ホッと音をたてて息を吐いた。終わった。儀式の第一は無事に終わった、最後の一滴はこぼれないで瓶へ戻され、澱も洩れないですんだようである。二つのグラスに歴史がなみなみと満たされ、二人の男はグラスごしに茫然としたまなざしをかわしあい、微笑しあった。偉大なワインを開ける時の給仕そして小説家のピーンと張りつめた雰囲気がわれわれ読者にも伝わってまいります。 小説家がつぶやいた、「飲んでいいのかしら?」と。重役氏が優しくいった。「どうぞ」と。そして小説家の<  ロマネ・コンティ1935年>の描写に入る。「暗く赤い。瑠璃の髄部のように閃きはなく、赤からはるかに進行して、褪せた暗褐に近いものとなっている。さきのラ・ターシュは無垢の白い膚から裂かれて朝の日光のなかへほとばしり出た血であったが、これは繃帯に沁みでて何日かたち、かたくなな顔つきでそこにしがみつき、もう何事も起こらなくなった古血である。澱んで腐りかかった潮のようなところもある。太陽はいよいよ冬の煙霧のなかで衰え、窓を蔽いかけている黄昏のすぐ背後には誤りようなく夜と名ざせるものが大きな姿をあらわしている。広い、無残な、ひからびた干潟のあちらこちらに赤や青の小さな閃光が音もなく炸裂しはじめている。光も、光めいたものも、何もこの室にはとどきそうにない。たとえ朝の日光があり、昼の日光があったとしても、このどろんとした暗褐の澱みには光輝も影も射すまいと思われる」と。 ロマネ・コンティ1935年>の描写に入る。「暗く赤い。瑠璃の髄部のように閃きはなく、赤からはるかに進行して、褪せた暗褐に近いものとなっている。さきのラ・ターシュは無垢の白い膚から裂かれて朝の日光のなかへほとばしり出た血であったが、これは繃帯に沁みでて何日かたち、かたくなな顔つきでそこにしがみつき、もう何事も起こらなくなった古血である。澱んで腐りかかった潮のようなところもある。太陽はいよいよ冬の煙霧のなかで衰え、窓を蔽いかけている黄昏のすぐ背後には誤りようなく夜と名ざせるものが大きな姿をあらわしている。広い、無残な、ひからびた干潟のあちらこちらに赤や青の小さな閃光が音もなく炸裂しはじめている。光も、光めいたものも、何もこの室にはとどきそうにない。たとえ朝の日光があり、昼の日光があったとしても、このどろんとした暗褐の澱みには光輝も影も射すまいと思われる」と。小説家はおずおずと体を起し「では」とつぶやいた。「やるか」と暗い果実をくちびるにはこんだ。くちびるから流れは口に入り、ゆっくりと噛み砕かれた。歯や、舌や、歯ぐきでそれはふるいにかけられた。分割されたり、こねまわされたり、ふたたび集められたりした。小説家は椅子のなかで耳をかたむけ、流れが舌のうえでいくつかの小流れと、滴と、塊になり、それぞれ離れあったり、集りあったりするのをじっと眺めた。くちびるに乗ったときの第一撃にすでに本質があらわに、そしてあわれに姿と顔を見せていて、瞬間、小説家は手ひどい墜落をおぼえた。けれど、それが枯淡であるのか、それとも枯淡に似たまったくべつのものであるのかの判断がつきかねたので、さらに二口、三口、それぞれのこだまが消えるのを待って飲みつづけなければならなかった。小説家は奪われるのを感じた。酒は力もなく、熱もなく、まろみを形だけでもよそおうとする気力すら喪っていた。ただ褪せて、水っぽく、萎びていた。衰退を訴えることすらしないで、消えていく。どの小流れも背を起こさなかったし、岸へあふれるということもなかった。滴の円周にも、中心にも、ただうつろさしかなく、球はどこを切っても破片でしかなかった。酒のミイラであった。こうして小説家は<ロマネ・コンティ1935年>という偉大なワインを無限の期待をもって口にした時、思いがけず手ひどい墜落の感覚を味わうことになったのです。 ここでさすがだと思ってしまうのは、その老いさらばえたロマネ・コンティの様を、中世最大のフランス  の詩人と讃えられているフランソワ・ヴィヨン(1431?-1463)の『老女の繰言(遺言の書)』の詩から引用して実に見事に表現していることです ―「生者必滅世のならひ 額の皺に灰色の髪 ふりさばき 眉毛さへ媼(おうな)さびしてむくつけく花の笑まひ秋波(めづかひ)の さしもに人を悩ませし眼もとの色香消え失せてとほき昔の花ならで 歪み曲れる鼻柱 萎(しを)れし耳に毛も生えて 色艶のなき顔色は死人にまがふ蒼白さ顎(あご)落ちて脣(くち)は梅干」、「人の色香の儚(はかな)さは 帰らぬ水の泡沫(あわ)とのみ 腕(かひな)ちぢまり掌(て)もしかみ せむしめかして屈む背に 胸乳(むなち)も骨と皮ばかり 腰とて同じさまなれば 男泣かせの何やらも名残とどめぬ太腿(ふともも)の細(ほつそ)りなつたる渋紙に 鹿子斑(かのこまだら)の汚点(しみ)さへあるえ」と。 の詩人と讃えられているフランソワ・ヴィヨン(1431?-1463)の『老女の繰言(遺言の書)』の詩から引用して実に見事に表現していることです ―「生者必滅世のならひ 額の皺に灰色の髪 ふりさばき 眉毛さへ媼(おうな)さびしてむくつけく花の笑まひ秋波(めづかひ)の さしもに人を悩ませし眼もとの色香消え失せてとほき昔の花ならで 歪み曲れる鼻柱 萎(しを)れし耳に毛も生えて 色艶のなき顔色は死人にまがふ蒼白さ顎(あご)落ちて脣(くち)は梅干」、「人の色香の儚(はかな)さは 帰らぬ水の泡沫(あわ)とのみ 腕(かひな)ちぢまり掌(て)もしかみ せむしめかして屈む背に 胸乳(むなち)も骨と皮ばかり 腰とて同じさまなれば 男泣かせの何やらも名残とどめぬ太腿(ふともも)の細(ほつそ)りなつたる渋紙に 鹿子斑(かのこまだら)の汚点(しみ)さへあるえ」と。偉大なワインや古いワインを飲んだ経験を豊富にもつ愛飲家にとっても、このようにワインばかりはどんな血筋やヴィンテージが良くても、残念ながら開けてみるまでは分からないのです。1930年代のワインは、良年の多い1920年代と1940年代に挟まれて若干影が薄かったようです。全般的に気候が不順だったのかもしれません。 小説家は「・・・フ  ランスの田舎の厚くて、深くて、冷暗な石室のすみでじっとよこたわったきりでいるしかないのに、旅をしすぎたのだ。・・・旅がこの酒には暴力だったのではあるまいか」と考えます。実際のところ、小説の中の<ロマネ・コンティ1935年>は旅をし過ぎているように思います。小説家がこのワインを飲んだ時(1972年)、ワインは37歳でした。いつ、ロマネ・コンティの酒蔵を出たのか分かりませんが、どうやらフランスからアメリカへ、そしてアメリカから日本へ旅をしているようです。その間、何人の人がこの一本のワインの所有者になったことでしょうか。このワインは、静かに横になって休む間もなく、寝る間もなく、オークションからオークションへと渡り歩いたのかもしれません。ロマネ・コンティという偉大なワインでありながら、このような環境下に置かれたワインを飲んだ重役氏と小説家の落胆振りも分かりますが、ワインの方も、これでは余りにも可哀そうな気がします。 ランスの田舎の厚くて、深くて、冷暗な石室のすみでじっとよこたわったきりでいるしかないのに、旅をしすぎたのだ。・・・旅がこの酒には暴力だったのではあるまいか」と考えます。実際のところ、小説の中の<ロマネ・コンティ1935年>は旅をし過ぎているように思います。小説家がこのワインを飲んだ時(1972年)、ワインは37歳でした。いつ、ロマネ・コンティの酒蔵を出たのか分かりませんが、どうやらフランスからアメリカへ、そしてアメリカから日本へ旅をしているようです。その間、何人の人がこの一本のワインの所有者になったことでしょうか。このワインは、静かに横になって休む間もなく、寝る間もなく、オークションからオークションへと渡り歩いたのかもしれません。ロマネ・コンティという偉大なワインでありながら、このような環境下に置かれたワインを飲んだ重役氏と小説家の落胆振りも分かりますが、ワインの方も、これでは余りにも可哀そうな気がします。「1935歳(このワインは葡萄だけをつくって1935年間になる土からできたゆえ、37歳というよりは1935歳のワインだという)から毎年一歳ずつ眠りつづけていた。歴史を肴に飲む酒だよ」、「けれど、死んだ」、「こんな酒を批評してはいけないな」、「そうかもしれない」、「批評できないんだよ」、「虚無に捧げる供物といった人もいる」、「名言だね」と、暫し語り合います。 そして、「終わった。もう飲めない。ひどい澱である」。グラスの内壁がこまかい粉でまっ黒になり、瓶にはまだ酒がのこっているけれど、ためしにちょっと斜めにしてからたててみると、どろどろにとけたタールのようなものがべっとりと瓶の内壁をつたって流れ落ちる。それを眺めているうちに小説家はとつぜんうたれた。「この酒は生きていたのだ。火のでるような修行をしていたのだ。1935歳になってから独房に入って37年になるが、けっして眠っていたのではないのだ。汗みどろになり、血を流し、呻きつづけてきたのだ。それでなくてこのおびただしい混沌の説明がつくだろうか。不幸への意志の分泌物ではないのだろうか。これもまた一つの劇ではなかったか?・・・」と。重役氏が「では、いくか」といった。小説家は「うん」といった。ここで、この物語は終わります。 ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ社の共同経営者の  オベール・ド・ヴィレーヌは、フランス語に翻訳された『ROMANÉE-CONTI1935(ロマネ・コンティ・1935年)』を絶賛しています。「このヴィンテージはもはや存在しないし、われわれも味わったことがありません。しかし、この小説を通して、完璧に、細部まで味わうことができました。ワインを味わう喜びを共有する最上のあり様が描かれていたから」と。 オベール・ド・ヴィレーヌは、フランス語に翻訳された『ROMANÉE-CONTI1935(ロマネ・コンティ・1935年)』を絶賛しています。「このヴィンテージはもはや存在しないし、われわれも味わったことがありません。しかし、この小説を通して、完璧に、細部まで味わうことができました。ワインを味わう喜びを共有する最上のあり様が描かれていたから」と。この小説に影響を受けた池田満寿夫は、初めてロマネ・コンティの存在を知り、『ロマネ・コンティ』(1989文學界)の題で自らも短編小説を発表します。そして小池真理子も『Vintage‘07』の「過ぎし者の標」(2007年刊)の中でロマネ・コンティに纏わる短編を書いておりますが、今回は紙数が尽きてしまいました。 ブルゴーニュを描写した長編の名作『化石』(1969年刊)を遺した井上靖は、死を前にして、「ブルゴーニュ地方に行きなさい。そうすれば本当の生きる歓びを味わえます」と語ったといいます。 |
上の |