|
懐かしのバー物語(3)

|
扉がゆっくりと開いた。バーの扉の開き方によって、常連の方か初めてか、女性か男性かが分かる。一瞬でどの席にご案内するかを判断するのがバーテンダーの最初の大切な仕事になる。 「こんばんは。いらっしゃいませ」。今宵は常連の皆様にいつものお席で、お好きなカクテルを傾けながら、ドライ・マティーニに纏わるいくつかの物語をお聞きいただければと思います。 第一話:カクテルとブルースの街、ニューヨークに夜の明かりが灯り出す頃、  ここ「JAY'S BAR(ジェイズ・バー)」は店を開ける。ダウン・タウンの場末にあるこの店では、毎夜、カクテルを傾けながらニューヨーカーが語る言葉から、小さなドラマが生まれては消えていく・・・。 ここ「JAY'S BAR(ジェイズ・バー)」は店を開ける。ダウン・タウンの場末にあるこの店では、毎夜、カクテルを傾けながらニューヨーカーが語る言葉から、小さなドラマが生まれては消えていく・・・。
「ジェイ(JAY'S BARのオーナー兼バーテンダー)、ドライ・マティーニのお代わり、超ドライでね」。前からサラは美人だと思っていたが、その夜、体にぴったりとしたロングの黒いドレスを着た彼女は、また一段と綺麗だった。かすかにほつれたブロンドの髪、もうこれ以上は塗りようのない、めいっぱいの化粧、そしてぬけぬけと、彼女の40年間を、まるで他人(ひと)ごとのように語る、いくつだか見当のつかない青い瞳、そんな彼女が美しかった。今宵、僕が改めてそう感じたのは、初夏の夜のせいかもしれないな。時間が相当遅かったせいもあるかもしれないけどね・・・。 彼女はただ、空になったポルト・グラスを手の中で回したり、戻したりしている。「ジェイ、今までのと同じグラスよ。替えないでね。私、かつぐ方なの・・・」。「OK・・・」、つぶやくようにそう答えた。まさか、この僕がサラに向かって、もう飲むのはやめろなんて言える柄かい?それで、のらりくらりと、タンブラーの中でも一番背の高いものを選びだし、氷を3個放り込んだ。「時間が掛かるものほど、余計に急いじゃだめなのよ、ジェイ。ゆっくりつくってね」、これは以前サラが僕に教えてくれたことのひとつだ。 ご希望通り、ジンを定量よりたっぷりめに注ぐ。  アンゴスチュラ1ダッシュ(ひとふり、約1ml)、ベルモット・フランセ・ドライを1ダッシュ入れ、軽くステア(強くかき混ぜない。これはドライをつくる場合には、やっちゃだめなんだ)。そしてタンブラーの中身を、サラのポルト・グラスに注いだ。 アンゴスチュラ1ダッシュ(ひとふり、約1ml)、ベルモット・フランセ・ドライを1ダッシュ入れ、軽くステア(強くかき混ぜない。これはドライをつくる場合には、やっちゃだめなんだ)。そしてタンブラーの中身を、サラのポルト・グラスに注いだ。彼女の背後では、アルシー(JAY'S BARのピアノ奏者兼歌手)のピアノが古いブルースの一曲を流しながら、今夜の最後の客たちを、一人、そしてまた一人と店から立ち去らせていた。僕なんかこいつを聴くと、いつもとことん落ち込んでしまう・・・。 さてと続きだ。グラスの上で、クオーター玉くらいのレモンの皮を搾り、香りが十分浸透したって分かる、油分の仄かな痕跡が、カクテルの表面に現れるのを見届ける。それから手をゆっくりとグリーン・オリーヴの方へ伸ばし、真珠一粒ずつ摘んでは首飾りでもつくっているような仕草で摘むと、グラスの底に沈めた。そっとサラの前にドライ・マティーニを差し出した。 彼女が微笑む。ぼんやりした眼差し、好きでもない男と愛を交した後のような目・・・そして呟いた。「ジェイ、あなたにドライ・マティーニを注文する人間がいたら、よく観察するのよ。多分あなたの手に目を釘付けにしたまま黙りこくって、身動きひとつしないはずよ。それとね、何故ドライ・マティーニを注文したのか分かる・・・?それはねえ、そうやってあなたの仕草を目で飲んでいる間はね、とうの昔に終わってしまった自分の人生のことを、ほんの少しの間だけ、悔やまなくてすむからなのよ・・・」と。 第二話:先の店よりもう少し上等なニューヨークにあるバー(名前は失念)での話。  上流階級のようなクイーンズ・イングリッシュが響いた。老紳士はカウンターに手の切れそうな100ドルの新札を置いた。「如何いたしましょう」。「ドライ・マティーニをください。ニューヨークで一番ドライなマティーニを」。二人の間に決闘前のガンマンのような緊張感が走った。僕はミキシング・グラスを取り出すと、たっぷりの氷とミネラル・ウオーターを入れ、1分間で300回ほど、バー・スプーンを回した。氷がぶつかる音は一切出さない完璧なステアだ。ミキシング・グラスの周りに真っ白い霜が張り付いたのを感じると、中身を捨てて、新たに氷を満たした。その中に少量のベルモットを注ぐと、氷にくぐらすように、素早く、最後の一滴まで捨て切った。微かなベルモットの香りが、纏わりついたミキシング・グラスにドライ・ジンを優しく流し込むと、今度は一切混ぜずにカクテル・グラスに注いだ。比重が違う。上から覗き込んでみると、きりっと冷えた蒸留酒のジンの中にマーブル状に醸造酒のベルモットが泳いでいるのが見えた。 上流階級のようなクイーンズ・イングリッシュが響いた。老紳士はカウンターに手の切れそうな100ドルの新札を置いた。「如何いたしましょう」。「ドライ・マティーニをください。ニューヨークで一番ドライなマティーニを」。二人の間に決闘前のガンマンのような緊張感が走った。僕はミキシング・グラスを取り出すと、たっぷりの氷とミネラル・ウオーターを入れ、1分間で300回ほど、バー・スプーンを回した。氷がぶつかる音は一切出さない完璧なステアだ。ミキシング・グラスの周りに真っ白い霜が張り付いたのを感じると、中身を捨てて、新たに氷を満たした。その中に少量のベルモットを注ぐと、氷にくぐらすように、素早く、最後の一滴まで捨て切った。微かなベルモットの香りが、纏わりついたミキシング・グラスにドライ・ジンを優しく流し込むと、今度は一切混ぜずにカクテル・グラスに注いだ。比重が違う。上から覗き込んでみると、きりっと冷えた蒸留酒のジンの中にマーブル状に醸造酒のベルモットが泳いでいるのが見えた。
「リンス・マティーニ。これ以上ドライなマティーニはチャーチルしかつくれない」。手馴れた手つきで、マティーニを口に運ぶと、老紳士は満足気に頷いた。「素晴らしいマティーニだ」、「チャーチルは残念なことをした。ジンとベルモットを混ぜることを諦めてしまったのだから」(註)因みに、英国元首相チャーチルのマティーニの飲み方とは、ジンをストレートで飲む。それでドライ・ベルモットの栓だけ・・・においを嗅ぐ。否、ドライ・ベルモットの瓶を一瞥するだけとの説もある。 第三話:今度は趣向を変えて文学作品、イヴリン・ウォー著『ブライズヘッドふたたび(Brideshead Revisited)』に登場するマティーニの話。 著者イヴリン・ウォーは、イギリスのカトリックの作家で、しばしばグレアム・グリーンと並べて論じられる。しかし、どうも日本での人気は、圧倒的にグレアム・グリーンの方に軍配が上がる。  ひょっとすると、英文学を専攻する者でもなければ知らないかも。それも無理のない話で、ウォーの小説には、イギリスの社会 ― それも上流社会の風俗を、風刺で描いたものが多く、且つ、カトリック精神を盛り込んであるので、日本の読者には必ずしも舌触りのよい小説とは思えないからだ。それでも、僕はイヴリン・ウォーが好きである。それは『ブライズヘッドふたたび』が、全篇を通じて殆ど間断なくといってよいくらいにワインをはじめ酒の話が出てくるからである。それもその筈、イヴリンの実兄がワインの名著『In Praise of Wine(邦題:わいん ― 世界の酒遍歴)』の著者であるアレック・ウォーであるからかもしれない。 ひょっとすると、英文学を専攻する者でもなければ知らないかも。それも無理のない話で、ウォーの小説には、イギリスの社会 ― それも上流社会の風俗を、風刺で描いたものが多く、且つ、カトリック精神を盛り込んであるので、日本の読者には必ずしも舌触りのよい小説とは思えないからだ。それでも、僕はイヴリン・ウォーが好きである。それは『ブライズヘッドふたたび』が、全篇を通じて殆ど間断なくといってよいくらいにワインをはじめ酒の話が出てくるからである。それもその筈、イヴリンの実兄がワインの名著『In Praise of Wine(邦題:わいん ― 世界の酒遍歴)』の著者であるアレック・ウォーであるからかもしれない。
イヴリン・ウォーの代表作として、『ブライズヘッドふたたび』を推すことに異論はあるまい。しかしこの小説にも、イギリス独特の大学生活、貴族の家庭における親子関係、信仰による愛の断念など、日本人の生活感情にダイレクトに溶け込んでこない場面が多い。だが、こと酒に関する限り、この小説には実に多くの話題となるべきパッセージがちりばめられている。 この小説の内容を一言でいうならば、一人のイギリス知識階級の人間の精神遍歴をタテ糸に、彼の学友が育った貴族家庭の時代的変遷をヨコ糸にして綴ったロマンである。小説の主人公「私」は、名前をチャールズ・ライダーといい、小説に登場する頃は、まだ19歳。オクスフォード大学の学生で、毎日楽しい生活を送っている。時は1920年代。「私」の学友に、とびきりの美貌をもつ貴族の青年、セバスチャン・フライトがいた。そしてオックスフォード大学時代、「私」が友達づきあいをしたもう一人の人物に、アントニー・ブランシュという耽美主義的な学生がいた。これらの友達との付き合いの中で、いろいろな酒が次々に登場する。カクテルのアレキサンドリア、シャルトリューズ、シャンパン、ラム、ポート・ワイン、シェリー、コニャック等々。中には銘醸ワインのモンラシェをはじめシャンベルタン・クロ・ド・ベーズや貴腐ワインのシャトー・ペラゲイまでも。 セバスチャンは、放蕩無頼、泥酔癖のある学生として、オックスフォードの教授預かりの身となるが、監視されることに非人間的な屈辱を感じ、ある日突然失踪する。セバスチャンの妹ジュリアのフィアンセ、レックス・モトラム(カナダ生まれの成り金、政界への野望あり)が、当時パリにいた「私」のところにセバスチャンが来てはしないかと訪ねてくる。このレックスは、やがて希望通り、セバスチャンの妹ジュリアと結婚し、貴族の一員となるが、その結婚生活は決して幸福ではなかった。 前置きが大分長くなったので先を急ごう。それから何年かの歳月が流れる。「私」はアメリカでの絵の仕事からイギリスに帰る船で、偶然、レックスの妻となったジュリアに逢い、忽ち大人の恋に陥り、ロンドンやブライズヘッドで逢瀬を重ねるようになる。その逢引のある日、二人が汽車の食堂車で向かい合って会話をしている。その場のカクテルの描写は、この小説の中で最も印象的な場面である。  「暗闇の中を汽車が走って行くのに連れて、卓上のナイフやフォークがかち合って音を立てていた。グラスに注がれたジンとベルモットの小さな円が伸びて楕円になり、また縮まり、縁まで来てまた戻り、決してこぼれはしなくて、私はその日一日から刻々と遠ざかりつつあった」と。お互いに家庭をもつ身の男女が、その枠を乗り越えて二人だけの時間をもつ。“恍惚と不安”の錯綜した心理を隈なく表現した文章として強烈な印象を与える。二人の目の前にあるカクテルは恐らくマティーニだと思われる。それがドライかどうかは分からないが・・・。きりっと冷えた飛び切りのドライ・マティーニを飲みながら、暫し文章の余韻に浸りたい気分になる場面だ。 第四話:最後のお話は、アーネスト・ヘミングウェイの小説『河を渡って木立の中へ(Across the River and into the Trees)』から。 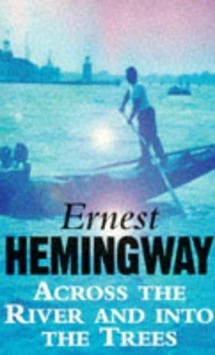 アメリカの現代作家の中で、ヘミングウェイほど、小説の中に酒をふんだんに登場させる作家はいないのではなかろうか。これはヘミングウェイ自身に美食趣味があったからで、パリ在住時代の追想記『移動祝祭日』(vol.85)を読めば一目瞭然である。処女作『日はまた昇る』は全篇、酒の匂いが立ちこめているような小説で、登場人物たちは、四六時中酒を飲まないではいられないみたいだ。 アメリカの現代作家の中で、ヘミングウェイほど、小説の中に酒をふんだんに登場させる作家はいないのではなかろうか。これはヘミングウェイ自身に美食趣味があったからで、パリ在住時代の追想記『移動祝祭日』(vol.85)を読めば一目瞭然である。処女作『日はまた昇る』は全篇、酒の匂いが立ちこめているような小説で、登場人物たちは、四六時中酒を飲まないではいられないみたいだ。
さて、ヘミングウェイの後期の作品となる『河を渡って木立の中へ』でも、酒が篇中で随所に効果的に使われていることは、先の二作に劣らない。この小説では、舞台を北イタリアにとり、第二次世界大戦と恋愛を描いている。主人公はアメリカ陸軍大佐リチャード・カントウエル、51歳。第二次世界大戦後、イタリアのトリエステで駐留軍人として軍務に服し、週末になると、車を駆ってヴェニスに遊びに行くが、そこのバーで知り合ったイタリア人に、ヴェニスの伯爵家の令嬢レナータを紹介され、僅か19歳という自分の娘のような令嬢と、たちまち恋に陥ってしまう。逢引きの間も、職業軍人として育った大佐は、戦争の回顧談をレナータに頻りに話す。というより、武骨な彼は、それぐらいしか話のネタがないのだ。 小説の先を急ごう。大佐は、駐車場のバーに入り、顔馴染みのバーテンダーにネグローニというカクテルをつくってもらう。カクテルを一杯飲んだ大佐は、船着場から小舟でヴェニスに渡り、今日宿泊すべき定宿ホテルに直行する。大佐の小舟は、ホテルに横付けになる。大佐は、このホテルに着くや、またも早速バーに入る。そしてマティーニを注文する。「なるべくさっぱりした味のマティーニをこしらえてくれ」、「ダブルだ」。さっぱりした味のマティーニとはベルモットの量を少なくした、辛口のマティーニのこと。原文は、a very dry martiniとある。辛口好みのアメリカ人らしい注文だ。更に「ドライ・マティーニをもう一杯くれ。うんと辛口のやつをな、2倍も辛口のやつを」。アメリカ人の大佐は、マティーニをうんと辛口につくったものでなければ、満足できないらしい。殆ど、ジンだけのような強烈なマティーニを飲みたいのだ。  こうしてホテルのバーで一息ついた後、大佐は昔馴染みの酒場「HARRY'S BAR(ハリーズ・バー)」に出掛ける。暫くすると大佐の恋人レナータが店に駆けつける。レナータは、この店に来るのが今日は二度目である。一度来た時は早過ぎて、まだ大佐が来そうもないので、出直したのである。顔馴染みの友人が去り、二人だけになると、大佐は又もや好物のカクテルを注文する。「ドライのマティーニを二杯」と大佐は言った。「モンゴメリー将軍だよ。15対1というやつさ(Montgomerys.Fifteen to one)」。この15対1という数字は、ジンとベルモットの比率をいっているのである。この処方でつくると、ベルモットはほんの僅かを滴らす程度になり、超辛口に仕上がる。アフリカ戦線の連合軍総司令官モンゴメリー将軍がドイツ軍との戦力比が15対1以上にならないと決して攻撃を開始しなかったことに引っ掛けている。  ところで、この小説が出版されたのは、1950年で、その当時、イタリアで辛口のマティーニを好むのはアメリカ人ぐらいのものだったようだ。 ところで、この小説が出版されたのは、1950年で、その当時、イタリアで辛口のマティーニを好むのはアメリカ人ぐらいのものだったようだ。
だから、伯爵令嬢レナータも次のようにいうわけである。「もう一杯マティーニを飲みましょうよ」と娘は言った。「あなたと逢うまで、わたし、マティーニを飲んだことがなかったのよ」、「知ってるよ。だが、君は、それにしてはよく飲む」。よく飲むのは、勿論、マティーニが大佐の好物だからに他ならない。ここは身も心も大佐に捧げている女性のいじらしい心境がある。ヘミングウェイは、そうした心理を一切地の文で語らず、こうした会話だけで小説を展開していくが、伯爵令嬢に酒に対する好みの変化を語らせるだけで、彼女の胸のうちを雄弁に読者に伝えるのである。ヘミングウェイの真骨頂だ。 ということで、ニューヨークにある2つの「懐かしのバー」の想い出のシーンと昔々読んだ2つの文学作品に登場するマティーニのお話について少し紙数を超えて綴らせていただきました。それでも尻切れとんぼになってしまいましたが、取敢えずここでペンを措くことにします。  |