|
シャトー訪問記(その34)

<シャトー・ランシュ・バージュ(Château Lynch Bages)> |
私たちはシャトー・コス・デストゥルネルを後にして、次なる訪問地ポイヤック村のシャトー・ランシュ・バージュへ向かいます。途中、偉大なシャトー・ラフィット・ロートシルトへ立ち寄ることにしました。
 今回はシャトーが工事中のため見学できずに残念でしたが、写真だけでも撮ろうと車を止めました。池を前にして瀟洒なシャトーが辺りを睥睨するように建っています。このシャトーが言わずと知れた、あの威厳ある1855年格付けの第1級のトップを飾っているラフィットなのです(Premier des Premiers!1級の中の1級!)。 今回はシャトーが工事中のため見学できずに残念でしたが、写真だけでも撮ろうと車を止めました。池を前にして瀟洒なシャトーが辺りを睥睨するように建っています。このシャトーが言わずと知れた、あの威厳ある1855年格付けの第1級のトップを飾っているラフィットなのです(Premier des Premiers!1級の中の1級!)。
およそこの世の最高をワインに求めるとしたら、衆目の一致するところは、やはりボルドーのシャトー・ラフィットか、ブルゴーニュのロマネ・コンティのどちらかに落ち着くのではないでしょうか。でも、この2つの葡萄園には歴史上の因縁があるのです。ルイ15世の時代に入って、王の寵妾マダム・ポンパドゥールとコンティ大公がフランスの最高の葡萄園を手に入れようと猛烈な闘いを演じることになります(vol.93をご参照ください)。この争いは結局、大公の勝ちになり、  これを手に入れ、誇らしげにロマネ・コンティと命名してワインの歴史に燦然と名を残すことになりました。だが、後にそれが政治的失脚という高い代償を払わされることになります。そして、ロマネ・コンティを手に入れそこなって、心穏やかならぬマダム・ポンパドゥールに、これこそがフランス最高のワインですぞ、とラフィットを奨めたのがリシュリュー男爵であったという、ラフィット出現に纏わるエピソードがまことしやかに伝わっております。事の真相は兎も角として、この頃から、ロマネ・コンティへの対抗意識からか、それともラフィットの良さに惚れ込んだのか動機は定かでないとしても、マダム・ポンパドゥールはその華麗な宮廷晩餐会の食卓にラフィットを欠かさなかったのは確かのようです。かくして、ラフィットを飲むことはフランス貴族のステイタス・シンボルになり、一躍ラフィットはワイン界のスターダムにのし上がっていったのであります。 これを手に入れ、誇らしげにロマネ・コンティと命名してワインの歴史に燦然と名を残すことになりました。だが、後にそれが政治的失脚という高い代償を払わされることになります。そして、ロマネ・コンティを手に入れそこなって、心穏やかならぬマダム・ポンパドゥールに、これこそがフランス最高のワインですぞ、とラフィットを奨めたのがリシュリュー男爵であったという、ラフィット出現に纏わるエピソードがまことしやかに伝わっております。事の真相は兎も角として、この頃から、ロマネ・コンティへの対抗意識からか、それともラフィットの良さに惚れ込んだのか動機は定かでないとしても、マダム・ポンパドゥールはその華麗な宮廷晩餐会の食卓にラフィットを欠かさなかったのは確かのようです。かくして、ラフィットを飲むことはフランス貴族のステイタス・シンボルになり、一躍ラフィットはワイン界のスターダムにのし上がっていったのであります。
偉大なるシャトー・ラフィット・ロートシルトに敬意を表し、歴史上のエピソードの一端をご紹介しましたが、先を急ぎシャトー・ランシュ・バージュに向かうことにします。ここは同行したキロスさんがボルドー大学に在学中に1年間ほど働いたことがあるとのことで、全てアレンジをしてくれました。午後5時からという遅い訪問を許可していただいたのも彼のお蔭でしょう。カズ家の結婚式に出席し、3代目オーナーのジャン・ミシェル・カズとも親しく何度かお会いしているそうです。キロスさんはボルドー大学在学中にいろいろな経験をされており、今回宿泊したボルドー随一の老舗ホテル「ブルディガラ」(5つ星)でも働いていたことがあり、  支配人と親しいこともあって私たちのステキな部屋も格安で泊めて貰えました。ホテルのスタッフの皆様もキロスさんを懐かしがって親しく話しかけてきます。彼は友人宅に泊まっていたのですが、ホテルで私たちと一緒にとった朝食は全て無料でした。フランスでもこういう粋なサービスがあるのだなと妙に感心したものです。そういえば2日目にはわざわざオーナー自らが挨拶に見えられ恐縮してしまいました。オーナーにリュル・サリュース伯爵から歓待を受けた話をすると大層吃驚され、最近の伯爵の消息はボルドーでも知る人は少なくなくなっているので、それはすばらしい経験をなさいましたねと感心されておりました。 支配人と親しいこともあって私たちのステキな部屋も格安で泊めて貰えました。ホテルのスタッフの皆様もキロスさんを懐かしがって親しく話しかけてきます。彼は友人宅に泊まっていたのですが、ホテルで私たちと一緒にとった朝食は全て無料でした。フランスでもこういう粋なサービスがあるのだなと妙に感心したものです。そういえば2日目にはわざわざオーナー自らが挨拶に見えられ恐縮してしまいました。オーナーにリュル・サリュース伯爵から歓待を受けた話をすると大層吃驚され、最近の伯爵の消息はボルドーでも知る人は少なくなくなっているので、それはすばらしい経験をなさいましたねと感心されておりました。
また横道に逸れてしまいました。シャトー・ランシュ・バージュに集中します。少し早目に着いたので、寒風吹きすさぶ中を最近シャトー周辺にできたという“バージュ・ヴィレッジ”を訪ねてみました。すると、洒落たビストロをはじめ地元の肉屋さん、パン屋さん、ブティック、そして子供たちの遊び場まで整備された、ひとつの小さな町のようになっており吃驚してしまいました。以前訪れた時とは全く違う様相を呈していました。シャトーの見学に訪れた観光客がワインと共にここでより楽しめるためのエリアをつくり上げたそうで、良いワインはその土地からの恵み、シャトーだけが潤っていても土地の恵みに感謝していることにはならない、との3代目オーナーのサービス精神から生まれたものらしい。でも正直のところ、私は葡萄畑に囲まれた中にある以前の静かなシャトーの佇まいの方が好きです。 ここでシャトー・ランシュ・バージュの簡単な歴史を振り返ってみたいと思います。ここは16世紀まで遡れる由緒あるシャトーですが、18世紀の初めにアイルランドからメドックに移住してきたトーマス・ランシュ家に、シャトーの所有者の娘さんが嫁いでからランシュ家のものとなりました。子息はフランス革命直後にはボルドー市長を務め、伯爵の爵位まで授かっています。ランシュ(Lynch)というフランス語では聞き慣れない名前は、アイルランドに由来(Lynch=リンチ(私刑)というおかしな名前)していますが、バージュ(Bages)の方はここにバージュの集落があるからです。同家はシャトーにランシュの名を残しましたが、19世紀になるとシャトーを手放し、その後何人かの手を経て1939年にジャン・シャルル・カズが正式にシャトー・ランシュ・バージュを取得し、ここからカズ家の物語が始まります。シャトーはその後、息子のアンドレ、次いで孫のジャン・ミシェルに継承され、現在は同名のひ孫のジャン・シャルルが4代目を継いでいます。このカズ家はなかなかの実力者揃いで2代目アンドレはポイヤック市長を長く務め、メドックきっての名士になっています。社交的な3代目ジャン・ミシェルは、メドック・グラーヴ・ポンタン騎士団の団長となって、ボルドーのワイン大使として世界中で活躍をしておりました。  そして、シラク大統領の時代に、フランスの地位と文化に多大な貢献をしていることから栄えあるレジオン・ドヌール勲章を受章しました。 そして、シラク大統領の時代に、フランスの地位と文化に多大な貢献をしていることから栄えあるレジオン・ドヌール勲章を受章しました。
さて、シャトー・ランシュ・バージュは1855年格付けの第5級ですが、歴代オーナーの弛まぬ努力により今やその品質と評判は高まる一方で、現在は第2級の実力をもっているとさえ高く評価されています。その世界的名声を得るまでに急成長させた立役者は、やはり何といっても3代目のジャン・ミシェル・カズでしょう。今回は残念ながらお会いすることができませんでした。 シャトーではお二人のお嬢さんが付っきりで詳しく案内をしてくださいました。ところが案内の途中で突然シャトー内が停電となり真っ暗闇になってしまいました。今まで何度となくシャトーを訪問してきましたが、このような事態に出くわしたのは初めてのことです。ポイヤック村の何処かで木製の電柱に車が激突して村全体が停電になってしまったらしいのです。恐らく運転者はワインを飲んで酔っ払っていたのでしょうか。ワインの温度管理の方は緊急時でも自家発電でコンピュータが作動しているので大丈夫とのこと。以降はお嬢さんが蝋燭ならぬ懐中電灯を片手に案内してくれたのですが、それでなくとも寒い日でしたので、醸造所内は零度を遥かに下回っており、身体は冷え切って正直説明を聞いているどころではありませんでした。でも、二人のお嬢さんはさすがプロで、  平然と案内をしていたのはさすがです。後日、友からそれは正に昔のシャトーそのままを見学させてもらったようなもので、貴重な経験しましたねと冷やかされました。私たちは震えながらもシャトーの歴史から現代の製法まで事細かな説明を受けました。やはり超近代化されたシャトー・コス・デストゥルネルの壮観な発酵室を見た直後なので見劣りはしますが、ここも今年から3年間かけて大改修を行うそうで、新型の除梗機の導入や発酵槽を小さなものにして現在の42基から85基に増やし、全てステンレス・タンクにするそうです。ステンレス・タンクはコンピューター・コントロールという面では最も信頼できるシステムなのでしょうか。時代の趨勢なのでありましょう。樽貯蔵庫も大幅に拡大し、土質が脆いため、カーヴ(地下貯蔵庫)はつくらずに全てシェ(地上貯蔵庫)になるようです。 平然と案内をしていたのはさすがです。後日、友からそれは正に昔のシャトーそのままを見学させてもらったようなもので、貴重な経験しましたねと冷やかされました。私たちは震えながらもシャトーの歴史から現代の製法まで事細かな説明を受けました。やはり超近代化されたシャトー・コス・デストゥルネルの壮観な発酵室を見た直後なので見劣りはしますが、ここも今年から3年間かけて大改修を行うそうで、新型の除梗機の導入や発酵槽を小さなものにして現在の42基から85基に増やし、全てステンレス・タンクにするそうです。ステンレス・タンクはコンピューター・コントロールという面では最も信頼できるシステムなのでしょうか。時代の趨勢なのでありましょう。樽貯蔵庫も大幅に拡大し、土質が脆いため、カーヴ(地下貯蔵庫)はつくらずに全てシェ(地上貯蔵庫)になるようです。
 完成した暁にはここも超近代化されたシャトーへと生まれ変わることでしょう。ただ、このシャトーの2階には1850年代につくられた醸造所をそのままの形で残し、古い醸造設備や道具を展示したギャラリーになっており、醸造の歴史を学ぶには貴重な資料が大切に保存されております。このギャラリーだけは改造後も残して欲しいものです。 完成した暁にはここも超近代化されたシャトーへと生まれ変わることでしょう。ただ、このシャトーの2階には1850年代につくられた醸造所をそのままの形で残し、古い醸造設備や道具を展示したギャラリーになっており、醸造の歴史を学ぶには貴重な資料が大切に保存されております。このギャラリーだけは改造後も残して欲しいものです。
寒い中で一通りの説明を受けた後に、少し夕陽の射すテイスティング・ルームで、<シャトー・ランシュ・バージュ2009年>と、サン・テステーフに同家が所有する<シャトー・レ・オルム・ド・ペズ2009年>を比較テイスティングしながらやっと一息つきました。2009年というビッグ・ヴィンテージのワインはすばらしく、特に、アルコール度数(13.5%)、ポリフェノール濃度共に史上最も高かったといわれるこの年の<ランシュ・バージュ>はゴージャスで、香りはイチジクや黒系果実の濃厚で甘い香りが漂い、西洋杉や樽のロースト香のニュアンスも感じます。タンニンは堅牢というよりか馴染み易く酸味は控えめでした。今後30年程は楽しめそうです。 今回の訪問は停電という思わぬ事態が発生しましたが、友が言うようにこれはこれで貴重な経験だったのかもしれません。 最後にカズ家のホスピタリティー・ビジネスのひとつである、「シャトー・コルディヤン・バージュ」をご紹介しましょう(vol.29をご参照ください)。シャトー・ランシュ・バージュの集落を街道に向かって下った直ぐのところにあります。3代目のジャン・ミシェル・カズが17世紀の優美な古城を買い取ってルレ・エ・シャトー(Relais et Châteaux)にしました。質の高いすばらしい料理と心のこもったサービスと洗練された魅力あるスペース、落着きやリラックスできる場所を保証する、  まさにワインの里に相応しいお奨めの宿です。おまけに感動的なワインにも巡り合えます。ここは周りをぐるりと葡萄畑に囲まれており、ワイン好きにはたまらない場所です。窓からは美しい庭園となだらかな葡萄畑が見え、その眺めはすばらしくレストランからも形を変えて広がっています。1996年の晩秋に初めて訪れた時の感動が鮮やかに蘇ります。レストランでは当時も今もミシュラン2つ星を誇る本格的なフランス料理を楽しめます。このレストランで当時の総料理長であった有名なティエリー・マルクスのつくる美味なる料理に夫々ワインをマリアージュさせるというフルコース料理、「LA CUISINE DU MARCHE」を堪能しました。メインの料理とワインは、骨髄をのせた鹿の背肉のココット煮とシャトー・ピション・ロングヴィル・バロン1985年でした。そのマリアージュの妙味に感激したことを憶えています。それからというもの、私はすっかりここが気に入ってメドックを訪れる度に滞在しました。今思えば随分と贅沢をしていたものです。初めて訪れた時に、このホテルのシェフ・ソムリエとして活躍していたのが何と30歳にも満たない北海道出身の日本の若者であることに吃驚してしまいました。彼のワインについての優れた知識をカズ家でも十分認めていたのでしょう。だから本場ポイヤックの2つ星レストランで、フランス人のソムリエを従えて堂々とシェフ・ソムリエの地位を勝ち取ることができたのでありましょう。彼からワインのことについていろいろと教えていただきました。カーヴにあったメドックの銘醸ワインを原価で分けて貰い日本へ送ったこともありました。ある時、彼はいつかメドックで葡萄畑を買って、自分でワインをつくってみたいと夢を語ってくれました。大きな夢があって羨ましいなと思ったものです。当時ボルドーで最も有名な日本人の一人だったのかもしれません。現在は独立してパリでビストロを開いていると仄聞しております。彼のことだからパリでも思う存分に力を発揮し大活躍されていることでしょう。近い将来またメドックに戻ってきて、長年の夢を実現して欲しいものです。 まさにワインの里に相応しいお奨めの宿です。おまけに感動的なワインにも巡り合えます。ここは周りをぐるりと葡萄畑に囲まれており、ワイン好きにはたまらない場所です。窓からは美しい庭園となだらかな葡萄畑が見え、その眺めはすばらしくレストランからも形を変えて広がっています。1996年の晩秋に初めて訪れた時の感動が鮮やかに蘇ります。レストランでは当時も今もミシュラン2つ星を誇る本格的なフランス料理を楽しめます。このレストランで当時の総料理長であった有名なティエリー・マルクスのつくる美味なる料理に夫々ワインをマリアージュさせるというフルコース料理、「LA CUISINE DU MARCHE」を堪能しました。メインの料理とワインは、骨髄をのせた鹿の背肉のココット煮とシャトー・ピション・ロングヴィル・バロン1985年でした。そのマリアージュの妙味に感激したことを憶えています。それからというもの、私はすっかりここが気に入ってメドックを訪れる度に滞在しました。今思えば随分と贅沢をしていたものです。初めて訪れた時に、このホテルのシェフ・ソムリエとして活躍していたのが何と30歳にも満たない北海道出身の日本の若者であることに吃驚してしまいました。彼のワインについての優れた知識をカズ家でも十分認めていたのでしょう。だから本場ポイヤックの2つ星レストランで、フランス人のソムリエを従えて堂々とシェフ・ソムリエの地位を勝ち取ることができたのでありましょう。彼からワインのことについていろいろと教えていただきました。カーヴにあったメドックの銘醸ワインを原価で分けて貰い日本へ送ったこともありました。ある時、彼はいつかメドックで葡萄畑を買って、自分でワインをつくってみたいと夢を語ってくれました。大きな夢があって羨ましいなと思ったものです。当時ボルドーで最も有名な日本人の一人だったのかもしれません。現在は独立してパリでビストロを開いていると仄聞しております。彼のことだからパリでも思う存分に力を発揮し大活躍されていることでしょう。近い将来またメドックに戻ってきて、長年の夢を実現して欲しいものです。
ここ「コルディヤン・バージュ」ではもう一つ思い出があります。それは初めて訪れた17年前のことでした。朝食を一人で食べていた時に、隣の席で同じく一人で食べていた紳士が言葉を掛けてくださり、それから一頻りワイン談義がはじまったのです。あなたが今、注目しているワインは何かと質問されたので、グラーヴのシャトー・ド・フューザルの白と答えたところ、 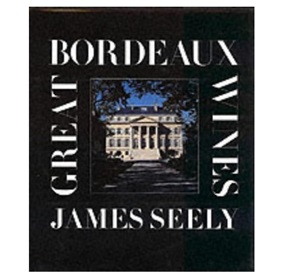 それは良いところに目を付けていると大層褒めていただきました。そしてちょっと待っていてくれないかと言って、彼の部屋から分厚い一冊の本を持って戻って来られました。実は、件の紳士はジェームズ・シーリー(James Seely)という英国の高名なワイン作家で、持参された本は『Great Bordeaux Wines(偉大なボルドー・ワイン)』という大著でした。彼曰く、今日はこれからアラブの王族をシャトーへ案内するのでこの本が必用なため、あなたに贈呈できないのが残念だと。彼はボルドーだけでなくフランス各地のワインの本も数多く出版しておりました。すっかり意気投合して、暫し二人でワインの話に夢中になりました。別れる際にはお互い名残惜しく写真を1枚撮りました。その後はどうされていらっしゃるのだろうかと思って今回調べてみると、彼のご子息クリスチャン・シーリー(Christian Seely)がポイヤック村の有名な格付け第2級のシャトー・ピション・ロングヴィル・バロンの社長をしていることが分かりました。私が「コルディヤン・バージュ」で味わったあの懐かしいピション・ロングヴィル・バロン1985年のシャトーの社長とは!ワインを介して人との巡り会いは不思議で実に面白いものです。もし、またボルドーへ行く機会があれば、お会いしてみたいなと思っています。 それは良いところに目を付けていると大層褒めていただきました。そしてちょっと待っていてくれないかと言って、彼の部屋から分厚い一冊の本を持って戻って来られました。実は、件の紳士はジェームズ・シーリー(James Seely)という英国の高名なワイン作家で、持参された本は『Great Bordeaux Wines(偉大なボルドー・ワイン)』という大著でした。彼曰く、今日はこれからアラブの王族をシャトーへ案内するのでこの本が必用なため、あなたに贈呈できないのが残念だと。彼はボルドーだけでなくフランス各地のワインの本も数多く出版しておりました。すっかり意気投合して、暫し二人でワインの話に夢中になりました。別れる際にはお互い名残惜しく写真を1枚撮りました。その後はどうされていらっしゃるのだろうかと思って今回調べてみると、彼のご子息クリスチャン・シーリー(Christian Seely)がポイヤック村の有名な格付け第2級のシャトー・ピション・ロングヴィル・バロンの社長をしていることが分かりました。私が「コルディヤン・バージュ」で味わったあの懐かしいピション・ロングヴィル・バロン1985年のシャトーの社長とは!ワインを介して人との巡り会いは不思議で実に面白いものです。もし、またボルドーへ行く機会があれば、お会いしてみたいなと思っています。
夕闇迫るメドックを後にして、ホテル「ブルディガラ」に急いで戻り荷物を取って、今宵ボルドーで最後の宿となる「ヴィクトリア・ガーデン」へ向かいます。ここは私がボルドー滞在中ずっとお世話になった思い出のホテルです。 次回はフランスとスペインにまたがるバスク地方(ビアリッツ、サン・ジャン・ド・リュズ、サン・セバスチャン)の旅をお話ししようと思います。 |
上の |