|
ドン・キホーテの時代のスペイン・ワイン

|
ドン・キホーテについては前回で終わりにしようと思っていましたが、当時のスペイン・ワインを語らずに終わることは忍びなく、もう少し続けることにいたします。  さて、『ドン・キホーテ』の登場人物たちは盛んに祝杯を挙げてワインを飲んでいますが、作者のセルバンテス(1547-1616)が当時のスペイン・ワインをどう評価していたのかは、残念ながらこの物語からでは伺い知ることができません。果たして「カマチョの婚礼」の大宴席ではどんなワインが出たのでしょうか。当時のことですから、地元ラ・マンチャのワインに決まっているでしょうが・・・。ひょっとすると、広大なラ・マンチャの南端にある、昔から有名なバルデペーニャスのワインかもしれません。ドン・キホーテの中には100回近くワイン(ぶどう酒)が登場しますので、こうして自分なりにあれこれとワインを推測しながら読みすすめていくのも楽しいことです。 さて、『ドン・キホーテ』の登場人物たちは盛んに祝杯を挙げてワインを飲んでいますが、作者のセルバンテス(1547-1616)が当時のスペイン・ワインをどう評価していたのかは、残念ながらこの物語からでは伺い知ることができません。果たして「カマチョの婚礼」の大宴席ではどんなワインが出たのでしょうか。当時のことですから、地元ラ・マンチャのワインに決まっているでしょうが・・・。ひょっとすると、広大なラ・マンチャの南端にある、昔から有名なバルデペーニャスのワインかもしれません。ドン・キホーテの中には100回近くワイン(ぶどう酒)が登場しますので、こうして自分なりにあれこれとワインを推測しながら読みすすめていくのも楽しいことです。
前編では、「時おり、ぶどう酒の革袋を傾けてぐびりぐびりと飲んでいたが、その満足気な様子ときたら、恐らくマラガで一番の居酒屋の亭主ですら羨望を覚えたにちがいない」と、ドン・キホーテは従士サンチョ・パンサの飲みっぷりを称えています。それもその筈、サンチョは利き酒にも自信があり、それはわが一族の代々の特性であると鼻高々に自慢しておりました(vol.128)。ところが後篇になると一転して、ドン・キホーテはサンチョに向かって節度あるたしなみを勧め、「飲むのはほどほどにせよ。ぶどう酒が過ぎると秘密を守れず約束を果たすこともできぬぞ」と諭しています。この場面などはなかなか印象的です。 実をいいますと、その頃のスペイン・ワインは国外ではそれ程評判は良くなかったようです。というのは、当時のスペインを旅した著名人の中には、スペイン・ワインについて痛烈な批判を書き残した者もいるからです。例えば、「スペインではワインの生産量が少ない。それと何処に行ってもワインがまずい。革袋に入れて保存するから、どうしても嫌な風味がワインについてしまう。それにこの国にはワイン蔵というものが殆どないから、ワインを暑過ぎる部屋に置きっぱなしにして台無しにしてしまうのだ。更にいただけないのは、大概の酒屋でワインを素焼きの大きな壺に入れて戸外に置いていることだ。この壺からワインを汲んでは素焼きの大鉢に移し、他のワインと混ぜ合わせて量り売りしている。大鉢の中にこれまた素焼きの容器を何度も沈めてはワインを汲んで、もっと大きな容器に入れて売るのだ。容器の大きさは様々で、夫々の値段が決まっている・・・うまいワインができるのはアンダルシア、エストレマドゥーラ、グラナダ。それとムルシア、アラゴン、カスティーリャでも少しつくられている」(A・ジューヴァン著『ヨーロッパの旅人たち』(パリ、1672年))と、手厳しい筆致で綴られております。ワインの貯蔵方法が不適切だったという点で、この記述は正しいと思います。ですが、量も質も大したことがなかった、というのは大きな間違った見方であると思います。実際に調べてみますと、黄金世紀のスペインでは良質のワインを大量に生産していたことが分ります。スペインにおいて今日にも通じるワイン産地の骨格が形成されたのは、16世紀から18世紀であるとされているからです。特に、量の点でいえば『ドン・キホーテ』の舞台となったラ・マンチャの大平原は、スペインで最も多くのワインを生産する地区でありました。  『ドン・キホーテ』の作者、セルバンテスは、  ラ・マンチャ地方のシウダー・レアル産ワインをとても気に入っていたようです。著書の『模範小説集』(1613年)の<ガラスの学士>の中でも、「笑いの神(酒神バッカス)の住処たるシウダー・レアル ― これはむしろ、シウダー・レアル(王の都)というよりシウダー・インペリアル(帝都)とすべきである」と絶賛しています。そして、「私は、機会があればぶどう酒を飲む。時には機会がなくても飲む」と言っているくらいですから、相当な愛飲家でありワイン通でもあったのは確かなようです。そして、マドリード地方のサン・マルティン・デ・バルデイグレシアス産赤ワインを“スペイン最高峰”として高く評価しておりました。当時、この赤ワインは濃厚で力強い甘口で、アルコール度数も高かったようです。古代ローマ時代から一般的に甘口ワインが好まれていました(vol.97)。 ラ・マンチャ地方のシウダー・レアル産ワインをとても気に入っていたようです。著書の『模範小説集』(1613年)の<ガラスの学士>の中でも、「笑いの神(酒神バッカス)の住処たるシウダー・レアル ― これはむしろ、シウダー・レアル(王の都)というよりシウダー・インペリアル(帝都)とすべきである」と絶賛しています。そして、「私は、機会があればぶどう酒を飲む。時には機会がなくても飲む」と言っているくらいですから、相当な愛飲家でありワイン通でもあったのは確かなようです。そして、マドリード地方のサン・マルティン・デ・バルデイグレシアス産赤ワインを“スペイン最高峰”として高く評価しておりました。当時、この赤ワインは濃厚で力強い甘口で、アルコール度数も高かったようです。古代ローマ時代から一般的に甘口ワインが好まれていました(vol.97)。
他のワイン産地も抒情詩の中で讃えられています。「いとも貴きワインの故郷、イェーペスからオカーニャを巡れば、その美酒が私の足をとる」と。スペイン黄金世紀のワインについて古典文学研究者のミゲル・エレロ・ガルシア(1895-1961)は著書『17世紀スペインの生活』の中で、  日常の食卓で飲まれた良質なワイン、そしてマドリード地方でつくられていた極上食後酒のモスカテルなどのように、当時最良といわれたワインをいくつか紹介しています。なかでも一番ポピュラーだったのが、カラバンチェル産の赤と白で、旅籠や居酒屋ではこれらを混ぜ合わせて客に出すことが多かったと記しています。これにはちょっと吃驚させられますが、赤と白を混ぜる飲み方は、つい最近まで行われていたようです。大衆的なカラバンチェルに対して、宮廷で最もよく飲まれていたのはバルデモロ産のワインでした。マドリードの洗練された愛飲家たちは、バルデモロのワインが品薄にならないように村の居酒屋で売ることを禁じたほどで、この小さな村でつくられる王室御用達ワインの虜となったようです。極上モスカテルはピントでもつくられており、その名声は他の地方にも聞こえていました。このモスカテルを赤ワインと混ぜて水で割り、ハチミツとスパイスを加えて、カラスパダという人気の飲み物もありました。 日常の食卓で飲まれた良質なワイン、そしてマドリード地方でつくられていた極上食後酒のモスカテルなどのように、当時最良といわれたワインをいくつか紹介しています。なかでも一番ポピュラーだったのが、カラバンチェル産の赤と白で、旅籠や居酒屋ではこれらを混ぜ合わせて客に出すことが多かったと記しています。これにはちょっと吃驚させられますが、赤と白を混ぜる飲み方は、つい最近まで行われていたようです。大衆的なカラバンチェルに対して、宮廷で最もよく飲まれていたのはバルデモロ産のワインでした。マドリードの洗練された愛飲家たちは、バルデモロのワインが品薄にならないように村の居酒屋で売ることを禁じたほどで、この小さな村でつくられる王室御用達ワインの虜となったようです。極上モスカテルはピントでもつくられており、その名声は他の地方にも聞こえていました。このモスカテルを赤ワインと混ぜて水で割り、ハチミツとスパイスを加えて、カラスパダという人気の飲み物もありました。
 他の産地からは、宮廷付きの聖職者たちが贔屓にしていたアルコベンダスのような粗削りで素朴なワインがマドリードに送られていました。花のようなアロマとメロンや白桃を想わせる華やかな香りをもつ甘口のモスカテルは、当時の宮廷の女官たちに愛されていましたが、中でも最高とされていたのがアルカラ・デ・エナレス産のものでした。これらの産地は王宮のあるマドリードから近かったこともありますが、とはいえそこでつくられるワインがスペインの中で最も洗練されていたかというとそうでもなかったようです。宮廷の宴席でよく飲まれていた聖なるワイン、サン・マルティン・デ・バルデイグレシアスの赤ワインは別として、他の産地にもさらにすばらしいワインがあったからです。 他の産地からは、宮廷付きの聖職者たちが贔屓にしていたアルコベンダスのような粗削りで素朴なワインがマドリードに送られていました。花のようなアロマとメロンや白桃を想わせる華やかな香りをもつ甘口のモスカテルは、当時の宮廷の女官たちに愛されていましたが、中でも最高とされていたのがアルカラ・デ・エナレス産のものでした。これらの産地は王宮のあるマドリードから近かったこともありますが、とはいえそこでつくられるワインがスペインの中で最も洗練されていたかというとそうでもなかったようです。宮廷の宴席でよく飲まれていた聖なるワイン、サン・マルティン・デ・バルデイグレシアスの赤ワインは別として、他の産地にもさらにすばらしいワインがあったからです。
トレド地方では、当時からイェーペスとエスキビアスのワインが高く評価されていました。エスキビアスはセルバンテスのお気に入りの銘柄でもあったようです。スペイン最高の劇作家・詩人、ロペ・デ・ベガ(1562-1635)にも称えられ、そして、スペイン文化の黄金時代を代表する劇作家、ティルソ・デ・モリーナ(1579-1648)にいたっては『恩寵の騎士』の中で、「トレドのエスキビアスはおまえに優しく接吻し、口を通って魂の中まで入り込む」とまで高く評価しておりました。 そして、当時最高のワインを産出していたのが、セルバンテスお気に入りのラ・マンチャ地方のシウダー・レアルでした。この地のワインがあまりにも誉れ高かったためシウダー・レアルという地名が品質の高さを示す代名詞になったほどです。そのため、ラ・マンチャ地方の多くの村々がシウダー・レアルの銘柄でワインをつくるようになりました。このワインはボリューム感と果実味があり、アルコール度数が高く、色も濃かったため、水や白ワインと混ぜても十分な存在感があったのでしょう。軽いワインがマイナーとなった現在、ラ・マンチャ地方でつくられているワインは、ある意味、かつてのシウダー・レアルとタイプが似ているのかもしれません。ラ・マンチャ地方のワインがスペインの古典文学作品にしばしば登場するのは、当時のシウダー・レアルの名声を思えば当然なことなのでありましょう。  セルバンテスは『ドン・キホーテ』の中で、ラ・マンチャ地方のワインばかり触れていますが、それは主人公であるドン・キホーテが遍歴したのがこの地方だったから、という以外にも先に述べたように生産量の多さがその理由にあったのです。現在と同様に、当時もスペイン・ワインの大半はカスティーリャの広大なメセタ(中央台地)の南部に位置する、あの白い風車が点在するラ・マンチャで生産されていたのでした。しかし、かつてラ・マンチャ以外の産地にも評価の高いワインがいろいろありましたが、これについてはシェリーと共にまたいつか別の機会に述べることにして、「誰だってぶどう酒の旨さにゃかないませんよ。神様のお陰でね」とのサンチョの言葉を以て、ドン・キホーテの時代のワインを巡る旅をひとまず終えることにします。 当時のワインについて簡単にまとめてみますと、白はフルーティで香り高く、赤は逞しく、デザートワインは濃厚で酒精が強いものであり、殆どのワインはアルコール度数が高く、色が濃く、革袋から染み出た松脂やその他の成分に風味が影響されておりました。それらはまさしく、更に強大になることを夢見ていた当時のスペイン人の血管に流れていた血の如きワインであったであろうことが想像できます。  ついでにと言っては何ですが、ワインとは切っても切れない関係にあるスペインのチーズについて少し語ってこの章を終わりたいと思います。チーズについてはフランスのブリヤ・サヴァラン(1755-1826)の名著『味覚の生理学』の中で、「チーズのないデザートとは、片目のない美女と同じである」といったアフォリズムに見られように大切なデザートでありました。食事の時にワインを飲みすすめていって、最も堪能するのは、食後のデザートにはいる頃に沢山のチーズが大きな皿に載せられてお目見えする時です。こう思っただけで、血湧き、肉躍るところまでいかないまでも、ついつい「ア・ヴォートル・サンテ(Á votre santé!もう一杯やりましょうか)」と言いたくなるのは私ばかりではないでしょう。 ドン・キホーテと旅する従士サンチョ・パンサにとっても、チーズは必要欠くべからざるものでした。ある時、旅の必需品の提供を申し出られたサンチョは、「半かけチーズと半かけのパン以外には何も要らないと答えた」とあります。ラ・マンチャが昔も今もチーズの産地であることを考えればいよいよもって納得のいくところです。スペインにおける最大のチーズの生産地はワインと同じくラ・マンチャ地方なのですから。セルバンテスと同時代のユーモア詩人バルタサール・デル・アルカサール(1530-1606)は、チーズの食べ合わせについて面白いことを記しています。  「今のおいらは 3つのものに首ったけ 別嬪イネスと生ハム それにチーズにくるんだ茄子なのさ」と。女性とハムとチーズ、それに茄子を並列させるとは、何とも奇妙な発想ですが、ドン・キホーテの国スペインはやはり茄子の里なのだということが改めてよく分ります(vol.132)。『ドン・キホーテ』に、「肉を食べ終えると、毛皮の上にしなびたどんぐりをしこたま広げ、おまけにしっくいにも負けぬほど固いチーズの半切れを出した」とあります。このようにラ・マンチャのチーズは『ドン・キホーテ』の中でワインと同様に頻繁に登場する食べ物なのです。ドン・キホーテが旅の出発第1日目に立ち寄るラピセ峠では今も手づくりのラ・マンチャのチーズが出るそうです。スペイン・チーズの最高級品とされていますが、一般のヨーロッパ・チーズとは製法が異なり、古くオリエントで行われていた方法を忠実に継承する唯一のチーズだと言われています。原料は羊乳。「・・・、もっと詳しくいうと、羊の乳のチーズだっただよ」とサンチョが言っていることからも、これは今でもスペインで有名なチーズ、マンチェゴでありましょう。 「今のおいらは 3つのものに首ったけ 別嬪イネスと生ハム それにチーズにくるんだ茄子なのさ」と。女性とハムとチーズ、それに茄子を並列させるとは、何とも奇妙な発想ですが、ドン・キホーテの国スペインはやはり茄子の里なのだということが改めてよく分ります(vol.132)。『ドン・キホーテ』に、「肉を食べ終えると、毛皮の上にしなびたどんぐりをしこたま広げ、おまけにしっくいにも負けぬほど固いチーズの半切れを出した」とあります。このようにラ・マンチャのチーズは『ドン・キホーテ』の中でワインと同様に頻繁に登場する食べ物なのです。ドン・キホーテが旅の出発第1日目に立ち寄るラピセ峠では今も手づくりのラ・マンチャのチーズが出るそうです。スペイン・チーズの最高級品とされていますが、一般のヨーロッパ・チーズとは製法が異なり、古くオリエントで行われていた方法を忠実に継承する唯一のチーズだと言われています。原料は羊乳。「・・・、もっと詳しくいうと、羊の乳のチーズだっただよ」とサンチョが言っていることからも、これは今でもスペインで有名なチーズ、マンチェゴでありましょう。
最後に唯一残念なことは、『ドン・キホーテ』とラ・マンチャに纏わる料理や食卓風景そして挿絵をたっぷり使ったGarcía Solana(ガルシーア・ソラーナ)著『La cocina en El Quijote(ドン・キホーテの料理)』という、題名からして楽しそうな本にとうとう巡り合えなかったことでした。でも、読まないというのもひとつの読み方かもしれません。ドン・キホーテは言っています。「見て信じるのはたやすいが、見ずに信じることにこそ値打ちがあるのだ」と。 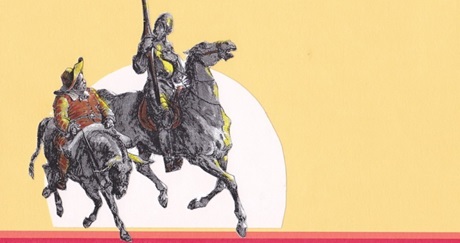 追記 私のことをかつて読売新聞夕刊のコラム「GINZA通信」(2008年、http://perfectnet.jp/bordeaux/yomiuri.pdf)に書いてくださった永峰好美さん(当時プランタン銀座取締役、現在読売新聞東京本社編集委員)が、わが国ワイン界の泰斗、山本博先生と大滝恭子さんと共著で『スペイン・ワイン』(2015年7月、早川書房刊)を出版されました。今や革命的進歩を遂げたスペイン・ワイン ― その歴史から、地勢・気候、葡萄品種、主要な銘柄、生産地、ワイナリー等の最新情報まで ― 全てが分かる好著です。この本を読みながらスペイン・ワインを飲めば、気分はもうドン・キホーテの国スペインです。是非ご一読をお奨めいたします。 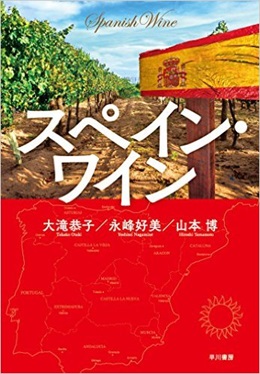 |