|
- シャンソン(1)) -  <フランス革命記念日(パリ祭)> |
今年も「パリ祭」(7月14日、フランス革命記念日)の季節が巡ってまいりました。「パリ祭」というと直ぐに想い浮べるのはシャンソンでしょう。私の主催する銀座< Salon de vin>(サロン・ド・ヴァン、ワイン会)も、例年通り銀座並木通りの「シャンソニエ マダムREI 窓」で、“シャンソンとシャンパンでパリ祭を祝う”と題して賑やかに開催するのを楽しみにしておりましたが、残念ながら今次東日本大震災を機にお店は急遽閉店することになりました。銀座で38年間営んできた老舗がまたひとつ幕を下ろすことになってしまい、言いようのない寂しさを感じております。お店には私の蔵書である100冊余りの17世紀、18世紀にジュネーブで印刷された『フランス農業全書』、そしてエリック・サティの楽譜とシャルル・マルタンのポショワール(vol.52,53,54をご参照ください)を飾 Salon de vin>(サロン・ド・ヴァン、ワイン会)も、例年通り銀座並木通りの「シャンソニエ マダムREI 窓」で、“シャンソンとシャンパンでパリ祭を祝う”と題して賑やかに開催するのを楽しみにしておりましたが、残念ながら今次東日本大震災を機にお店は急遽閉店することになりました。銀座で38年間営んできた老舗がまたひとつ幕を下ろすことになってしまい、言いようのない寂しさを感じております。お店には私の蔵書である100冊余りの17世紀、18世紀にジュネーブで印刷された『フランス農業全書』、そしてエリック・サティの楽譜とシャルル・マルタンのポショワール(vol.52,53,54をご参照ください)を飾 らせて貰っていました。私にとってはわが書斎のようでもあり、とても愛着のあるステキなお店でした。でも、このお店を元気に取り仕切っていたオ―ナー兼シャンソン歌手そして作詞・作曲家でもある友人の長坂玲さんは、震災後銀座の社交の場を続けていくことの難しさを瞬時に感じ取り、閉店の決断をされました。経営者としての洞察と潔さに敬意を表したいと思います。 らせて貰っていました。私にとってはわが書斎のようでもあり、とても愛着のあるステキなお店でした。でも、このお店を元気に取り仕切っていたオ―ナー兼シャンソン歌手そして作詞・作曲家でもある友人の長坂玲さんは、震災後銀座の社交の場を続けていくことの難しさを瞬時に感じ取り、閉店の決断をされました。経営者としての洞察と潔さに敬意を表したいと思います。今回は<シャンソン>について、長坂玲さん(芸名:リリ・レイ。シャンソンのブログとして高い人気を誇る:http://blog.goo.ne.jp/1955piafsukiをご参照ください)へのオマージュを捧げつつお話していきたいと思います。私事に亘って恐縮ですが、長坂玲さんとは東京藝術大学声楽科2年生の19歳の時からの長い友人です。その後、彼女は東京藝術大学大学院へ進まれ、更にロータリーインターナショナル財団奨学金を得てベルギーの王立音楽院へ留学し、最優秀な成績で卒業されました。そしてオペラ歌手として8年もの長い間、ベルギー、フランスを中心にヨーロッパ、北アフリカ等で活躍されたのです。帰国後暫くして御父上様の亡き後にクラブ等を含めた銀座並木通りの5軒のお店の 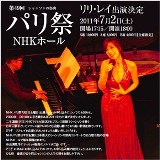 経営を任され、これを機にシャンソン歌手に転向し新たな活躍の場を得ることになります。現在は毎年パリをはじめ世界各国で、そして日本各地でリサイタルを開催し大活躍されております。この7月2日にはNHKホールで毎年開催される「第49回パリ祭」にも連続して出演されました。今後は芸術活動一筋に邁進されつつ、後進の指導のために成城の自宅を開放して「シャンソン教室」も続けられるとのことです。長坂玲さんの今後の芸術活動に幸多かれと心からエールを送りたいと思います。 経営を任され、これを機にシャンソン歌手に転向し新たな活躍の場を得ることになります。現在は毎年パリをはじめ世界各国で、そして日本各地でリサイタルを開催し大活躍されております。この7月2日にはNHKホールで毎年開催される「第49回パリ祭」にも連続して出演されました。今後は芸術活動一筋に邁進されつつ、後進の指導のために成城の自宅を開放して「シャンソン教室」も続けられるとのことです。長坂玲さんの今後の芸術活動に幸多かれと心からエールを送りたいと思います。(リリ・レイさんが昨年のシャンソン・フォリーで熱唱された「パダン・パダン」をお聴きください。http://www.youtube.com/watch?v=WtN69szcS54) そもそも私が<Salon de vin>の会を立ち上げましたのは、2004年にボルドー留学から帰国して間もない頃、彼女からお店に来ませんかとお誘いの声が掛かったのがはじまりです。早速に飛んで行き、彼女の経営する銀座の寿司屋さんで鮨をつまみながら話していると、折角遥々ボルドーまで行ってワインを学んできたのだから、その経験を生かして何かやってみませんかと言われました。彼女はどこでも好きな銀座のお店を土曜日、日曜日に自由に使って構わないと言ってくださいました。勿論、無料で提供しますと。大きなプレゼントをいただきました。彼女の親身なるご支援・ご協力をいただきながら、このよう  にして2005年2月に銀座並木通りの「シャンソニエ マダムREI」で、<Salon de vin>の会は産声をあげることになりました。爾来、多士済々の皆様にお集まりいただき、温かいご愛顧のお陰をもって今年で早や6年目を迎えました。誠に感慨深いものがあります。この7月からは懐かしの銀座をあとにして、青山の旧男爵邸「ミュージアム にして2005年2月に銀座並木通りの「シャンソニエ マダムREI」で、<Salon de vin>の会は産声をあげることになりました。爾来、多士済々の皆様にお集まりいただき、温かいご愛顧のお陰をもって今年で早や6年目を迎えました。誠に感慨深いものがあります。この7月からは懐かしの銀座をあとにして、青山の旧男爵邸「ミュージアム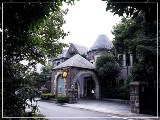 1999 ロアラブッシュ」へ場所を移し開催することになりました。 1999 ロアラブッシュ」へ場所を移し開催することになりました。長坂玲さんのお陰で、サラリーマン生活をリタイアした後の私の人生は大きく変わりました。感謝のみです。ワインという自分の好きなことをやって、皆様に喜んでもらえる。幸せだなとしみじみ感じております。その間の状況は留学中のことを含めて読売新聞、日経BPそして東京新聞に掲載されました(「目次」を開きますとご覧いただけます)。 さて、全くの門外漢が「シャンソン」を語るなど誠に恐れ多いのですが、長坂玲さんに大きな刺激を受けて、私なりにシャンソンの歴史を思いつくままに書き綴ってみたいと思います。 フランス語で「歌」という言葉には、辞書を調べてみますと「シャンソン(chanson)」の他に、「シャン(chant)」、「ロマンス(romance)」そして「メロディ(mélodie)」があります。歴史的に見ると「シャンソン」は11世紀にラテン語で「カンティオ(cantio)」と呼ばれ、「シャン」は12世紀に「カントゥス(cantus)」、それが現在、イタリア語に「カント(canto)」として残っていることが分かります。 シャンソンは確かに最も「ポピュレ―ル(Populaire,民衆的な、大衆的な)」芸術でありますが、フランスの歴史を紐解くと、いつも歌っていたのは必ずしも民衆だけではありません。領主、貴族、知識人もまた歌っていたのであって、彼らはその社会的身分から他の芸術にも接し得た人たちです。ですからシャンソンは宮廷風歌謡、民間伝承シャンソン、学者風シャンソン、職人風シャンソンといったように、極めて多様なジャンルをもった普遍的芸術でもあるように思うのです。シャンソンのことを「エール・デュ・タン(Air du temps)」とも言います。つまり、時代の様相です。徐々に大衆文化に育っていくシャンソンが、その時代の庶民によって様相を変えていくことは当然のことだったのでしょう。シャンソンは歌詞とメロディがワインと食事と同じように、上手くマリアージュしたものと言えるかもしれません。フランス人のシャンソン趣味は、いっさいのものをシャンソン化する能力とでもいったらいいのでしょうか。 古来より歌と踊りは、笑いと同様に人間固有のものであることは「西馬音内盆踊り」(vol.74,75,76,77をご参照ください)を見ても分かる通りですが、一層古い形式は果たしてどちらなのでしょうか。歌か、踊りか、興味あるところですが、その判断は民俗学者にお任せすることにしましょう。 さて、シャンソンの歴史は古く、9世紀頃、フランス語の誕生と共に生まれたものであると考えられるし、それが後世に残るようになったのは、11世紀から13世紀頃までの南フランスに生まれた「トゥルバドゥール(troubadour,南仏吟遊詩人)」たちによってであるというのが定説のようです。作品はオック語で書かれています。丁度十字軍の時代でもあり、彼らを励ますためのシャンソン、妻や恋人と別れる哀歌などもあったのでしょう。 12世紀後半からはトゥルバドゥールの詩は北に移り、そして西ヨーロッパ全域に広がっていきます。北フランスの吟遊詩人を「トゥル 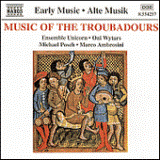 ヴェール(trouvère)」と呼び、彼らは南のトゥルバドゥールから受け継いだシャンソンを更に発展させていきました。また印刷術の発明はシャンソンをも一変させ、16世紀初めにはヴェニスでフランスのシャンソンが初めて出版され、益々発展の道を辿っていくようになりました。 ヴェール(trouvère)」と呼び、彼らは南のトゥルバドゥールから受け継いだシャンソンを更に発展させていきました。また印刷術の発明はシャンソンをも一変させ、16世紀初めにはヴェニスでフランスのシャンソンが初めて出版され、益々発展の道を辿っていくようになりました。でもシャンソンを歌う人たちが公に世に知られるようになったのは18世紀になってからのことです。シャンソン歌手兼劇作家のピロン、コレ、クレビヨンの3人が集まり「シャンソニエ協会」なるものを結成し、それを「カヴォー(caveau,小さい穴倉)」と呼んだのです。そして、近代になってシャンソンは「カフェ・コンセール(café-concert)」において本格的に栄えていきます。カフェ・コンセールとは喫茶したり食事をしながらシャンソンを聴いたりできるお店のことです。19世紀中頃には「アンバサドゥー  ル(Ambassadeur,大使)」がシャンゼリゼで産声をあげました。コンコルド広場に近い最高級のホテル・クリヨンには外国の大使や高官が泊まり、その人たちが度々お客として来店するところから名付けられたものです。1850年代にはパリに続々と有名なカフェ・コンセールができていきました。 ル(Ambassadeur,大使)」がシャンゼリゼで産声をあげました。コンコルド広場に近い最高級のホテル・クリヨンには外国の大使や高官が泊まり、その人たちが度々お客として来店するところから名付けられたものです。1850年代にはパリに続々と有名なカフェ・コンセールができていきました。ここに20世紀初頭からのカフェ・コンセールの変遷とそこに集う芸術家たちの様子や人情が鮮やかに伝わってまいります、藤田嗣  治画伯がお書きになられた『スーブニール』と題する一節があります。少々長くなりますがご紹介いたします。「私が巴里へ着いたのは、欧州大戦以前の1913年であった。リュ―・デ・ラ・ゲーテ、街の周囲にはまだカフェ・コンセールが1900年の空気をそのまま表通りのテラース迄を厚いカーテンで取り囲んで、奥まったステージに駆け出しのアーチストが、ロートレックの画の様に巴里の流行歌を歌っていた。毎晩の様にスケッチに出掛けて、歌も聞いていた。ゲーテ通りのボビノにシュバリエ、ダミヤ等が未だ世界的に有名にならぬ本当の巴里のブレドブレの唄をうたって、界隈の男女を笑わせたり泣かせていた。イベット・ギルベール、マイヨル、ドラネム等は既に名を成して、ロートレックやホーラン等に描かれていた頃であった。 治画伯がお書きになられた『スーブニール』と題する一節があります。少々長くなりますがご紹介いたします。「私が巴里へ着いたのは、欧州大戦以前の1913年であった。リュ―・デ・ラ・ゲーテ、街の周囲にはまだカフェ・コンセールが1900年の空気をそのまま表通りのテラース迄を厚いカーテンで取り囲んで、奥まったステージに駆け出しのアーチストが、ロートレックの画の様に巴里の流行歌を歌っていた。毎晩の様にスケッチに出掛けて、歌も聞いていた。ゲーテ通りのボビノにシュバリエ、ダミヤ等が未だ世界的に有名にならぬ本当の巴里のブレドブレの唄をうたって、界隈の男女を笑わせたり泣かせていた。イベット・ギルベール、マイヨル、ドラネム等は既に名を成して、ロートレックやホーラン等に描かれていた頃であった。私の巴里生活も長く成った。空襲を受けて巴里のカフェ・コンセールは全く  姿を消して自滅して仕舞った。戦争後に大象があったムーラン・ルージュもカジノ・ド・パリも改築された。フォリー・ベルジエールもロココの姿を改めてモダンな化粧をした。悲運にのみ苦しんだミスタンゲットは世界的のブエデットに成り終え、シュバリエも彼女の引き立てで人気は物凄いものになった。ベルギーから、イボンヌ・ジョルジュが突如として巴里に現れて、巴里のスノッブ連中の人気をさらった。 姿を消して自滅して仕舞った。戦争後に大象があったムーラン・ルージュもカジノ・ド・パリも改築された。フォリー・ベルジエールもロココの姿を改めてモダンな化粧をした。悲運にのみ苦しんだミスタンゲットは世界的のブエデットに成り終え、シュバリエも彼女の引き立てで人気は物凄いものになった。ベルギーから、イボンヌ・ジョルジュが突如として巴里に現れて、巴里のスノッブ連中の人気をさらった。ダミヤがジゴレットの唄を棄ててフランスの古歌を唄い出した。ジョセフィン・ベーカーが落雷の様にシャンゼリゼ―に現れて、巴里のブルジョワは腰を抜かす様に驚いた。シュバリエはハリウッドへ渡った。私はこれ等の歌手と友人仲間と成って舞台以外にアンチミテの内によく歌ってきかせて貰った。パレ・ロワイヤルのシェ・カミーの地下室に歌っていて誰も相手にもしなかった小さなボワイエが、俄かにランセされて一躍世界的に有名になった。イボンヌ・ジョルジュが肺病で死んだ。イサドラ・ダンカン(vol.75,76,77をご参照ください)も非業の最後をとげた。私らは作品を競売して救助した。巴里の名を成した芸術家はすべて二度は苦しい貧乏生活を味わっている。この共通な生活の親密さで固く結ばれて、すべての種類の芸術家が仲良しであることはうれしいことである。 フランスのシャンソンは、各自がその想い出を唄っている様に、貧乏の中に笑い興じたり、労苦を気にかけぬ呑気さがあったり、成功したからと言って、成金気分のヌーボー・リッシュの嫌味が無いところは、ここから出発している様である(後略)」と。 次回はモンマルトルの丘の麓にあるキャバレー、「シャ・ノワール(Chat Noir,黒猫)」に集う文化人たち、そしてエリック・サティやボリス・ヴィアンとシャンソンの係りなどについて述べてみたいと思います。 |
上の |